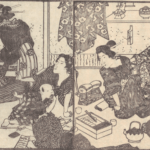江戸のSDGs? 「紙屑買い」はなぜ商売として成立したのか?
転職してみたい江戸のお仕事 第3回 「紙屑買い」

子どもが習字を練習した紙や、商家の大福帳など、現在では捨ててしまうような紙屑を買い取り、漉き直して再生紙として利用する。紙屑買いは、古典落語の中に「屑屋」として登場するほど、江戸の人々にとって身近な存在であった。イラスト/志水則友
みなさんはブラシなどに絡みついた抜け毛をどうしているだろうか? 江戸時代の人たちは、こうした抜け毛を大切にとっておいた。なぜかというと「落ちはないか」という声とともに『おちゃない』と呼ばれる女性が町内を回ってきて、抜け毛を買い取ってくれるからだ。今の時間でいうと午後2時ごろ、集めた髪の毛を入れた風呂敷を頭の上にのせて、町内を回って抜け毛を集める。この時間は家事もひと段落、掃除も終わって今日の分の抜け毛を拾い集め終わったタイミングなのだろう。買い取り金額についてはよくわからないのだが、子どもの飴玉代くらいにはなったのではないだろうか。
買い取った髪はかもじといって、女性が髪を結う時につかう付け毛として使用された。俗にいう日本髪は、ある程度の長さが必要だからだ。後には歌舞伎役者が被るかつらにも使用されたという。女役だけでなく男役のかつらもあったから、男性のあまり長くない髪はこうしたかつらに使われたようだ。
この商売はもともと紙屑買いが集めて来た不要品の中から髪の毛だけをより分けていた。だんだんと女性の髪型が凝ったものになり、需要が増えたのだろう。髪の毛を専門に集める人が出現したのだ。といっても大量には集まらなかったようだ。
この紙屑買いとはどんな商売なのだろうか。江戸時代には現在の私たちが捨ててしまうようなものを買い取る商人たちが多くいた。その代表的な商売が紙屑買いであった。
大きな籠を背負って声を上げながら町内を回る。江戸の場合、着流しに尻端折り(しりはしょり)で秤と大きな風呂敷を手に持っていた。京都や大坂では「てんかみくず、てんてん」といいながら、町を流す。てんてんとは古手の略で古着のことだ。古着や書き損じた紙、折れた火箸や錆びたハサミ、包丁といった古金属、古器物など、身の回りの不用品を秤で計って買い取った。
買い取ったものは、古着なら古着、紙ならば紙とより分けて、古着は古着屋などに売る。屑屋が買い取ったものの中で一番高額で売れたのは古金属だったという。
さて、屑屋の名前にもなった紙屑だが、これは、立場と呼ばれていた紙屑問屋に持ち込む。紙屑問屋から再生紙業者へと渡るのだが、浅草に再生紙業者が集中していたことからこうした再生紙を浅草紙と呼んでいた。今でいうところのトイレットペーパーだ。
トイレットペーパーといっても当時の紙は、1枚1枚すべて手で漉(す)く。集めた紙を溶かして再び紙にするのだが、紙を煮溶かしても熱いままでは紙を漉くことはできない。そこで再生紙の職人は紙が漉けるように冷めるまで、近くにあった吉原に出かけていく。しかし、女の子と遊ぶ金も時間もないので、ただ見るだけで帰って来る。ここから買う気がないのに商品を見ることを「冷やかす」というようになったという。
再生紙といってもトイレットペーパーだけかと侮るなかれ、古くは天皇の命令は宿紙(しゅくし)とよばれる再生紙で出す決まりとなっていた。
このほかに灰、破れた傘など現代人の私たちから見れば「ゴミ」としか思えないようなものも江戸時代の人々は買い集めてリサイクルしていた。捨てるものといえば、魚の骨などわずかなもので、それらを集めて現在の木場あたりは埋め立てられたという。