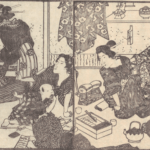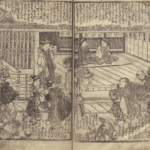江戸時代の人気スイーツ!「飴売り」はなぜパフォーマンスを重視したのか?
転職してみたい江戸のお仕事 第2回 「飴売り」
江戸時代に人気を集めた「飴売り」は、町を異国人風の格好で練り歩きながら飴を売った。どうしてそのような格好をしていたのか、その理由について考察する。

飴売りの飴細工を描いたもの。保温してある飴を取り出して、温かいうちに形を作らなければならない。かつては、葦の茎の先に飴をつけ息を吹き込んで飴を膨らませて形成していたが、現在は衛生上の理由から行われていない。イラスト/志水則友
カラフルな異国の服を着て、派手な帽子を被り、笛を吹きながら歩く男の後を子どもたちが歓声を上げながら追いかける。といってもここは、中世ドイツのハーメルンではなく、江戸時代の江戸の町中だ。江戸の町にハーメルンの笛吹きが登場? いやいや、子どもたちは手に小銭を持ち、それを異国人風の男に差し出している。男は小銭と引き換えに棒状の飴を手渡している。男は「唐人飴(とうじんあめ)」と呼ばれていた飴売りなのだ。
「唐」とは中国にかつてあった国の名前だ。しかし、この時代の人たちにとって唐は、異国を示す言葉であった。だから唐人飴の絵を見る限り中国人というよりは、将軍の代替り時に江戸を訪れる朝鮮通信使のように見えるが、当時の人々は矛盾を感じていなかった。ちなみに華やかな朝鮮通信使の行列は、江戸時代の人々に大変に人気があり、各地のお祭りでこれを真似た人々が登場していた。その祭りの行列が現在に伝えられているところも少なくはない。
では、なぜ飴売りが異国人の格好をしているのかといえば、目立つからだ。いまでも様々なイベントや町中で着ぐるみを着た人やゆるキャラなどからチラシを貰うことがあるだろう。これと同じことなのだ。派手ないでたちで人目を引くがことが目的であったから唐人飴の衣装はこうでなければという明確なものはなかった。笛も異国風ということで戦国時代に日本に伝わったとされるチャルメラを使用。笛ではなく鉦(かね)を叩いて人を集めることもあった。お買い上げのお客様には、サービスで歌や踊りを披露したという。それがとても奇妙なものだったそうで、おそらく飴売りが考えた「唐風」の歌と踊りだったのだろう。
ここまで、唐人飴売りがサービスするのには理由があった。唐人飴以外にも様々な飴売りがいて、過当競争になっていたからだ。例えば、飴を使って鳥を客の目の前で作って見せる「飴の鳥」。のちに客の注文に応じて様々な物の形を作り、藍や紅で彩色を施して、飴細工と呼ばれるようになった。現在でも数は少ないものの、東京の下町の縁日などで鶏や動物、アニメーションのキャラクターなどを手早く作る技を披露している。
飴売りが江戸の町に多かったのは、江戸の人々が甘味を好んだからである。一般に甘味が広まったのは、五代将軍徳川綱吉の治政の元禄年間のころといわれている。当時の飴は、現在の私たちが真っ先に思い浮かべる砂糖を使ったいわゆるキャンディではなく、米などから作られた今でいう晒し飴が大半を占めていただろう。
というのは、砂糖は輸入品でとても高価だったからだ。それでも、人々の要求にこたえるため、オランダから大量の砂糖を買い付け、その代金として日本の貨幣が海外へ運ばれていく。8代将軍徳川吉宗は少しでも輸入量を減らそうと砂糖の国産化を図り、江戸城でサトウキビ栽培を試みている。
これと前後して薩摩藩が奄美などで作った黒砂糖が市場に出回るようになった。また、吉宗の時代からかなり後にはなるが試行錯誤の末、讃岐というから現在の香川県で和三盆(わさんぼん)と呼ばれる国産砂糖の生産が軌道に乗った。今でも和三盆は、香川県の名物である。
こうした、人々の努力の末、高値の花であった甘味が庶民にも手に入るようになり、飴が子供たちに人気のおやつになったのだろう。