日本人が今後の中国渡航で気をつけるべき点とは? 今後も不透明な日中関係
日中関係は依存と対立が併存する複雑な構造にある。最大の貿易相手国として中国市場は日本企業にとって欠かせない一方、安全保障や技術流出、世論感情などをめぐる緊張が高まっている。特に2023年に全面改正された中国の「反スパイ法」は、日本人のビジネスや観光での渡航にも直接的な影響を及ぼしている。
改正法では「国家の安全と利益に関わるあらゆる文書・データ」がスパイ行為の対象となり、その範囲は極めて広範である。政府が「スパイ行為」と認定すれば、明確な証拠がなくとも身柄拘束が可能であり、実際に日本企業の駐在員が拘束される事例も発生している。日本政府は邦人保護の観点から繰り返し注意喚起を行っているが、依然として法運用の透明性は低く、恣意的な適用のリスクは拭えない。
では、一般の日本人が中国に渡航する際、どのような点に注意すべきか。まず重要なのは、自身の行動が中国当局からどのように見えるかを常に意識することである。街頭での写真撮影やドローン使用、工場・港湾・インフラ設備の撮影などは誤解を招く可能性が高い。業務目的の調査や聞き取りも、相手が国営企業や行政関係者であれば「情報収集活動」と見なされる恐れがある。加えて、デジタル機器の取り扱いにも細心の注意が必要である。業務用パソコンに国家安全保障や先端技術に関するデータが含まれている場合、入国時や滞在中にチェックを受ける可能性がある。VPNの使用も原則として違法であり、日本と同じ感覚でインターネットを利用すべきではない。現地の規制に合わせた端末やアプリの管理が求められる。
さらに重要なのは「自分の身は自分で守る」という自覚を持つことである。中国で一度拘束されれば、日本政府や企業であっても即座の救済は難しい。行動履歴や出張目的、面会相手などは事前に社内で共有し、緊急連絡体制を整備しておくべきである。観光客であっても、現地在住者との接触やSNSでの発信が問題視される可能性がある以上、油断は禁物である。
日中関係は今後も「協調と警戒」が同時進行する状態が続くであろう。中国市場の魅力が失われたわけではないが、渡航リスクは確実に高まっている。必要なのは過剰な恐怖ではなく、実態に即したリスク管理である。中国と関わり続ける日本人こそ、法の仕組みと政治状況を正しく理解し、自らの安全保障を常に意識することが不可欠である。
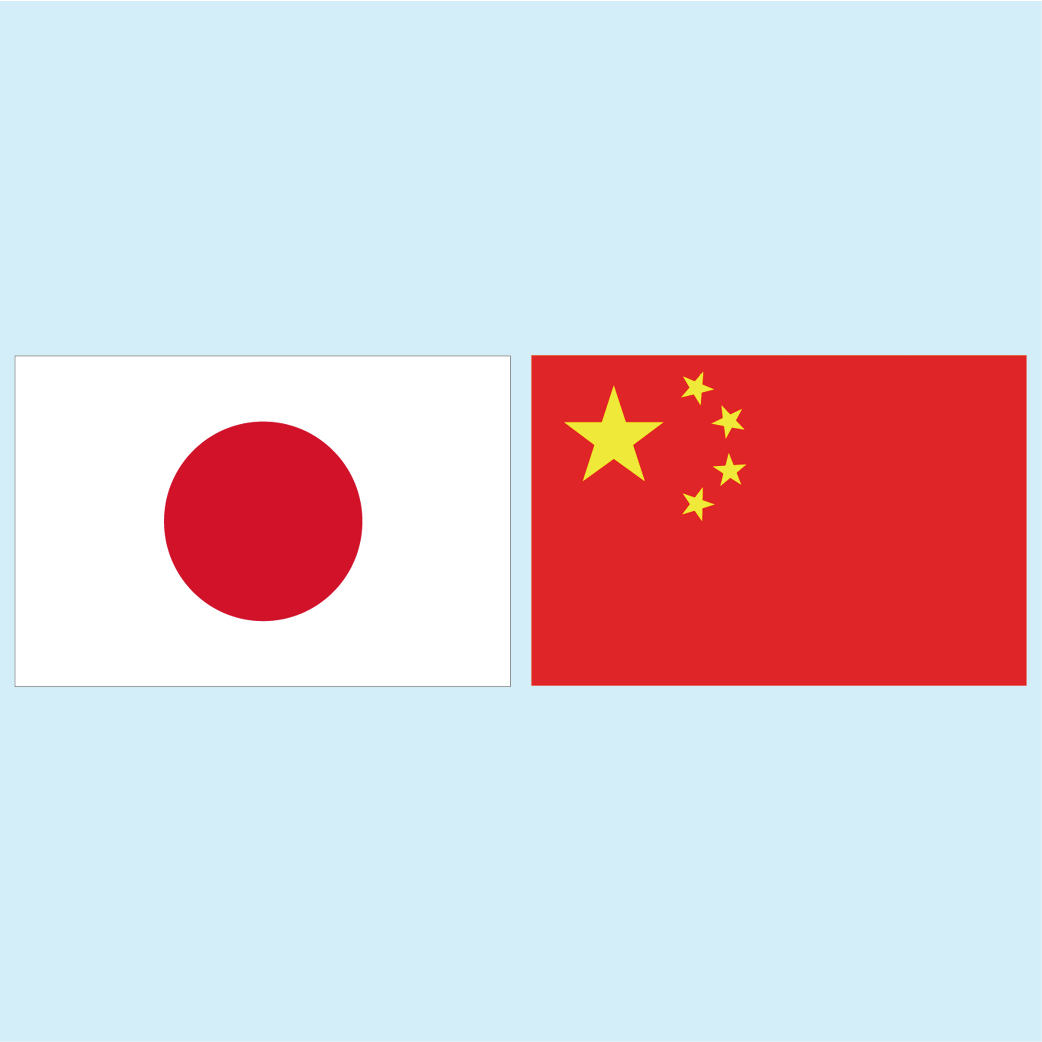
イメージ/イラストAC
写真AC






