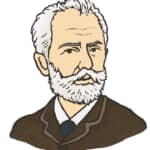日本人を悩ませた“外国人との向き合い方” 外交オンチは昔から!? 威厳を保ちたい「為政者たちのプライド」 が邪魔をする
2025年7月の参院選では外国人政策が争点の一つに浮上し、「日本人ファースト」なるワードがさかんに飛び交った。外国人との付き合い方の難しさは、今に始まったものではない。島国の日本人にとっては、古くからセンシティブな問題であり、時に外交問題に発展することもあった。今回は、古代から近代まで、為政者を悩ませたさまざまな「外国人問題」を紹介したい。
■宋人と対面し「天魔の所為」と罵られた後白河法皇と平清盛
古代の日本において、身近な外国である中国や朝鮮は憧れ、あるいは畏怖の対象だった。邪馬台国や倭の五王の時代は、中国の魏や宋(南朝)に朝貢することで後ろだてとし、飛鳥・奈良時代は積極的に遣隋使・遣唐使を派遣して大陸の先進文明を取り入れた。
外国人に対する見方が変わるのは、遣唐使が廃止された9世紀末以降である。海外との通交は絶え、海外渡航も禁止されて一種の鎖国状態となった。為政者である皇族・貴族の間で外国に対する無関心がはびこり、それはやがて異国を“ケガレ”とみる排外主義的思想となっていく。
9世紀末の宇多上皇は子の醍醐天皇に与えた「寛平御遺誡(かんぴょうのごゆいかい)」の中で、天子は外国人と引見することは避けるべきであり、やむを得ない場合も御簾の中で会うべきであると述べている。
平安末期、平清盛が日宋貿易を始めた時も、保守的な貴族たちから大きな批判をあびた。
ことに嘉応2年(1170)、福原(神戸)の清盛の別荘で、後白河法皇が宋人と対面したことは貴族社会に衝撃を与えた。摂関家の九条兼実(かねざね)は、日記に「天魔の所為か」と記し厳しく糾弾している。
さらに、その翌年、宋の明州の刺史(しし/地方官)から法皇と清盛に贈り物が届いたが、そこに「賜う」と書かれていたことも問題となった。上から目線の手紙に対して貴族たちは怒り心頭に発し、贈り物を受け取ってはならない、返事を出す必要もない、外交慣例を無視した非礼をわびさせよと息巻いた。
だが、高度に中央集権化された宋において、刺史はれっきとした皇帝の名代であり、地方官の権限で行われた贈答ではない。外交に疎いわりに、プライドだけは高い貴族たちにはそこが分からなかったのである。ちなみに、法皇も清盛も宋の「非礼」などは気にせず、恭しく返書をしたため贈答品を送っている。
■フビライを怒らせ蒙古との関係をこじらせた北条時宗
為政者の外交オンチは、武士の時代になっても変わらなかった。そのことを示すのが、中世最大の対外危機、蒙古襲来である。
一般に、この事件はモンゴル皇帝のフビライ・ハンが日本に服属を求める恐喝めいた国書を送り、幕府がそれに反発したために引き起こされたといわれている。
だが、近年の研究で、フビライの国書は日本に通交を求める、丁寧かつ穏当な内容だったことが明らかにされている。ようは、中国で統一王朝が成立した際、周辺諸国に朝貢を求める伝統的な外交手法を踏襲しているにすぎず、日本側が元の建国を言祝ぐ国書を送りさえすれば、穏便にすませられた可能性が高かったというのだ。
実際、朝廷の貴族たちは返書の下書きまで作成した。しかし、時の執権・北条時宗はそれを制止し、徹底的に無視する態度にでたうえ、元の使者を問答無用で処刑したことで、二度の蒙古襲来を招いてしまう。
結果的に、日本はラッキーな“神風”に助けられたが、蒙古襲来の恐怖は長らく日本人のトラウマとなり、ことあるごとに人々を不安にさせた。恐ろしいもの、理不尽なものを表す「ムクリコクリ」という方言は、元軍の主力である蒙古と高句麗に由来するともいわれている。
■明使に対する度を過ぎた拝礼が批判された足利義満
室町幕府の全盛期を築いた足利義満の時代にも、中国・明との外交が問題となった。
元来、義満は朝貢貿易に積極的で、自ら「大明皇帝陛下に奉る」と記した国書と贈答品を送り、明に通交を求めていた。
やがて、明の建文帝から日本国王に認められた義満は、京都の北山第に明の使者を招き、三拝してひざまずくという最大限の礼節を示して国書を受け取った。
平清盛と同じく、体面よりも実利をとったわけだが、明の国書の内容と義満の度を過ぎた表敬儀礼に、プライドの高い貴族はもちろん、幕府方の禅僧や重臣まで不満を抱いたという。
義満の死後、明への朝貢は4代・義持(よしもち)により一時中止されたが、後を継いだ6代・義教(よしのり)が復活させた。
この時、義満が行った三拝してひざまずく「三拝拝跪(さんぱいはいき)」が問題とされ、拝礼は二拝にして立ったまま国書を披見するよう改めるべきとする意見が出たという。拝礼の数を減らしたところで、明の臣下となった日本の立場が変わるわけではないのだが、少しでも日本の威厳を保ちたいという為政者たちのプライドの高さが垣間見えて面白い。

月岡芳年「日本名将鑑 足利義満公」/ロサンゼルス・カウンティ美術館蔵(www.lacma.org)