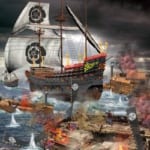江戸の疫癘防除~疫神社の謎①~
武蔵国に描かれた幻の北斗
無病息災を祈った武蔵国の人々

武蔵国地図/国立公文書館 コラージュ作成/戸澤徹
不思議なことを発見した。
なにを見つけたのかといえば、
――十七世紀から十九世紀にかけて、武蔵国に北斗七星が描かれたのではないか。
もしくは、
――江戸時代、篝火(かがりび)を七つ焚き、それを結んで北斗七星に見立てたのではないか。
ということだ。
いったい、どこに描かれたのかといえば、多摩川と玉川上水に挟まれた東西十一里という細長い三角形の地帯、すなわち多摩郡と呼ばれた地域の一部、もう少し詳しくいえば、明治になってから北多摩と呼ばれるようになった郡域の南半分あたりではなかったか。
当時、内藤新宿から西の方を見やれば、野や畑が遠くまで広がり、それらをつらぬく玉川上水の流れが望まれたことだろう。陽が傾けば、追分で分かれた甲州街道がきらきらと照り返し、やがて暮夜ともなれば、好き放題に飛び跳ねていた狐も狸も闇に紛れ、蛙の声や虫の音が上がり始めて、静けさをなおさら印象深くしたことだろう。
このとき、もしも、夜空へ浮かび上がることができたなら、こんな光景を眺められたかもしれない――。
闇に、炎が映えている。
どこからか、
〝おおん、おおん〟
という、警蹕(けいひつ)にも似た声音が漏れ聞こえてくる。
大声で喚くのではなく、押し殺した声韻で、まるで地の底から這い上ってくるように響いている。さらには、それに和するように法螺貝も奏でられ、やがて、それらの声韻に混じって、龍笛(りゅうてき)が奏でられ、小鼓が叩かれ、大太鼓が轟き始めた。
ざわめきは、いっさいない。
焚かれていた火が少しずつ勢いを増し、天を焦がすほどに猛り始めるだけだ。
火焚きの炎は、
「ひい、ふう、みい……」
少なくとも七つ、数えられる。
そして、ふと、見ようによってはとある星の並び方によく似ていることに気付くかもしれない。春夏秋冬、いかなる季節にあっても北天に輝くその星座は、当時も現在もこう呼ばれている。
北斗七星、と。
大地に映える火の七つ星は、視点にもよるのだが、やや離れた場所からも眺めることができただろう。なぜなら、そこは激しく傾いた崖線(がいせん)と、緩やかな段丘と、懐の深い沖積地(ちゅうせきち)になっていて、手前にはとうとうと流れる河川があった。つまり、対岸に立てば、なにひとつ遮られるものとてない彼方の地に、なんとなく北斗七星を思わせる大松明(おおたいまつ)の群れを遠望することができたかもしれない。
そのような七つの火の焚かれている大地こそ、こんにちでいう武蔵野段丘、国分寺崖線、立川段丘、府中崖線、青柳段丘、沖積低地などの河川段丘であり、それを穿ちつつ流れてゆくのが多摩川である。南へ向かって緩やかに傾斜している水はけのよい崖の地に、夜、暗闇に融け込んでゆくように、火があかあかと焚かれているのである。
(次回へ続く)