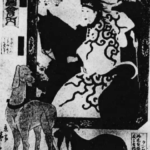舞妓見習いの少女たちに性的なちょっかいをかけ…… 「伝説の芸者」が見た花街の現実
炎上とスキャンダルの歴史
■少女に性を求めた花街
「花街」という言葉が書物に初登場するのは、天明4年(1784年)に大坂で刊行された『浪花花街今々八卦(なにわはなまちいまいまはっけ)』の中だったといわれています。
当時、「花街」と「色街」はあまり厳密には区別されておらず、「芸を売るのが芸者」「色を売るのが遊女」といった職業上の境目も曖昧でした。しかし、かわいい娘を金のために売らざるをえない貧しい親としては、遊女より、芸者にするほうが良心の呵責がなかったようですね。
明治時代になっても、遊郭で働く遊女に自由などほとんどなく、客にいいように使われるうちに短命に終わる者がほとんどでした。世間的にも日陰者の扱いです。
しかし、芸者はお座敷に出るのがお仕事。各界のセレブリティたちとお近づきになる機会も多く、いい「旦那」――パトロンができれば、女性実業家として料亭などを経営、日向を堂々と歩ける存在になれるといわれましたが、現実はそれほど甘くはありません。
明治42年(1909年)4月、顔は良いけど身持ちが悪く、借金まみれの父親から「舞妓になってくれ」と頼み込まれた高岡たつは、13歳の幼さで大阪・宗右衛門町のお茶屋・辻井楼に連れて行かれたのでした。辻井楼の女将も元・芸者です。東京に出てからは五代目・尾上菊五郎の妾だったそうですが、菊五郎が亡くなったので大阪に戻り、もらった大金で辻井楼を開いたとのこと。夜の世界の成功者でした。
高岡たつが後年出家、高岡智照尼の名義で書いた自伝『花喰鳥』によると、辻井楼は「お茶屋」だったとあるものの、芸者たちが暮らし、所属事務所でもある「置屋」――大阪の言葉でいう「家形(やかた)」も兼ねていたようです。
「たつ」はいわゆる「目力」が強い美少女で、外見審査には通過したものの、幼い頃から習っていたはずの舞も下手で、名門・辻井楼所属の舞妓になることはできなかったようですね。
プライドが高い「たつ」は「占いの結果が理由だった」と、自伝『花喰鳥』で誤魔化していますが、適当な理由をつけ、芸事・作法よりも顔面重視の加賀屋という別の置屋に送られました。そして加賀屋の女将を養母とし、売れっ子芸者・八千代の妹分となったのですが、八千代は問題が多い女でした。
岡惚れしている自分の旦那が商売に失敗し、まともに援助してもらえない八千代はイライラしっぱなし。日々の不満を「たつ」にぶつけ、きつく当たるのです。
実際、色ではなく芸を売るという「タテマエ」の舞妓・芸者として生きていくには、「たつ」の芸事・作法にも問題ありとのことで、「たつ」は「富田屋」という別の置屋に送られ、舞や鼓、太鼓などの稽古を8ヶ月にわたって積み、そこからようやく舞妓修行が開始されたのでした。
ほかの生徒たちは11、2歳でしたから、1年ほど年長ですが、多少のハンデはあったはず。花街は、「若さ」に何よりも高い価値をつける世界だったからです。
現在ならば確実に違法ですが、初潮を迎える前後の少女にこそ「価値」を見出す客が大金をはたいてやってくる――それが当時の花街の現実でした。
花街で舞妓としてデビューするまでには何回か、座敷の「見習」を務める必要があり、現在なら小学校中学年~高学年ほどの年齢の少女たちが、大人の男たちが酔いつぶれ、ときに暴れる宴会で「置物のように襖の際に座らせられている」のでした。
しかしまだ暴れる客はマシで、つらいのはアルハラ客・セクハラ客でした。ジャンケンを挑んできて、負けると酒を強要され、「よう飲まんでは済まさん、眼をつぶって舌を出すのや」といわれると、その舌に垂らされるのは酒どころか、おじさんの唾液……。
「いきなりお客さんが顔を突き出して(「たつ」の同僚の)玉寿はんの舌をペロリとなめるのです」。さらに「わしとキッスしたのだから、今夜、わしと一緒に寝るのだ」。
ここでようやく料亭の仲居さんが登場し、注意してくれたので難を逃れるのでした。つまり舞妓見習いの少女たちへの性的なちょっかいは、キスくらいなら許されるし、許さざるをえない時代だったということですが、言葉を失ってしまいます。のちには「伝説の芸者」となった高岡たつ――しかし、彼女の試練はまだまだ続きます。

イメージ/イラストAC