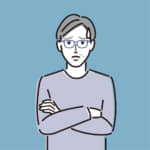朝ドラ『ばけばけ』なぜヒロイン・トキの家は没落したのか? 明治維新に翻弄された武士たちの嘆き
NHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』がスタートした。主人公・松野トキ(演:髙石あかり)の家は松江藩の上級武士という家柄だったが、明治維新ですっかり没落。家族総出で丑の刻参りをするほどだった。父・松野司之介(演:岡部たかし)は仕事もせず、武士の世と新時代の狭間で立ち尽くしており、トキはそんな父を「怠け者」と罵られたことに腹を立てた。この時代、急激な時代の変化に取り残される武士は、決して少なくはなかった。
■松江藩士の名家に生まれるも、明治維新で武士の世が終わる
朝ドラ『ばけばけ』のヒロイン・トキのモデルとなったのは、後に小泉八雲の妻となるセツさんだ。彼女の幼少期は、武士の世の終わりから明治の新しい日本への激動の時代に翻弄される。
慶応4年(1868)2月、セツさんは出雲松江藩の家臣だった小泉家に誕生。6人きょうだいの次女だった。親戚にあたる稲垣家には子がなく、既に小泉家から養子に出すことは決まっていたという。そして、セツさんは生後わずか7日で稲垣家の養女となった。
ちょうどこの1ヶ月前、前年末の王政復古の大号令を経て、戊辰戦争が勃発。鳥羽・伏見の戦いが開戦していた。ここから旧幕府軍と新政府軍の熾烈な争いが始まる。さらに、セツさんが誕生した2月は、神戸で備前藩の兵がフランス人水兵らを負傷させたことに端を発する「神戸事件(備前事件)」が起きている。これは明治政府初の外交問題ともいわれている大事件だ。
そんな時代の転換期に生まれたセツさんは、物語好きの少女に育つ。周囲の大人たちから昔話や伝承、伝説などあらゆる物語を聞いていたそうだ。しかし、家族を巡る状況は決して恵まれてはいなかった。明治維新によって、士族の特権は徐々に失われていくからである。
明治2年(1869)には戊辰戦争が終結し、版籍奉還が行われた。明治4年(1871)には廃藩置県があり、それまでの藩は府県となって政府の統治下におかれることになる。中央集権体制の確立を狙ったのである。これによって、それまで「知藩事」を務めていた旧藩主たちはその職を失うことになり、代わって各府県には政府から県令が派遣されることになった。その後も府県の統合・整理は急速に進められ、かつての「藩主とそれに仕える藩士」という構造は失われたのである。武士の世が終わり、職を失った者たちは新たな価値観、社会構造のなかで生き方を変えなければならなくなった。
さて、ドラマではトキが学校に通っていた。子どもの教育はどうなったかというと、明治5年(1872)に公布された学制によって、大学・中学校・小学校の三段階を基本にした新しい教育制度が構築され始めていた。誰もが小学校で基礎教育を受けられることも目標としており、各地に学校もつくられた時期だ。セツさんは8歳の時に小学校に通い出し、勉学に励んで優秀な成績を修めていたという。
武士の世と新たな世の狭間で立ち止まる父と、そんな父を案じながら子どもながらに明治という世の変化を感じているトキ。それぞれの目でみる変革期を本作は描いていく。

島根を代表する名所・宍道湖はしじみで有名だが、夕景が美しいことでも知られる。