プロ野球のスカウトとスナックやバーで会合!? だが、学生野球の本質は「教育」にあることを忘れてはならない
あなたの知らない野球の歴史
■ドラフトを見守る関係者の気持ち
西武ライオンズなどで、スカウト活動が問題視されるようになった頃である。つまり20年ほど前までの話になるが、一部の球団スカウトは、様々な活動をしていた。各地の大学のリーグ戦に足を運び、目を付けた選手がいると試合後に監督のもとに挨拶に訪れる。ここまではよくあることで大きな問題ではない。むしろここから問題が起きる。
その後、スカウトは大学グランドまで足繁く通い、監督と懇談し、夜になると飲食に誘うケースが多々あった。一次会は大衆的な小料理屋での顔合わせ、その後、二次会になるとスナックやバーになることもある。さらに、スカウト自らが飲食代の折半を断り、支払いを済ませてしまうことも多い。このようにスカウトと監督の接点は急速に増えていくことになる。
スカウトには、場を盛りあげるエンターテイナーのような人材もいる一方、取り立てて話題を持ち出さず監督の話を笑って聞いているスカウトなど、いろいろなタイプが存在する。だが、営業担当のようなスカウトは万事そつがない。その流れは実に巧妙で、数度の飲食会を経て、結局スカウトと監督の二人の話し合いの場になる。
ドラフトは野球界の独特なシステムだが、交渉プロセスが不透明で、球団スカウトと選手や監督の間にどのようなやり取りがなされているのか、外からは見えにくい部分がある。
かつては目を付けた選手に他の球団を近づけないようにする「囲い込み」が問題となったことがある。学外での試合終了後の時間、複数のスカウトが該当する選手に寄り添うように囲うのである。他の球団が特定の選手に接触できないように諦めさせる必要があるからだ。
また、担当スカウトから選手や監督にドラフト会議で2位や3位で指名したいといった話や契約金の話がドラフト前にあったとしても、会議当日、有望選手は他球団との争奪戦になり、他球団が強引に指名を強行したりするなど(江川卓を阪神が指名したように)、当然、予定通りの指名順位とはならない場合もある。そんな時は、スカウトから選手や監督に陳謝することもある。
テレビでドラフト会議が中継され、実際に指名されるとホッとするというのが、関係者の偽らざる気持ちだ。下位指名ともなると選手は不安な気持ちで待機するという具合である。
■学生野球の本質とは
すべての選手が希望通りにプロへ進めるとは限らない。そもそも大学まで野球を続ける選手は少なく、ほとんどの選手は高校で野球から引退するか社会人野球に移ることになる。また大学まで進学する選手の中には高校受験から推薦で入学する者もおり、一般学生と同じように勉学をしているのか、大学入学後、授業で学び、単位を取ることは可能なのか、そこは問題も多い。かつては、入学したものの、単位を満たすことができず、いわゆる野球部の入学者名簿の写真は残っているが、卒業名簿の写真残っていないいうことがよくあった。果たしてこれが大学野球部のあり方かと問う人も存在する。
もちろん、勉学を疎かにしない選手もいる。ただ、私学高校では甲子園に出場することで学校のPRになるため、少子化が叫ばれる中、成績の下駄を履かせていたことは容易に想像できる。大学もまたしかりである。かつては都心周辺の大学野球部が大学選手権や明治神宮大会では優勝の常連だった。しかし、この20年ほどの成績を見ても地方私立大学の台頭が顕著になっているのは、高校と同様な状況が存在するともいえる。学部もありふれた学部ではなく、スポーツ関係や看護など特定の学部が増えている。彼らも含めて野球部の大学生たちは本当に無事に卒業したのか、疑問が生じるには当然だ。
アメリカの名門スタンフォード大学に入学した佐々木麟太郎は野球だけでなく勉学に追われていることが紹介されている。アメリカの伝統校では学業とスポーツと両立させるのは当然の方針である。
しかし勉学だけではない。学生野球の現場では、たびたび暴力問題などが表面化して大騒ぎになることがある。監督自身の性格もあるが、言葉より暴力が優先する状況で、そういうシステムが常態化してしまうと、その教え子が後任として監督に就任した場合、はやり何かの怒りで手を出してしまうことは多々あるようだ。さらに在任時間が長い監督の場合、暴力問題だけではなく複合的な様々な問題が生まれることもあるだろう。政治の世界でもそうだが、長期間の権力の座を占めていると独裁となり、独裁は腐敗することもあるのだ。
一方、学生野球は教育の一環である。たとえスポーツ推薦で大学に入学したとしても、野球に優れていればそれでよいのか。講義に出席せず、寮とグランドを往復するだけで終わっていないか。週に1回か2回、大学に通えば卒業単位は取れるのか。少子化がまずます進行するなか、大学当局のスポーツ推薦のあり方や、野球部を統括する大学体育会本部も大学の本分としてのシステムのチェック機能、学生スポーツのあり方や勉学との両立への模索に対して最高学府の片鱗を多少は見せてほしいものだ。
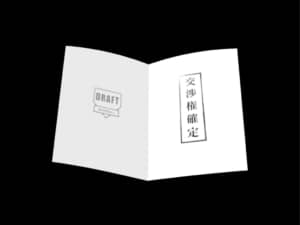
イメージ/AC






