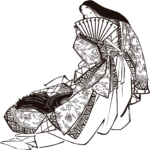死の影がつきまとった「悲劇の美女」 歴史に翻弄され続けた信長の妹・お市の方の悲運とは?
日本史あやしい話
織田信長の妹でありながらも、政略結婚によって浅井長政や柴田勝家に嫁がされたお市の方。その夫は2人とも自害に追い込まれたばかりか、兄・信長や長政の息子(万福丸)まで殺されるなど、彼女の周囲は、死の影が付いて回るのであった。挙句、最後には、自身も夫・勝家の手にかかって死去。これ以上ない不運な人生を歩んでしまったのである。
■夫も兄も殺され続けた不運な人生
いかに戦国の世とはいえ、これほどまで歴史に翻弄され続けた女性は、他にいないのではないだろうか。その名は、お市(お市の方)。織田信長の妹(従妹との説も)である。
最初は、浅井氏と同盟を結ぶための政略として浅井長政と結婚させられたが、3人の娘(茶々、初、江)にも恵まれ、それなりに幸せを掴んでいたようである。しかし、運命の歯車は、このあたりから狂い始める。信長が浅井家と関係の深い朝倉義景を攻撃したことで、織田家と浅井家が対立してしまったからである。結局、姉川において、両氏が対戦することになってしまったのだ。いうまでもなく、お市にとっては、兄(信長)と夫(長政)の戦い。彼女の心中や、察するに余りありそうだ。
結果は、夫の長政側が敗走。さらに1573年、拠点とする小谷城が陥落して、とうとう長政が、父・久政とともに自害してしまうのであった。その際、お市は三人の娘とともに救出されて織田家に引き取られているが、夫を殺した兄に恨みを抱いたことは言うまでもないだろう。
悲運は、そればかりではなかった。1573年、長政の長男である万福丸(生母は不明なるも、茶々らにとっては異母兄にあたる)の生存を知った信長が、羽柴秀吉に「串刺しにして晒せ」と命じたというからおぞましい。10歳にも満たない少年を磔にしてしまう兄・信長の残虐さに、背筋が凍ったに違いない。
その無慈悲な兄・信長も、1582年、本能寺の変において明智光秀に襲われて自害。いかに兄を恨もうとも、肉親の死には、悲しまずにはいられなかったはずである。
その後も、まだ彼女にとって不運が続く。織田家の継承問題についての話し合いの場となった清洲会議において、25歳も年上の初老の織田家家臣・柴田勝家(この時、60歳前後か)との再婚が、秀吉をはじめとする諸将に承諾されてしまったからである。勝家の不満を解消するための政略だったとはいえ、ここでもまた、お市の方の思いなど、あって無きが如し。それが戦国の世に生きる女たちにとっての運命であったとはいえ、葛藤の末に、渋々受け入れざるを得なかったことは想像に難くない。
その半年後のことである。秀吉がついに勝家攻略に動いたことで、夫・勝家が苦境に立たされてしまった。結局、賤ヶ岳の戦いに敗れた勝家が、越前北ノ庄城に逃げ戻るも、秀吉が追走して城を包囲。激しく攻め立てられたからたまらない。とうとう、80名もの臣下たちとともに、自害して果ててしまったのだ。
■夫・勝家とともに果てた、凄まじい死の情景
勝家が自害するにあたって、妻となってまだ日の浅いお市に、勝家は逃げるよう諭したと伝えられている。それが戦国の世の習わしである上、お市は、秀吉にとって、主家にあたる織田家の出自である。秀吉にしてみても、彼女が3人の娘とともに城から出てきて当然との思いがあったに違いない。それにもかかわらず、お市は退去を拒否。夫とともに果てることを選んだのだ。ただし、3人の娘だけは、身柄の保障を依頼する書状とともに、秀吉の元へ送り出した。こればかりは、幸いであった。
落城前夜のことである。死を覚悟した勝家は、臣下たちと夜を徹して酒宴を催したという。彼らと今生の別れをした後、勝家はお市に手をかけた。夫に刀を突きつけられたその時のお市の心情は計り知れないが、それは自ら望んだこと。夫に対して恨みなどあるわけもなかった。秀吉に我が身を委ねてなるものかとの思いもあったのだろうが、むしろ、夫とともに死ねることに安堵。清々しい心持ちであったと信じたい。
その後、勝家自身が腹を斬ることになるが、その情景は筆舌に尽くしがたいものであった。まず、左の脇腹に刀を突き立てるや、一気に右脇まで一直線に引き裂いた。さらに返す刀で胸からヘソまで縦に割いたというから恐れ入る。そればかりか、五臓六腑を掴み取って掻き出したというから驚くほかないのだ。それだけではない。その介錯にあたった中村聞荷斎に火薬を仕掛けるよう命じて、勝頼の遺骸もろとも吹き飛ばさせたというから、開いた口が塞がらないのだ。
最後に、お市の娘たちのその後の動向についても、目を向けておくことにしよう。
まずは長女・茶々が、父と兄の仇であったはずの秀吉の側室となっている。その時の彼女の思いがどのようなものであったのかはわからないが、その後豊臣家を支え続け、大坂夏の陣において、息子・秀頼とともに自害したことは特筆すべきだろう。
また、次女・初は、長政の姉の子・京極高次の正室に、三女・江は、徳川秀忠の継室となり、秀頼の妻となった千姫や、徳川三代将軍・家光、後水尾天皇の皇后となった徳川和子を生むなど、歴史に名を刻む錚々たる面々へと系譜を繋げていった。彼女の血は、脈々と今日まで受け継がれているのである。

お市の方の像/撮影:藤井勝彦