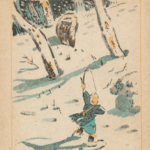ヒグマの子に自身をなめさせ、母乳を与えて育てる 史料に記された驚くべき「子熊の飼い方」とは
歴史に学ぶ熊害・獣害
今回ご紹介するのは、明治44年に発行された『熊』という書物に記された「子熊の飼養」である。著者は動物学者の八田三郎(1865-1935)だ。発行当時、同氏は東北帝国大学農科大学の教授を務めていた。
本書のなかではアイヌ民族とヒグマの関係性等についても言及されている。そのなかに「狩り獲た熊の頭の処分と熊の子の飼養」という項目がある。
それによると、春先に「穴狩」や「追狩」で熊狩りを行うと、子熊が1~3匹捕らえられることが多い。母熊が狩られてしまうので、こうした子熊は「みなしご」になってしまう。著者は「こんな孤熊(みなしごぐま)はほとんどすべて飼育(かいそだ)てられる」としている。
ここからはアイヌの人々がどのように子熊を飼育していたのかが詳説される。野山で母熊を狩り、子熊を発見した時、もし砂糖や蜜が手元にあったらすぐにそれを与える。それから集落に連れ帰り、村の女性らは子熊に自分の足の裏や腋など体じゅうをなめさせて、自分の匂いを覚えさせるそうだ。すると、早ければ半日~1日でよく慣れるのだという。
女性らに慣れると、しばらくは室内でまるで猫を飼うかのように一緒に暮らす。母乳が出る女性は、子熊に自分の乳を吸わせる。それ以外にも、エサとして穀類や豆類で作った粥や、煮た魚、植物の根茎とふきを細かく刻んで半日~1日煮たものなどを与える。かなり手間をかけて食事を用意するようだ。
子熊が成長してくると、檻の中で飼育するようになり、エサも牛や豚などの骨を買ってきて与えるようになるという。子熊はガリガリとまるで煎餅でも食べるかのように骨を味わうのだそうだ。著者はその様子を「未来の横綱だ」と例えている。
3歳にもなるともう人間が制御できない「猛獣」と化すため、2~3歳で殺さなければならない。その際行われるのが「熊送(熊祭)」という祭りだ。儀式の形式は集落で違いがあるようだが、酒がふるまわれ、子熊は解体されてこれもまたふるまわれる。著者は2歳の子熊の肉を食した時の感想として「なかなか美味で、親友にはぜひ勧めたいくらいだ」と絶賛している。
著者はこの熊送にも参加したことがある。アイヌの人々にとって神聖なこの儀式について考察し、「時々威儀を張って熊の魂魄というものを送る式をするのがこの熊送だろう」としている。そして、「そこまでして恐れるのなら熊狩をやめたらよかろうという意見もあるかもしれないが、狩りは北方に暮らす人類の緊要な生計法で、アイヌが狩りをやめるのは南方の住民が農業をやめるのと同じことなのだ」とし、「だから狩りを盛んにするのと同時に、祭典も盛んに執り行って生きていくほかない」と、その伝統と熊への敬意、共存の在り方を記している。

ブルックリン美術館蔵
<参考>
■八田三郎『熊』