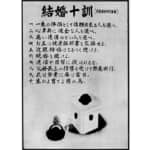朝ドラ『あんぱん』豪ちゃんはどこで戦死したのか? 激化する満洲国とソ連の国境紛争に動員された兵たち
朝ドラ『あんぱん』外伝no.26
NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』、第8週は「めぐりあい わかれゆく」が放送中だ。朝田のぶ(演:今田美桜)は “愛国の鑑”として、日々生徒らに軍国教育を行っている。しかし、朝田家には出征していた原豪(演:細田佳央太)の戦史の報せが……。戻って来たら夫婦になると約束して帰りを待ちわびていた蘭子(演:河合優実)は、「豪ちゃんに会いたい」と慟哭する。さて、豪は架空のキャラクターではあるが、当時高知連隊区から出征していった兵らの動向と、当時の戦況を取り上げる。
■第11師団は満州国に派遣され、ソ連軍との国境紛争の最前線へ……
大日本帝国陸軍においては、全国の地域を師管や連隊区といったように区分けし、基本的にはそれぞれの本籍地に基づいて徴兵するシステムをとっていた。
時期によって制度そのものも管轄にも変動があるが、昭和12年(1937)時点で、高知は第11師管に含まれている。第11師管には、昭和19年(1940)7月末までは、丸亀連隊区、徳島連隊区、松山連隊区、高知連隊区が属している。高知連隊区は大正9年(1920)に徳島連隊区から安芸郡を編入し、以降は高知市はもちろん、県全域を管轄していた。
転属などの事情もあるものの、本稿ではひとまずこの第11師管を徴兵区とする第11師団に焦点を当てて、盧溝橋事件以降の足どりを追っていきたい。
盧溝橋事件以降、全面戦争に発展した契機といえるのが昭和12年(1937)8月13日から始まった「第二次上海事変」だ。同日、日中両軍は戦闘を開始。大日本帝国政府は、緊急閣議によってこれまでの「不拡大政策」を捨てることを決断し、第3師団と第11師団に動員命令を下した。上海事変自体は最終的に日本軍の勝利に終わったものの、同年9月末までに第11師団は戦死者約1,500人、戦傷者約4,000人という大打撃を受けたという。
『日本防衛史と第十一師団の歴史』(第十一師団歴史刊行会)によると、その後師団主力は昭和13年(1938)3月に上海から坂出港(香川県)に戻った。そして同年9月に満州派遣のため改めて編成され、師団司令部は10月6日に坂出港を出て釜山経由で満州に入り、関東軍司令官の隷下に入った。最初は南満州に駐屯して、教育訓練を行ったらしい。
そして同年12月、ソ連と満州国の国境にほど近い北東の密山付近へ移動し、その地区の治安維持や国境防衛の任務を負うようになった。翌昭和14年(1939)6月、第11師団は関東軍の第1方面軍に属する第5軍司令官の隷下に入り、密山、虎林、饒河の三県を防衛区域とするようになる。
東進を推し進めるソ連と、満州が国防の要でもある日本の国境紛争は増え続け、規模も徐々に大きいものになっていた。『戦史叢書 関東軍<1> 対ソ戦備・ノモンハン事件』(防衛庁防衛研究所)によると、満洲東部における紛争だけで昭和12年(1937)には82回、昭和13年(1938)には110回、昭和14年(1939)には96回の紛争が起きている。つまり第11師団をはじめこの地域に派遣された兵たちは、対ソ連の最前線に立たされていたのである。
昭和14年(1939)5月、満州国とモンゴル人民共和国の国境紛争が勃発。これが、第一次と第二次に分かれて同年9月まで続くノモンハン事件だ。モンゴルの背後にはソ連がおり、実質的には大日本帝国陸軍とソ連軍の争いだった。日本側はこの大規模戦闘で大きな被害を受け、7月に満州国各地からの応急派兵の命を下すことになった。第11師団からも、所属する各歩兵連隊から臨時で派兵している。応急派兵の命令が解除されたのは、停戦協定が成立してから10日後の9月25日のことだった。
ここまで見てきておわかりいただけるように、第11師団が主に想定していた敵は中国ではなく、国境を越えて侵入しようとするソ連軍である。当時の日本は、中国との戦争を継続しながらも、満ソ・満蒙の国境紛争にも兵を動員し、満州国の防衛のために尽くさなければならない状況だったのである。
※画像はノモンハン事件の際の日本軍を撮影したもの(部隊不明)

ノモンハン事件時の日本兵/『同盟通信社写真ニュース 』より
<参考>
■第十一師団歴史刊行会『日本防衛史と第十一師団の歴史』(1969)
■大野広一『第十一師団歴史の概要』(1961)