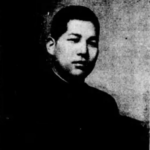朝ドラ『あんぱん』のぶを高等女学校へ進学させた理由は? 三姉妹を通じて見る当時の女子教育の実態
朝ドラ『あんぱん』外伝no.9
NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』、第3週は「なんのために生まれて」が放送中だ。朝田のぶ(演:今田美桜)は、父・結太郎(演:加瀬亮)の遺言である「女子も大志を抱きや」について、自分の夢を見つけられずにいたが、パン食い競争や近所の子へのラジオ体操指南を経て「学校の先生になる」という夢を見つける。今回は現代とは大きく異なる、当時の女子教育を朝田三姉妹の状況と照らし合わせて紹介したい。
■女子教育の基本は「良妻賢母育成」だった
明治40年に小学校令が改定された際には、尋常小学校が6年制の義務教育機関となった。これに伴って、高等小学校は2年制に定められる(旧高等小学校の3、4年が新高等小学校の1、2年に相当)。なお、尋常小学校は原則無償、高等小学校は授業料を納めなければならなかった。
尋常小学校では修身(現在の道徳に近い科目)や国語、算術、唱歌、体操などを中心に学び、学年があがると図画、理科など科目が広がった。また、女子は裁縫も習っていたという。高等小学校は現在の中学1~2年生にあたる。科目として手工や実業が加わり、女子に対しては「家事」が加えられる。
昭和10年(1935)春の時点で、朝田家の三女・メイコ(演:原菜乃華)は高等小学校1年生で12~13歳だ。メイコの2つ年上の次女・蘭子(演:河合優実)は郵便局勤めを始めているということで、もしこの春から勤め始めたのであれば高等小学校には進学したが、そこからさらに進学するのではなく就職する道を選んだことになる。それ以前から勤めていたということであれば、尋常小学校卒業後にそのまま就職したのだろう。
「高等」と名はついても、メイコが通う高等小学校はあくまで「初等教育」だ。中等教育機関としては、旧制中学校やのぶが在籍する高等女学校が存在した。高等小学校はこうした中等教育機関への受験に失敗した生徒らにとって、現代でいうところの「予備校」的な側面も持っていた。
のぶが尋常小学校卒業後に進学した高等女学校は、大正9年(1920)の高等女学校令改定によって5年制が基本になった。とはいえ、現在の中学・高校のようなイメージとは大きく異なる。端的に言えば「良妻賢母になるために女子が備えておくべきスキル」を身に着けるための場なのだ。実際、高等女学校令が出された明治32年(1899)には、時の文部大臣が「高等女学校ノ教育ハ其生徒ヲシテ他日中人以上ノ家二嫁シ、賢母良妻タラシムルノ素養ヲ為ス二在リ」と発言している。
もちろん国語や数学などの一般科目もあったが、家事や裁縫などの所謂“花嫁修業”に近い科目も多かった。また、その地域ごとに求められる“良妻賢母”を育成するため、とくに田舎では農作業なども扱ったという。成績については各科目の習熟度だけでなく、「周囲との協調性」つまり優しさや控えめな態度であるかなども重視されていたらしい。卒業後は多くが結婚して家庭に入った。
具体的な将来のビジョンが描けていなかったのぶを高等女学校に進学させたのは、長女であるのぶが幼少期から近所で有名な「ハチキン」であったために、良い縁談がまとまるような良妻賢母教育を受けさせる意図が(少なくとも祖父母には)あったのかもしれない。祖父・釜次(演:吉田鋼太郎)が、結婚ではなく進学を願うのぶに対して怒りを露わにする場面で、「じゃあどうして高等女学校まで進学させたのか?」と思った方も少なくないと思うが、そこには現代と女子教育の性質が全く違っていたという事情があるのだ。
のぶは学校の教師になるという夢を見つけ、女子高等師範学校への進学を志す。しかし、内閣府男女共同参画局によると、戦前における高等女学校から女子高等師範学校などの高等教育機関への進学率は、1%未満だったという。のぶの決意に祖父母が反対したのは、当時としては普通の感覚なのだ。果たして、一握りの女子のみが進む道を歩こうとするのぶは、今後どうなるのだろうか。

イメージ/イラストAC
<参考>
内閣府『男女共同参画白書 令和元年版』より「高等女学校における良妻賢母教育」