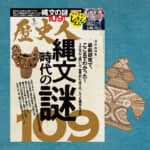縄文人は暇だったらしい⁉ 縄文人は「どんな1日」を過ごしていたの?─何時に起きて寝るの?─
縄文時代の謎109 #02

世界文化遺産 三内丸山遺跡
■定住のため知恵と技術を身につけた縄文人
縄文人は暇だったらしい。
道具としては不便になってしまう過剰な装飾を与えられた縄文土器(火焔土器をみよ)も、余裕があったからこそ作られた代物だ。飢餓状態で年がら年中獲物を追いかけ、植物採集をしていたら、あれほどの技巧を凝らした土器は作れない。
縄文時代の人口は東に偏っていたが、ほぼ、サケの遡上してくる地域に住んでいたことは、無視できない(遡上する最西端は、鳥取県説、兵庫県豊岡市説がある)。放っておいても勝手に秋になるとタンパク源が川を遡上してくるのだ。こんな楽なことはない。
縄文時代の日本列島は、現代以上に暖かい気候で(だから海水面が高かった)、食料となる動植物が豊富だったのだ。アフリカを出立した新人たちの中で、おそらく一番弱かった者が追いやられて日本列島にたどり着いたと筆者は推理しているのだが、「残り物の土地」が、意外にも楽園だったのだ。
そんな縄文人たちは、一日何をしていたのだろう。
旧石器時代の人々は狩りに明け暮れ、拠点をいくつか作り移動していた。ところが縄文人たちは定住するようになった。この差は意外に大きい。日々の暮らしは、大きく様変わりしたのだ。重い土器を作り、気に入った土地に居座り、保存食を作り、貯蔵した。移動しなくても生活できる知恵と技術を身につけたのだ。
とはいえ、縄文人全体が同じ暮らしをしていたわけではなく、地域差があったことも忘れてはならない。地域ごとの生活スタイルがあった。
たとえば、取れる食材が、海浜部と内陸部や高地では、まったく異なっていた。当然、地域ごとに食事のメニューは違っていたはずだ。
気候の差も、日常生活に違いを作った。たとえば日本海側を中心に、縄文時代の巨大建造物がいくつも見つかっているが、雪で覆われる季節になると巨大建造物に人びとは集まり、こまごまとした作業をしていたのではないかと推測されている。縄文土器を代表する精巧な技巧を施した「火焔土器」が日本海側で発達した理由も、長い冬と豪雪地帯という要素が大いにからんでいたわけだ。
日本海側の縄文人は冬の間暇だったのだ。そして、その活動できない時期を支えるだけの豊富な食料を、他の時期に確保して保存することが可能だった。
■定住生活とともに初歩的な農耕が始まる
一方、海岸地帯に住む人たちは、干し貝や塩を作り、内陸部の黒曜石などと交換するために、商人のような活動に励むようになった。川をさかのぼり、峠を越え、またある時は、大海原を渡った。すでに旧石器時代から、列島人は果敢に海に飛び出し、伊豆諸島との間を往き来していたことが分かっている。
また、定住を始めた縄文人は、簡単で初歩的な農耕も手がけていたことが分かっている。三内丸山遺跡からみつかったクリの遺伝子は似通っていて、野生のものではない。ヒョウタン・エゴマ・マメ類などが栽培されていた。ただし、「穀物栽培」に関しては、近年の研究で否定されつつある。
それはともかく、稲作が北部九州に伝わったのは紀元前10世紀後半と考えられているが、これが縄文時代なのか弥生時代なのか、一時議論になった。縄文時代、すでに稲作が始まっていたと大騒ぎになったが、縄文時代と弥生時代の時代区分ははっきりせず、稲作を始めた場所から弥生時代へと移っていったという結論になりつつある。何しろ、関東の人々が本格的な稲作を受け入れるのは、数百年もあとになるわけで、日本列島が一気に稲作を選択したわけではなかったし、弥生土器も、伝播のスピードは速かったが、揺り戻しが起きていて、弥生時代なのに縄文的な装飾が施されることが何度も起きた。
ところで、縄文人と言えば土偶をすぐに思い浮かべるが、土偶は女性で、出産や豊穣にまつわる祭祀を行っていたようだ。日常生活の中に、祈りの時間が含まれていたのかもしれない。
監修・文/関 裕二