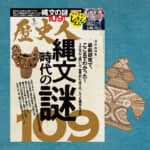長年議論されていた「縄文時代の幕開け」はいつなのか問題に迫る⁉ ─科学の発展でついに判明?─
縄文時代の謎109 #01

遮光器土偶
日本で最も有名な土偶の一つ、教科書でもおなじみの遮光器土偶。出典:Colbase、東京国立博物館蔵
■出土物の年代を調べるため炭素と樹木の年輪を利用
縄文時代の年代を測定するには、炭素14(14C)を用いることが一般的である。大気中における14Cは、太陽からの宇宙線によって生成され、β線という放射線を出して、窒素へと変化していき、大体5730年で元の量の半分になることがわかっている。14Cは大気中に含まれていることから、動植物が呼吸や光合成をすると、その動植物中における14Cの濃度は、大気中のそれと同じになる。しかし、動植物が死ぬと14Cの供給は絶たれるので、その時点から14Cの量は減少していくことになる。したがって、出土した炭化物や炭素を含む遺物に含まれる14Cの量を測定することで、今から何年前のものか知ることができるのである。これが14C年代測定法の原理である。
しかしながら、大気中における14Cの濃度は必ずしも一定ではなく、主に地磁気の変動によって、宇宙線が生成する14Cの量が異なることがわかっている。そこで過去における14Cの濃度の変動を調べ、炭素による測定年代(炭素年代)を補正してやる必要がある。これを較正(calibration)と言う。
炭素年代の較正には、樹木の年輪を利用する。伐採年がわかっている木材や建築材を利用し、その各年輪の中に含まれる14Cの量を測定することを繰り返して、14Cの測定値と実際の暦れ きねん年がどれくらいずれているのかを調べるのである。
■各地の最古級土器を調査使用年代が早まることが判明
また、これまで14Cによる年代測定には、炭素が崩壊するときに出る電子を数えるβ線法を用いていた。この方法は時間がかかる上に、測定に必要な炭素も、場合によっては数十グラムも必要であったため、貴重な考古学的資料に適用することができなかった。しかしながら、1977年に加速器質量分析(AMS;Accelerator Mass Spectrometry)法が開発されたことにより、測定に必要な試料が約千分の一以下の1㎎程度で済むことになった。これにより、また、測定時間が30分から1時間程度しかかからないことから、貴重な考古学的資料についても年代測定を行うことが可能となり、現在では多くの資料に具体的な年代が与えられている。
これまで高校の歴史教科書などでは、縄文時代の始まりを今から1万3000年ほど前であったと記述されることが多かった。しかしながら、AMS法が採用されたことによって、各地における最古段階の土器に付着した炭化物の年代測定が進んだ結果、おおむね土器の登場は1万6000年前にさかのぼることが確実であることがわかってきた。
科学技術の発展により、縄文時代の開始年代がさらに古くなることがわかったのである。
監修・文/山田康弘