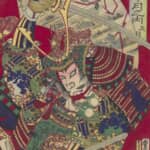信長・秀吉…天下人たちに振りまわされた戦国3大美女のひとり【お市】─悲劇に生きた女性の怒涛の人生とは⁉─
歴史を生きた女たちの日本史[第1回]
歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

お市像
お市の方は、悲劇に生きた戦国の女性である。謎にも満ち、あらゆる意味で戦国時代を代表する女性でもある。通説は多いものの、記録や資料はあまり残っていない。織田信長の妹というのが、その通説の軸になるものだが、それさえも「実は妹ではなく、従妹(いとこ)であった」のを妹と偽って、近江の武将で信長が同盟を結びたがった浅井長政に輿入れさせた、という異説がある。
妹の真偽はともかく、尾張一国を平定したばかりの信長は、敵対していた南近江の観音寺城主・六角承禎(義賢)を対しての政略として、その隣国の浅井氏を味方に引き入れるのが目的で、お市を長政に輿入れさせた。
この当時、長政は「野良田合戦」で六角勢に大勝利を挙げている。その勝利は、京都周辺では信長の「桶狭間合戦」よりも高く評価されたほどであった。そのうえ、長政は世間に鳴り響いたほどの美男子で、知勇優れた若武者として、知られるようになっていた。英俊で戦国3美女のひとりといわれたお市とは、まさに似合いの夫婦であった。一説には、木下(羽柴)秀吉も、美しいお市に恋焦がれていたともいう。
お市は、信長の父・織田信秀を父として生まれたが、生母は誰か不明である。その輿入れは、永禄6年(1563)頃であった。お市の方は、信長の野望・政略結婚の犠牲になった訳だが、しかし、長政との結婚生活は幸せそのものであった。長政との間には、男子1人、女子3人を産んだ。
長政の浅井家は、長年に渡り越前・朝倉氏(当時は朝倉義景)と懇意であり、信長とは「共同の敵・六角との争いはもちろん織田氏に味方するが、越前・朝倉氏との戦いは止めて欲しい。もしそのようなことがあるならば、事前に相談して欲しい」という交渉の末、約束が結ばれていた。しかし、勢力を大きくした信長は、この約束を破り越前に攻め入ろうとした。この時、長政は義兄・信長に味方せず、朝倉氏に付いた。そのため信長と織田勢は挟み打ちに遭い、危機一髪の状況になった。何とか「金ヶ崎の退き口」という危機を脱した信長は、長政とは敵味方になる。これが後の、姉川合戦に至る。
天正元年(1573)8月、信長の大軍が長政の居城・小谷城を攻囲した。そして9月1日、長政はお市の方と3人の娘を脱出させ、自らは自決した。ここに、浅井家は滅び、その直前に朝倉家も滅びた。生き残ったお市ら母子は、織田家で養育された。やがて、本能寺の変が起き信長が横死すると、その後を秀吉と柴田勝家が主導権争いをし、お市を勝家が娶る。またしてもお市は政略結婚の道具となったのであった。
さらに羽柴秀吉・柴田勝家2人の争いの結果、居城・北の庄城を攻撃された勝家が敗れ、お市もともに自害する。その際に、お市の3姉妹は助け出される。その3姉妹が、いずれも歴史に名を残す姉妹となる。長女は秀吉の側室となり豊臣秀頼の母となった茶々(淀君)、二女はキリシタン大名として名を馳せる京極高次の妻となるお初、徳川家康の子であり江戸幕府2代将軍となる徳川秀忠の正室となる三女・小督(お江与)である。なお、お市の辞世は「夏の夜の夢路はかなき跡の名を雲居に揚げよ山ほととぎす」である。享年37。