「男性への性加害」に鈍感な日本人 闇に消えていった、明治期のわいせつ事件とは?
炎上とスキャンダルの歴史
男色や衆道など、日本における男性同性愛文化の歴史は古い。しかし、それらの中で一般的だったのは「年長者が年少者を寵愛する」というスタイルであり、嫌がる子どもに無理やり男色の相手をさせるような悲劇も起きていた。男性同士での性加害がどのように行われ、扱われてきたのか、振り返ってみよう。
■明治政府が「男性同性愛者の性行為」を法律で禁じた理由

森鴎外像。彼も『ヰタ・セクスアリス』で男性に襲われた経験を語っている
「諸外国と比べると、古来、日本人は同性愛に対して寛容であった」とよくいわれますが、自分が好むスタイル以外の恋愛に対し、人はつねに批判的でした。どの時代においても、誰の目にも公明正大だと映る恋愛などは存在しなかった。それだけが事実といえるでしょう。
明治時代、(男性)同性愛者は「硬派」だと呼ばれた一方、彼らの関係は異性愛の人々の目には異質なものとして映っていたに違いなく、逆に同性愛の人々には、異性愛者は「軟派」として理解できないものだったはずです。
そんな中、明治6年(1873年)、明治新政府は「鶏姦罪(けいかんざい)」を制定、男性同性愛者の性行為を法律で禁止しようとしたことがありました。同性愛を禁忌とする諸外国に倣い、「近代国家」としての生まれ変わった日本も同性間の性行為を禁止しようとした……などという説明がされがちですが、実はそうではありません。
鶏姦罪は、白川県(現在の熊本県)から「県内の男子生徒たちが、男色にふけって勉強しないのでなんとかしてほしい」という問い合わせに応えるかたちで制定されたのだとか。逆にいえば、明治期の学生たちが最初に恋をする相手は、同性が多かったということかもしれません。
■両親が少年を差し出し、「男色の相手」に
古来、男性同性愛がさかんだった地域と聞くと、薩摩(現在の鹿児島県)を思い出す方も多いでしょうが、実際は日本全国、どこにでも似たような同性愛文化はありました。
かつて男性同性愛は、年長者(=念者)が、年少者(=念弟)を、心身ともに寵愛するというスタイルが一般的でした。男の子が思春期になると、年上の男性に心も身体も愛され、それが実社会との接点となるという考え方です。元・土佐藩士(土佐=現在の高知県)の馬場辰猪(ばばたつい)という人物は「少年が花の盛りとなるとき、両親が然るべき武士を見立て、保護者となることを頼むのが普通」だったと往時をふりかえっています。
しかし、年長の男性との関係をすんなり受け入れられない子供は悲惨でした。紅楼夢(こうろうむ)主人なる人物(土佐藩出身、明治期のジャーナリスト・宮武外骨/みやたけがいこつ/の筆名)の『美少年論』によれば、土佐では、男色の相手になることを嫌がる少年がいたら集団で家に押しかけ、手籠めにして「教育」したのだとか……。それが「ふつう」だった時代とは、恐ろしいというしかありません。
■闇に消えていった男性同士の性加害
森鴎外(もりおうがい)は『ヰタ・セクスアリス』(明治42年・1909年)という「性」にまつわる思い出を描いた作品の中で、彼が12歳の頃の記憶として、学校の寄宿舎で、鴎外のことを好いていた先輩の男子学生から頬ずりされたり、布団で添い寝を請われたりしたという話がでてきます。
添い寝はさすがに断りましたが、隣の部屋から様子をうかがっていた男が「応援して遣(や)る」と言ってきて、複数の男たちに手籠めにされそうになったので抵抗したところ、寄宿舎を統括する立場の「書生」たちが異変に気づき、駆けつけてくれた……というのですが、あまりにさらりと語られているので、違和感を覚えてしまうエピソードですね。
ちなみに例の「鶏姦罪」ですが、とあるフランス人の法律家から「恋愛を法律で取り締まろうとするなど時代遅れだ」と批判され、明治15年(1882年)には早くも撤廃されています。
鴎外の経験した「事件」は明治7年(1874年)ごろであろうと推測され、「鶏姦罪」が有効だった頃の話です。しかし、なんと「鶏姦された者が15歳以下だった場合は処罰の対象にはならない」という法律だったので、結局、ほとんどの事件は「なかったことにして、さっぱり忘れろ」と闇に消えていったのでしょう。
男性間の性加害について、鈍感である――あるいはそのように振る舞うのがよいとするのは、日本社会の影の伝統のひとつかもしれませんね。
画像…森鴎外旧宅の森鴎外像



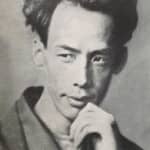

-150x150.jpg)
