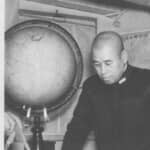日本軍の方針転換と米軍の沖縄本島上陸
沖縄戦と本土決戦の真実⑤
ノルマンディー上陸作戦に匹敵する米軍上陸部隊

爆撃を受けた当時の嘉手納飛行場。米軍によって撮影された写真と思われる。
昭和20年(1945)3月23日、沖縄本島西海岸の沖合に無数の艦船が姿を見せた。スプルーアンス大将率いる米中部太平洋部隊所属の8個の機動部隊を中心とする艦船群で、空母から掃海艇(そうかいてい)まで大小合わせると1300余隻を数えた。総兵力は45万2000名、その規模はノルマンディー上陸作戦に匹敵した。
沖縄戦で米軍が最初に占領したのは慶良間(けらま)諸島だった。3月26日早朝に阿嘉(あか)、慶良間、外地(がいち)、座間味(ざまみ)の各島に上陸した。米軍は慶良間諸島を兵站(へいたん)基地を兼ねた艦隊泊地として手に入れたかったのだ。
対して日本の第32軍は、米軍が慶良間諸島に上陸するとは考えていなかったため、本格的な戦闘部隊を配置していなかったから、米軍は簡単に上陸してしまった。そして各島とも3月31日までに全て占領され、多くの住民が犠牲になった。渡嘉敷(とかしき)では28日の夜、150名を超える住民が集団自決をしている。
一方、沖縄本島西側の沖合に腰を据えていた米艦隊は、4月1日午前5時30分、読谷から嘉手納(かでな)に続く海岸に向けて艦砲射撃を開始し、午前8時30分、米軍の第1陣1万6000名が嘉手納、読谷(よみたん)両飛行場の正面海岸に上陸した。日本軍からの反撃は全くなかった。
米軍の上陸部隊はバックナー陸軍中将を司令官とする第10軍で、嘉手納一帯にはホッジ少将の第24軍団、読谷一帯にはガイガー少将の第3海兵軍団が上陸し、嘉手納飛行場(中飛行場)と読谷飛行場(北飛行場)を占領した。持久戦を覚悟していた日本軍は、夕方までに6万以上の米軍が上陸してきても、まったく反撃しなかった。
強力な米軍の攻撃前に突破される日本軍陣地
沖縄本島は南北に縦長な地形をしている。その北側には険しい山々があり、南側には入り組んだ多数の丘陵がある。
日本軍はこの南側の高地や丘陵を利用して陣地を構築して潜み、最小限の反撃をしながら、米軍を本隊の待ち受ける首里北方の陣地まで誘い出す戦法を採っていた。
4月2日、米第7師団第17連隊は島を東に進み、中城湾(なかぐすくわん)が見渡せる高地を占領した。これで沖縄本島は南北に分断され、北部と南部の連絡は途絶えた。
4月3日、米第24軍はいよいよ南部へ向けて進撃を開始した。しかし、牛島(うしじま)司令官は戦略持久の姿勢を崩さなかった。こうした音無しの構えに対して、この日、第32軍の直属上級司令部である台湾の第10方面軍や第8飛行師団、連合艦隊などから「壕から出て、反撃すべきだ」という意見が殺到した。第32軍は各方面からの要望を無視できなくなり、この夜、攻勢に出ることを決定した。
4月6日、いよいよ白兵戦を交えた戦闘が始まった。日本の各部隊は戦車を伴う米軍に各地で全滅に近い損害を受けた。また、この日は、いわゆる沖縄航空特攻が本格的に始まった日でもある。この航空特攻・菊水一号作戦に呼応して、軍砲兵隊の砲門も初めて開いた。
4月7日になると米軍は第一次防御ラインの日本軍陣地に激しい攻撃を加え、宜野湾(ぎのわん)の大謝名(おおじゃな)、宇地泊を占領した。この4月7日、海上では沖縄を目指していた戦艦「大和」が撃沈されていた。この状況から浦添(うらぞえ)海岸への米軍上陸を予想した第32軍は、8日の総攻撃命令を「敵前攻撃」に変更した。
こうした軍司令部の「持久か、攻撃か」をめぐる方針変更は、沖縄戦に終始見られた特徴だった。
そして持久を主張する八原参謀に対して、長勇(ちょういさむ)参謀長はまたもや「大規模な夜間攻撃による殺傷攻勢」の作戦を決定した。
米軍上陸から約十日間の戦闘で日本軍の死傷者は2279名、米軍は2600名で、ここまでは米軍の方が多かった。戦死者こそ日本は1174名と米軍の475名より多かったが、それは米軍並に医療施設が整っていなかったからでもあった。
監修・文/平塚柾緒