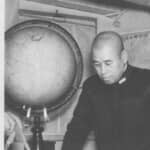沖縄戦前に精鋭部隊を失った日本軍と盤石の米軍
沖縄戦と本土決戦の真実④
台湾防衛に引き抜かれた沖縄防衛の主力・第9師団

沖縄県豊海城市に残る旧海軍司令部壕。約4000人の兵士が収容されていたといわれる。内部は当時の仕様のままで残されている。
昭和20年1月9日、米軍のマッカーサー軍はフィリピンのレイテ島に続いてルソン島にも上陸してきた。マリアナ諸島を奪取したニミッツ軍も、2月19日に日本の玄関口・硫黄島に上陸、またたく間に占領した。こうして米軍が日本本土攻略の前進基地にする重要拠点は、台湾か沖縄だけとなった。どちらを攻略するか、台湾案もあったが、日本本土に近い沖縄が選ばれた(1944年10月)。
その時、沖縄本島に布陣していたのは牛島満(うしじまみつる)中将率いる第32軍だった。当初、第32軍は3個師団と1旅団からなっており、その総力をあげて米軍を水際で迎え撃つ予定だった。しかし、大本営は昭和19年12月下旬、第32軍から沖縄防衛の中心的戦力である第9師団を台湾に転出させてしまう。これは大本営陸軍部の戦略ミスで、彼らはフィリピンに次ぐ米軍の次の目標は、沖縄ではなく台湾と読んでいたからだった。
これはレイテ決戦に台湾から1個師団を抽出したために開いた穴を、沖縄から補ったためだった。そのため第32軍の中心兵力は、当初の3個師団から2個師団になってしまった。
その穴埋めに沖縄県民を防衛召集し、さらには義勇兵という名目で根こそぎ動員をかけたのだが、当然、当初の邀撃計画は変更せざるを得なくなった。そこで考え出されたのが「専守持久」作戦だった。
作戦を考案したのは高級参謀の八原博道(やはらひろみち)大佐だった。八原大佐は圧倒的兵力の米軍に真っ正面から立ち向かっても、勝ち目はないと考えた。逆に敵を自分たちの得意なフィールドに引き込んで消耗させる持久戦に持ち込むほかはないと考えたのだ。米軍の上陸をあえて黙認し、敵が陣地の間近に迫ったら小部隊で肉薄攻撃を仕掛けるという戦法だ。しかし現有戦力ではその専守持久戦さえおぼつかない。悩んだ八原大佐が考えついた答えは「築城」だった。
八原大佐は『必勝の途』という全軍布告のパンフレットに書いた。
「空疎容易な必勝の信念、自暴自棄の敗戦思想は共に捨てよ。全知全能をふりしぼって、自らの手で運命の打開を図ろう。不可能を可能とする唯一の道は築城であり、洞窟戦法である」
米軍の兵力を消耗させる粘り強い持久戦
この持久戦の裏には、できるだけ長く戦って米軍の犠牲を多くし、来るべき本土決戦を一日でも遅らせる使命も担わされていた。そのため地下陣地の建設を急ピッチで進めた。軍司令部も首里城(しゅりじょう)趾の一角に洞窟を掘り、移転した。
第32軍は兵力不足を補うために沖縄県民2万5000名を防衛召集した。師範学校や中学校、専門学校、高等女学校の生徒も徴用した。1761名の男子生徒は「鉄血勤皇隊(てっけつきんのうたい)」と名付けられ、543名の女子生徒は緊急看護衛生班員となった。このうち、沖縄師範学校女子部と県立第1高等女学校の320名はとくに「ひめゆり部隊」と命名された。
3月に入り築城と部隊の配置が終了した。そして25日、米軍の上陸が近いことを確信した第32軍は全軍に戦闘配置の命令を下した。その際に徹底されたのは敵の上陸に際し、水際での攻防は避け、内陸で持久するということ。さらに砲兵にも射撃を禁じた。敵に自分たちの居場所を発見させないためである。こうして、運命の4月1日を迎えた。
対する米軍は、沖縄本島を日本本土進攻と、日本軍が展開している中国大陸へ進攻する作戦拠点にできる島と考えていた。同時に沖縄諸島を占領して基地化すれば、南西方面の海上航路と航空航路を遮断できる上に、連合国軍がフィリピンへ進攻した場合、日本軍の反撃基地になることも防げると考えた。
米軍主体の連合国軍が「アイスバーグ作戦」と名付けた戦力は、S・B・バックナー陸軍中将率いる米陸軍第10軍の5個師団、4個戦車大隊と、米海兵隊3個師団であった。
監修・文/平塚柾緒