米軍の二又進攻作戦と「絶対国防圏」構想の崩壊
沖縄戦と本土決戦の真実③
ふたつのコースから日本本土に迫る米軍

沖縄戦で大破した戦車。アメリカ軍と思われる兵士が機内を確認している。
昭和16年(1941)12月8日、海軍航空隊によるハワイの真珠湾奇襲攻撃と、陸軍部隊によるマレー半島上陸作戦によって始めた日本の対米英蘭戦=太平洋戦争で、当初、日本軍は破竹の快進撃を見せ、わずか3カ月で蘭印(オランダ領東インド=現在のインドネシア)の石油地帯をはじめ東南アジア全体を占領下に置いた。
一方、米統合参謀本部は昭和17年3月30日に、太平洋戦線での陸海軍の作戦分担地域を明確にした。陸軍のダグラス・マッカーサー大将は南西太平洋方面軍を率い、ソロモン諸島からニューギニアにかけての地域を担当、海軍のチェスター・W・ニミッツ大将(米太平洋艦隊司令長官)は太平洋方面軍を率い、南太平洋から中部太平洋にかけての作戦を担当することとした。
アメリカは日本との開戦直後に、イギリスとの協議でヨーロッパ戦線を優先することを決定していたが、昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本の主力空母4隻を葬(ほうむ)る大勝利を挙げると、一挙に反攻に転じた。
米統合参謀本部は南太平洋での対日反攻作戦を「ウォッチタワー」と名付け、8月7日にソロモン諸島のガダルカナル島への上陸を皮切りに、本格的反攻作戦を開始した。日本軍の作戦指導の稚拙さもあって作戦は順調に進み、昭和18年2月に日本軍はガ島から撤退した。
米豪軍はニューギニア戦線でも反撃に出て、18年1月までに東部ニューギニアのブナ、ギルワ地区での戦いに勝利し、日本陸軍の南海支隊はほぼ全滅した。米豪軍の進撃はその後も進み、日本軍は東部ニューギニア戦線を維持できなくなった。
予想以上に「ウォッチタワー」作戦が順調に推移したことから、米統合参謀本部は作戦計画を見直し、18年7月20日、二つのコースを並進して日本本土に迫る計画を決定した。
一つはニミッツ軍がまずギルバート諸島のマキン、タラワを攻略、続いてクェゼリンなどマーシャル諸島を攻略してマリアナ諸島のサイパン、テニアン、グアムの占領を目指して中部太平洋を攻め上がるコース。
もう一つはマッカーサー軍が南方最大の日本軍航空基地ラバウル一帯を制圧し、ニューギニア北岸を西進してフィリピン奪還に向かうニューギニア→フィリピンコースであった。
脆くも崩れ去った「絶対国防圏」構想
開始された米軍の二又進攻作戦は順調で、追い詰められた日本軍は18年9月30日に「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」、いわゆる「絶対国防圏」を決定した。すなわち「帝国戦争遂行上絶対確保すべき要域を千島―小笠原―内南洋(中西部)及び西部ニューギニア―スンダ―ビルマを含む圏域とする」ことを決めた。
だが、米軍を迎撃するための「絶対国防圏」構想も、米機動部隊(ニミッツ軍)の空襲によって次々に崩壊していった。昭和19年2月6日にはクェゼリンが占領され、2月17日にはトラック諸島が猛爆を受けた。3月30日には連合艦隊の泊地パラオが空襲され、連合艦隊司令長官古賀峯一(こがみねいち)大将は飛行機で脱出を図ったが暴風雨に巻き込まれ、消息を絶ってしまった。
そして昭和19年6月15日早朝、米軍は遂に日本の絶対国防圏の要衝サイパンに上陸、米軍は日本本土攻略の前進基地確保に乗り出してきた。戦いは凄惨を極め、22日目の7月7日午前3時30分、日本軍の「バンザイ突撃」を最後に終止符を打った。このサイパン戦で玉砕した日本軍は守備隊約4万3000名のうち4万1244名と言われている。
さらにサイパンには約2万人の一般邦人がおり、このうち島の突端マッピ岬に追い詰められて身投げした日本人は8000名とも1万2000名とも言われている。サイパンを占領した米軍は7月21日には隣接するグアム島に、24日にはテニアン島に攻め入り、占領した。
監修・文/平塚柾緒



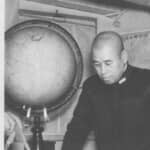

20200007-11-西京丸の奮戦(黄海海戦にて)-150x150.jpg)
