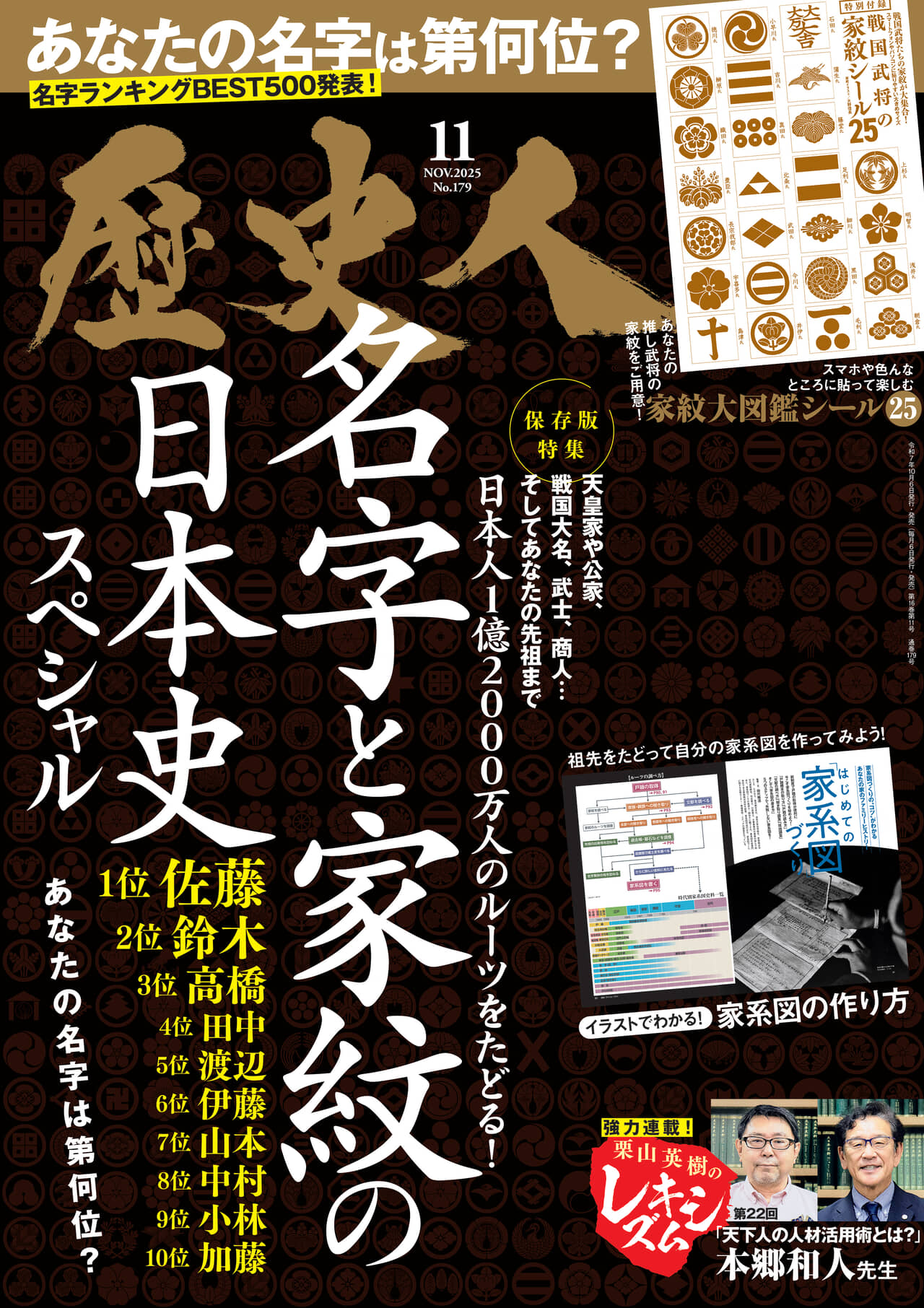関ヶ原の戦いで大勢に流され仕方なく東軍に寝返った「朽木元綱」(西軍)
「関ヶ原の戦い」参戦武将たちの本音! 第1回
参加した将兵が合わせて約15万人。さらには日本各地で繰り広げられた局地戦もあった関ヶ原合戦は、まさに天下分け目の戦いであった。参戦した武将には、取り上げられることが稀なマイナーな武将たちも多い。それらの中から東西両軍武将たちをフォーカスし、なぜ東軍(西軍)に加わったのか、合戦での役割はどんなものであったのか、さらには戦後の動向など、その武将たちの動きと心の裡(うら)を読み解く。

朽木元綱 くつき・もとつな
所領/近江𣏓木2石、動員兵力/600人(推定)、布陣場所/松尾山麓、合戦での動向/戦闘後半に東軍に寝返る、戦後の処遇/減封
長すぎたように思われた夜が今、やっと明けようとしている。雨の気配はまだあるものの、深い霧は天地に満ちて、その中のここかしこで人馬の声が響く。先ほど、徳川家康方である東軍の先鋒ともいえる福島正則(ふくしままさのり)が6千の兵で、ここ関ヶ原盆地の中央付近に進む気配がした。明神の森を背後にして布陣した様子を、配下の物見が伝えて来た。「確かに、白地に紺の山道の紋が描かれた旗が翻っておりました」。
東軍は、福島隊を軸にして加藤嘉明(かとうよしあきら)・3千、筒井定次(つついさだつぐ)・2千8百、田中吉政(たなかよしまさ)・3千が並ぶ。その福島隊の前面に西軍の陣を張るのが宇喜多秀家(うきたひでいえ)・1万7千の大軍である。
石田三成側である西軍として参陣したわが朽木勢6百は松尾山の麓に、赤座直保(あかざなおやす/6百)・小川祐忠(おがわすけただ/2千1百)・脇坂安治(わきざかやすはる/1千)とともに布陣した。総大将・大谷吉継(おおたによしつぐ)に率いられ、この関ヶ原まで転戦を重ねてきた。将兵たちも疲労困憊ではあろうが、今日から始まるであろうこの関ヶ原での大会戦が、まさに本番。「勝てば、必ずや我が世の春が訪れるぞ」などと、儂(わし)も家臣団を前に大声を上げたのが、昨夜のことであった。事実、儂は石田治部少輔(三成)率いる西軍が勝利を掴むと信じていた。だが…。
以前から親しげな書状などを送ってきていた藤堂和泉守(高虎)から、再三に渡って「東軍への寝返り」を迫られたのが、この関ヶ原に到着する前からのことであった。「松尾山に陣取る金五殿(小早川秀秋)が、戦さの最中に東軍に味方することになっている」という高虎の言葉は、儂ばかりか、横一線になって松尾山の麓に布陣する赤座・小川・脇坂らも心を揺さぶられたに違いない。高虎は「東軍勝利の暁には、朽木殿にも十分なる恩賞をと、内府殿(徳川家康)も約束なされております」と力強く言った。昨夜もそう囁(ささや)いてから闇に消えた。他の3将にも同じことを語ったに違いない。「さあて、どうするか」。儂はまだ迷い続けていた。西軍の勝利を願う気持と、万が一の東軍勝利を考えた時、天秤をどちらに掛けるか。そんな迷いを打ち消すように突如喚声が上がり、銃声が聞こえた。最前線で戦さが始まったのだった。
霧はすっかり晴れていた。福島と宇喜多の激突は、宇喜多勢の優勢のまま続く。儂の迷いは晴れそうになった。「やはり、このまま西軍にこそ」と思った矢先であった。
松尾山から小早川勢が雄叫びを上げて駆け下りてきた。その矛先が西軍の大谷隊に向かったのを知って、儂はたじろいだ。しかし、大谷隊は強い。小早川勢を圧倒して、救援に駆け付けた藤堂隊をも押し返した。その時だった。「我らが降る藤堂旗を合図に寝返りを」と約束していたその藤堂旗が大きく翻った。すると先ず脇坂の部隊が、そして赤座の部隊も大谷隊に向けて攻撃開始したのだ…。
儂も赤座らに引きずられるように采配を振り上げ、大谷隊への突入を命じた。弾みであった。「東西どっちが勝っても、永遠に悔いは残るに違いない」。儂の心の声がそう告げている。やがて大谷隊の崩壊が目の淵に見えた。終わった。槍を握る手が震えていた。
◇
合戦後、朽木元綱は寝返ったにもかかわらず約束は守られず、2万石から9550石に減封された。