江戸庶民が愛した寿司の中で、なぜマグロは不人気だったのか?
江戸っ子に愛されたファーストフード 第3回 「寿司」

屋台の握りすしは、1つ4文(約120円)からと安価であったが、やがて、この絵に描かれている松ヶ鮨のように1つ150文(4500円)もするような高級店ができたという。山海愛度圖會 国立国会図書館蔵
てんぷら、そばと並んで日本を代表する料理、すし。すしも江戸時代に人気のあった料理のひとつだった。ところで、すしはなぜ酢飯を使用するのだろうか。
酢飯という酸味のあるめしを使用するのは、もともとすしは、魚を飯の中に付け込んで発酵させ酸っぱくさせた保存食だったからだ。大漁の時などにあまった魚をすしにしていた記録が残る。何年も付け込むことで、魚の硬い骨を柔らかくなりまるごと食べることができるという。こうしたすしは「なれずし」といい稲作をしているアジア諸国では古くから作られており遅くとも奈良時代には日本に入って来た。現在でも滋賀県の名物として売られている「ふなずし」はこうして作られたものだ。
この「なれずし」、確かに魚は腐らせずに保存できるが、飯はドロドロになってしまうので、食べずに捨ててしまう。飯を捨ててしまうのはもったいないと、室町時代には飯の形が残るうちに取り出して魚と一緒に食べるようになった。「生成(なまなれ)」の登場である。
「なれずし」が完成までに数年かかるのに対し、「生成」だと早い場合には数日で食べることができる。しかし、生成でも発酵するまでの時間がかかる。江戸時代の初めころ、もっと早く食べたい! と思う人が、酢を使い、魚と飯に酸味を持たせた「にわかずし」や「当座ずし」、「一夜ずし」と呼ばれる製法を思いついた。これだと1日、2日程度で食べることができる。酢は日本では古くから親しまれていた調味料のひとつだった。室町時代から江戸時代にかけて日本酒の製造が盛んになったことも大きいだろう。日本で古来から使われている米酢は日本酒を作る技術を応用して作るからだ。
このころそれまでのように丸の魚だけでなく、切り身を使った「こけらすし」が登場。箱に酢飯を詰め、その上に魚の切り身を並べ、上から重しをして魚と酢飯となじませる。これが、現在でも作られている「箱ずし」や「押しずし」の原型となった。
しかし、これでも、箱に詰めてすしに重しを乗せて魚と飯がなじむまでの時間や、切り分ける手間がかかる。そこで、切り分ける手間を省くため、酢飯の上に魚を乗せて笹で巻いてから押した「笹巻ずし」が誕生。そのうち、笹で巻くのも押すのもめんどくさいと、握った酢飯の上に魚の切り身を乗せた「握りずし」を江戸の華屋与兵衛が文政年間(1818~1830)ごろ生み出したという。
「握りずし」が登場すると、すし売りのスタイルが一変する。それまでは店売りとバケツぐらいの大きさの桶や箱などにすしを入れて町中を売り歩く行商だったのが、人での多いところへ屋台を出して商うようになった。さらにいえば「握りずし」によってすしは、食べられるようになるまで待つものではなく、場合によっては、注文を受けてから作られるものに変化した。
当時の握りずしは今の握り飯ほどの大きさだったので、たくさん食べるものではなかった。また、すしネタも今とはだいぶ違った。現在人気のウニやいくらなどはなく、まぐろの赤身もトロも人気のネタではなかったとされる。当時は冷蔵技術が発達していなかったので、ネタはすべて煮たり、酢でしめたりと腐りにくくするために加工してあった。

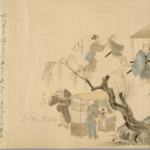
-150x150.png)



