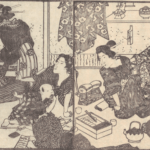過酷な汚れ仕事の代表格「大工」は なぜ江戸の花形の職業だったのか?
転職してみたい江戸のお仕事 第4回 「大工」

江戸における火事の多さが、慢性的に建設需要を下支え。大工をはじめとする建築系職人に対する労働力としての評価を高めた。イラスト/志水則友
一口に職人といっても、江戸時代のそれは様々な人たちがいた。植木職人や畳職人、瓦職人などは今でも見かける職人たちといってもいいだろう。では、江戸で最も花形とされた職人はなんだったのだろうか。
ヒントは、江戸がとても火事が多かったことにある。冬は小火も含めれば火事がない日はなかったといわれるほどだった。当時は消火活動といっても今のような大量の水を一気にホースで放出するような技術はなく、火が燃え移りそうなところにある建物を壊して延焼を食い止めるしか方法がなかった。つまり、一度火事が起きれば、大量の建物が破壊されるので、それを再建しなければならない。そのためには、建物を造る職人、つまり大工が必要になる。大工は、腕さえ確かならば、食うには困らなかったといい、「宵越しの銭は持たない」という言葉はこうした職人たちの自信の表れであろう。
大工が職人の中で一番の花形とされたのは、現場を取り仕切るのが大工の棟梁だからだ。家は、大工だけでは造ることはできない。大工は屋根を葺(ふ)くことも、壁も塗ることも、畳を入れることもできないからだ。こうした専門の職人たちを束ねるのは大工の棟梁の仕事だった。当時は建築士という仕事がなかったので図面を引き、必要な木材の手配も棟梁が行った。現在の工務店のようなものと考えればわかりやすいかもしれない。
では、大工の仕事ぶりはどうだったのだろうか。
朝、早くに起きて現場に行き、今の午前8時前には仕事を開始し、2時間ほど働くと短い休憩をとる。その後、やはり2時間ほど働いて休憩。この長めの昼休憩で鋭気を養って、午後の仕事に取り掛かり、3時ごろにまた休んで、陽が暮れる前には仕事を終えて家路につく。納期が迫っている時などは残業をすることもある。また、急ぎの仕事の場合には、早出をした上に残業もする。こうした場合には、通常の手間賃が五割増しになったといい、大火事で人手が足りない時などは賃金が高騰し、幕府が介入する事態になることもあった。
仕事を終えて家に帰れば、家族がいる場合は家族と一緒に夕食をとり、湯屋に行く。夕食にお銚子の1本がつくくらいのゆとりはあった。
ただし、大工の仕事は雨が降るとできない。「大工殺すに刃物はいらぬ。雨の3日も降ればよい」という戯(ざ)れ歌は、賃金はその日払いが普通で、雨の日が続くと生活に困ってしまうことをうたっている。
実際にはある程度の蓄えはあり、なくてもどこかで金を都合するので死ぬことはなかったようだ。雨で働けない時はどうするか。道具の手入れをすることもあったようだが、湯屋の2階が集会場のようになっていたので、そこに知人と行ったり、江戸のいたるところにあった寄席などに出かけたりしたようだ。大抵の寄席は、朝一番に中に入ったら夜寄席を閉めるまでいても同一料金だ。江戸で本格的な落語を始めた立川焉馬(たてかわえんば)は、大工から転身したとされているし、落語には多くの大工が登場する。「あの大工、仲間の〇〇に似ているなあ」とか「こんな棟梁下で働きたい」と思いながら聞いていたのだろう。
正月や節句、雨や雪などで年間60日ほどは休みであったというが、それでも部屋を借りて、親子4人程度ならば贅沢をしなければ暮せたようだ。