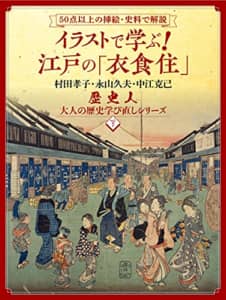江戸人口の半分以上が住んだ「長屋暮らし」の仕組みと間取りとは⁉
いま「学び直し」たい歴史
徳川家康が江戸に入城すると江戸の町は次第に広がり、江戸中期、人口は約100万人の大都市となる。しかし人口の半分以上を占める庶民は質素な長屋暮らしだった。6畳ひと間に家族5人は当たり前で、トイレと井戸はもちろん共用。江戸っ子の半数が住んでいたそんな長屋から、当時の暮らしに迫る。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
日本橋、京橋、神田の通りを60間ごと奥行き20間の街区に

江戸時代の日本橋各地から訪れる人々や物産で、街は賑わい、通りの両側には、「三井越後屋呉服店」や「白木屋(のちの東急百貨店)」をはじめ、店が次々と軒をつらね、隙間なく立ち並んだ。(「東都名所 駿河町之図」歌川広重 国立国会図書館蔵)
江戸庶民の多くは長屋に住み、隣人たちとの生活を楽しんでいた。長屋は棟を長くして建てた集合住宅だがこれには表通りに面した「表長屋」と路地裏の「裏長屋」とがあった。
こうした違いが生じたのは、徳川家康が考えた都市計画に基づく。江戸開発の目標にしたのは京都の町割(都市の区画)で、京間60間(約118メートル。1間=約1・97メートル)四方を基本に、道路に面して奥行き20間の住宅地をつくった。
つまり、一つの街区を京間60間四方(正方形地区)とし、その中央部に20間四方の空き地をつくり、これを会所地とした。家康がつくった江戸の中心地、メインストリートは当初、大橋とよばれていた常盤橋(ときわばし)[千代田区大手町2]から伝馬町[中央区日本橋小伝馬町]へと抜ける奥州街道沿いの本町通り[日本橋本石町、日本橋室町あたり一帯]だった。

町屋街町家は表通りに面した家。町人の住む店舗併設の都市型住宅。同じ民家の一種である農家が、門を構えた敷地の奥に主屋が立つのに比べ、通りに面して比較的均等に立ち並ぶ点に特徴がある。(国立国会図書館蔵)
江戸の町割も日本橋、京橋、神田で行なわれ京間60間四方の正方形の街区が基準とされた。その一つの街区を町人地とし、細分化し、表通りには「表店(おもてだな)」と呼ぶ商店をつくった。
間口は京間5間(約9・5メートル)から10間(約19メートル)、奥行(約38メートル)くらいである。むろん、それより規模の小さい表店もつくられた。間口2間とか3間で、これらは表長屋ともいわれる。
監修・文/中江克己
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。
Amazon / Apple Books / 楽天Kobo