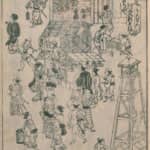伊勢神宮参りの男性客で盛り上がった『古市遊郭』─独自の遊び方とは⁉─
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第8回(伊勢・古市/ふるいち 遊郭 後編)
古市は伊勢神宮の外宮と内宮を結ぶ参宮街道沿いにあり、ここにあった遊郭は全国から伊勢参りに訪れた男性の客で毎夜盛り上がったという。江戸・吉原などとは異なった楽しみ方もでき、独自の文化が生まれていたという。
江戸時代の遊郭は床入りだけではなく、飲んでは踊りの酒宴も楽しんだ

図3『浮世名異女図会』(五渡亭国貞)、国会図書館蔵
図3は画中に「勢州古市おやま踊り」とある。
「おやま」は先述したように遊女のこと。踊っているのは伊勢音頭であろう。伊勢音頭は寛延年間(1748~51)に、古市の妓楼・備前屋で始まった。その後、全国に伝わった。

図4『伊勢名物通神風』(式亭三馬著、文化15年)、国会図書館蔵
図4は、備前屋のにぎわいを描いている。享和二年(1802)、上方に旅した滝沢馬琴は、その紀行『羇旅漫録』に――
古市はいずれも大楼なり。見世は暖簾、二重にかけてあり。軒は常の暖簾の如し。奥行一間の土間ありて、その上がり口にまた、長暖簾をかける。
――と記し、妓楼が立派なのに感心している。
また、古市では最初の客があると、妓楼の遊女すべて、およそ十五、六人から二十人くらいが集まり、にぎやかな酒盛りになる。そのうち、別な客が上がるにともない、徐々に散っていく。そして――
閨房にいるの時にいたりて、衆妓はじめて散ず。それまでは、ほしいままに貪り食うて遊ぶなり。
――と、床入りになるまでは、ほかの遊女も部屋にいて、好き勝手に飲食をしていた。一見、古市の遊女をけなしているかのようだが、同書で、馬琴は伊勢(三重県)の妓楼を総括して――
伊勢の妓楼、しかるべきもの。第一、古市。第二、松坂。第三、一身田。第四、四日市。第五、津。第六、神戸。第七、桑名なり。
――と、古市を高く評価している。
いっぽう、深川の遊里を舞台にした戯作『面美多通身』(廓通交・同集交著、寛政3年頃)に、お伊勢参りをした客の男が古市の事情を語る場面があるが、
有名な妓楼として、千束屋、湊屋、備前屋、柏屋、を挙げている。
戯作『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著、文政5年)で、弥次郎兵衛と喜多八は京都の男と道連れになり、妙見町の旅籠屋に泊まる。妙見町は、古市の手前である。もちろん、旅籠屋にじっとしているはずはない。旅籠屋の亭主の案内で、三人は古市に向かう――
はや日も暮れて、時分はよしと、亭主を案内として三人とも出かけ行くほどに、この妙見町の上はすぐに古市にて、倡家軒を並べ、弾きたつる伊勢音頭の三味線勇ましく、浮かれ浮かれて、千束屋といえるに至れば、女ども皆々走りいで、「よう、ござんした。すぐに、お二階へ」
――という具合だった。「倡家」は娼家で、妓楼のこと。千束屋は、前述の『面美多通身』に出ているように、大店である。

図5『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著、文政5年)、国会図書館蔵
図5は、千束屋での宴席の様子。その後、三人はそれぞれ遊女と床入りした。弥次郎兵衛ら三人は妙見町の旅籠屋に泊まったにもかかわらず、けっきょく寝たのは古市の妓楼・千束屋だった。
『全国遊廓案内』(日本遊覧社、昭和5年)は、「古市遊廓」について――
昔は遊女屋が軒を並べて、その店先には大きな茶釜が据えてあった。そして勅使参向や代参通行の節には、娼妓が赤前垂をかけて、店頭に整列して迎えたものだ。油屋のお紺は死んでも、その名を慕って集い寄る人は今でも、「お紺の間」を見物に来るそうで、油屋は現在、旅館に早変わりしてしまったが、このお紺の間のあるために、相当繫昌している。
――とあり、油屋も妓楼から旅館に転業するほどで、すでに遊廓としては衰退していた。
原因は、明治以降の鉄道の開通である。駅の近くに新たな遊廓ができ、男はそちらに行くようになったのだ。
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。