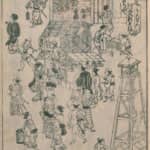芸者は芸を売るが体は売らない⁉「芸者」というお仕事 ~吉原芸者と町芸者~
江戸の性職業 #032
■深川の芸者はすぐ“転ぶ(金をもらって男と寝る)”

図1『吉原十二時絵巻』(文久元年) 国会図書館蔵
江戸の芸者は大きく、吉原芸者と町芸者に分けられた。
吉原芸者は、遊廓(ゆうかく)吉原で働く者で、妓楼(ぎろう)の宴席に呼ばれ、三味線を弾いて座を盛り上げた。
町芸者は、吉原以外の場所で働く芸者である。岡場所はもちろん、盛り場の料理屋や、舟遊びをする屋根舟などに呼ばれ、三味線を弾いて酒宴を盛り上げた。
図1は、吉原芸者である。
左のふたり連れが芸者で、妓楼に向かう所であろう。先を行く男は芸者置屋の若い者で、手にかかえた黒い木箱は三味線箱である。
さて、芸者の方が遊女より上と思っている人は少なくないようだ。「芸者は芸を売るが、体は売らない」から、というわけである。しかし、身分の実態はまったく逆だった。
遊廓や遊里(ゆうり)では、あくまで主役は遊女であり、芸者は宴席における引き立て役に過ぎない。
芸者はけっして出しゃばってはならなかったし、客の男と深い仲になるなどもってのほかである。遊女の領分を侵すことになるからだ。
吉原では、妓楼の宴席には芸者は必ずふたりで出た。図1でも、ふたり一組なのがわかろう。
ふたりで出たのは、客の男と言い交したりしないよう、相互監視するためだった。
とはいえ、男と女の関係である。また、禁止されればされるほど燃え上がるという、人間の厄介な傾向がある。
人目を忍んだ客の男と芸者の逢引きはしばしば起きて、騒動になった。
いっぽう、町芸者には、吉原芸者のような「禁制」はなかった。
というより、芸者が「転ぶ(金をもらって男と寝ること)」のは、当たり前と考えられていた。
吉原以外では、芸者はセックスワーカーだったのである。そのため、町芸者には宴席には必ずふたり一組で出るべしという「掟」もなかった。
とくに、深川の芸者はすぐに転ぶので有名だった。
たとえば、料理屋の宴席で、芸者が気に入ったとしよう。もちろん、客の男は本人に、
「あとで、どうだ?」
と、ささやいてもよい。
自分から言いにくかったら、料理屋の女将(おかみ)に頼めばよかった。あとは女将が手配をして、奥座敷に寝床を用意してくれる。
もちろん、芸者に渡す揚代のほかに、料理屋にも金を渡さねばならないので、遊女と遊ぶよりは高いものについた。

図2『花容女職人鑑』(歌川国貞) 国会図書館蔵
図2は、深川の料理屋の二階座敷である。眼下に広がっているのは、江戸湾(東京湾)の海。
左から、「芸者」、「子供」、「なかゐ」とある。
子供は遊女のこと。深川では遊女を子供と言った。
なかゐは、仲居である。
図3は、深川の芸者置屋の光景。こうして、料理屋などから声がかかるのを待った。

図3『娘消息』(三文舎自楽著、天保10年) 国会図書館蔵