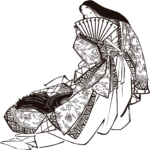「人柱」として橋脚の下に埋められた足軽・源助の悲劇 朝ドラ『ばけばけ』に登場した奇怪な伝承の真相は?
日本史あやしい話
小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが著した『神々の国の首都』に、人柱として橋脚の下に埋められてしまった足軽・源助の不運な出来事が記されているのをご存知だろうか?連続テレビ小説『ばけばけ』にも登場したこの奇怪な伝説が、いったいどのようなものだったのか、著書を紐解いて、あらためて振り返ってみたいと思う。
■『ばけばけ』に登場するおぞましい人柱伝説
連続テレビ小説『ばけばけ』の第7回において、主人公・松野トキが、友人のサワとともに、とある橋の欄干を前に恭しく祈りを捧げるシーンがあったのを覚えておられるだろうか?とある橋とは、いうまでもなく松江大橋のことであるが、その橋の下に、かつて人柱として一人の男が埋められていたことを思い出していただきたいのだ。それを耳にして、少々鳥肌が立つような思いに駆られた方も少なくなかったに違いない。
話の元となったのは、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが著した『神々の国の首都』に記された源助柱の伝説である。まずは、そこに記された時代、ハーンが松江へとやって来た1890年代へと、時計の針を巻き戻してみよう。
ハーンが初めて松江にやって来たのは、1890年8月30日のことであった。その翌朝のこととして、彼が宿泊した富田旅館(現大橋館)2階からの光景が描かれている。障子を開けて望み見たのが、彼が「鉄柱の立ち並ぶ長く白い橋」と表した松江大橋と、それを取り巻く情景であった。
朝靄に包まれる中、川面に帆船が行き交う様を「東洋の海の夢まぼろし」と表し、橋を行き交う人々の下駄の音を「舞踏会の音響」に例えるハーンの感性の豊かさにも、心打たれたものであった。
この時、ハーンが見た松江大橋は、ほんの少し前に鉄橋に架け替えられたばかりのもので、開通式が盛大に催されたことも記録している。
その渡り初めの儀式には、その土地で「一番幸せな人」が選ばれなければならないという。そこで選ばれたのが、結婚生活半世紀以上という二人の老人であった。12人もの子宝に恵まれた上、一人も欠ける事がなかったとか。祝砲の嵐の中の、孫やひ孫に囲まれながらの渡り初め、これ以上ないほどの幸せムード溢れるものであったに違いない。
ところが、である。実はその幸せに包まれた松江大橋の橋桁の下に、とある男が人柱として埋められていたと聞けば、幸せムードも一転。寒々しい思いに駆られてしまうに違いない。男の名は源助。彼もまた、この日の朝までは、それなりに幸せなひと時を享受していたはずであった。
■有無を言わさず人柱として埋められてしまった男
時は、慶長年間(1596〜1615年)というから、関ヶ原の戦いを経て、徳川家康が江戸幕府を開いた頃のことである。この時、出雲の大名になったのが、豊臣政権において三中老として活躍していた堀尾吉晴であった。関ヶ原の戦いで東軍に与したことが評され、出雲国富田に加増移封してきたのだ。
不幸な出来事が起きたのは、慶長12(1607)年のこと。中世山城であった月山富田城が城下町を築くには不向きであったことから、宍道湖と中海を結ぶ太田川近くにそびえる亀田山に築城を開始したことがそもそもの始まりであった。月山富田城を解体してその材料を松江に移動させるために、大橋川に架かっていたカラカラ橋と呼ばれていた小さな竹橋を解体。頑丈な木橋に架け替えることにしたことが、この男にとっての不幸の始まりであった。
橋の架け替えのために、大工たちが橋脚を支える土台を築こうとしたものの、地盤が軟弱で、何度石積みを行っても、流されるばかり。ようやく橋が出来上がったと思いきや、すぐに押し流されてしまうということが繰り返されたという。
そこで考え出されたのが、人柱を立てて、水神の怒りを鎮めようというものであった。もちろん、進んで志願する者などいるわけもなかった。そこで取り決められたのが、襠の付いていない袴、つまりスカート状の行灯袴をはいた男が橋を通りかかれば、有無を言わさず取っ捕まえるというものであった。そこにたまたま通りかかったのが、行灯袴をはいた源助だったというわけだ。
この男、雑賀町に住む足軽で、妻とともに幸せに暮らしていたはずであった。この日の朝、妻は夫に2杯目の茶を勧めたものの、夫はなぜかそれを断って出かけてしまったという。結果として、それが彼の死出の旅を急がせたようだ。もう一杯ゆっくりと茶を味わっていれば、彼が人柱に選ばれることがなかったかもしれなかったからである。
ともあれ、すべては後の祭り。源助が橋を渡りきる前に捕らえられ、直ぐさま、橋脚の下に人柱として埋められてしまった。それが本当に効き目があったからなのか定かではないが、以降、橋の工事も順調に進み、慶長13(1608)年、全長153mの木橋が完成。以降、橋が流されることもなくなったというわけである。彼が埋められた橋脚は、彼の名をとって源助柱と名付けられたという。
ただし、奇妙なことが起き始めたのがそれからである。月のない日の夜中の2〜3時頃ともなると、決まったように源助柱の周りを赤い鬼火が掠め飛ぶようになったのだとか。源助の魂が成仏できずにうろついていると思われたのだ。
そればかりではない。昭和12(1937)年にも、現在の松江大橋の建設中に、深田清技師が落下物のために死亡するという痛ましい事故が発生。それが源助柱の直ぐ側であったことから、「痛ましい昭和の源助」と報じられたものであった。大橋の直ぐ南寄りに源助公園と名つけられた小さな広場に、源助の碑とともに置かれているのがその供養碑(深田清技師の碑)である。

源助柱/撮影:藤井勝彦
- 1
- 2