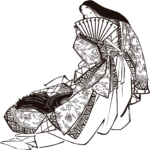息子・伊達政宗を毒殺しようとした母・義姫とは何者か? 「毒殺未遂事件」は政宗の自作自演だった?
日本史あやしい話
伊達政宗の母・義姫といえば、政宗を毒殺しようとした悪女として語られることが多いようだ。義姫が長男・政宗よりも次男・小次郎を溺愛していたから、あるいは政宗が義姫の父と兄を死に追いやったことが原因と言われることもある。それでも、どんな理由があろうとも、義姫が我が子を手にかけたとは信じられない。むしろ、秀吉の仕置を前に、政宗による自作自演であった可能性が高いのだ。いったい、どういうことが起きていたのか、振り返ってみることにしよう。
■岩下志麻さんが演じた男勝りの女傑
伊達政宗といえば、独眼竜政宗の名でも知られた奥州随一の名将である。幼い頃に天然痘を患ったことから、右目を失って隻眼に。史実かどうかはともあれ、いつの間にか、黒い眼帯姿の政宗像が人々の間に定着していったようである。
1987年に放映された大河ドラマ『独眼竜政宗』で俳優の渡辺謙さんが政宗役を演じた際には、刀の鍔を付けて登場。その雄姿に視聴者が酔いしれたものか、最高視聴率47.8%を記録。驚異的な数字をはじき出すほどの人気ぶりであった。
では、その名将の母が誰だったのか、覚えておられるだろうか?大河ドラマでは、女優の岩下志麻さんが演じていた、男勝りの女傑・義姫(保春院)である。出羽国の戦国大名・最上義守の娘で、対立していた伊達家との調整役として伊達輝宗に嫁がされ(1566年)、翌年に長男を生んだ。それが梵天丸こと、後の政宗であった。
この義姫について語る際、どうしても避けて通れないのが、我が子・政宗を毒殺しようとしたという疑惑である。腹を痛めて生んだ我が子を手にかけるなど、本来なら考えられないような話ではあるものの、江戸時代に記された『伊達治家記録』にその詳細が記されていたゆえに無視するわけにはいかず、とうとう史実であったかのように流布されてしまったのである。その真偽のほどはいかに? 真相を探ることにしたい。
■長男・政宗よりも、次男・小次郎を溺愛したから?
時は、秀吉が天下統一の最終局面ともいうべき小田原征伐(1590年)直前のことである。この時、政宗24歳。家督を相続して6年目を迎えた、血気盛んなうら若き青年であった。秀吉の惣無事令(私戦禁止令)をも無視して最上家らとの戦いを繰り広げるなど、領土拡大に勢い込んでいた頃のことである。
そんな折、突如秀吉から小田原参陣を命じられたから猛反発。「秀吉ごときが何するものぞ」との思いがあったのだろう。しかも、小田原城を守る後北条氏とは、父・輝宗の代から同盟を結ぶ仲。「長年の同盟者を裏切ることなぞ出来るか!」との思いも、政宗の決断を鈍らせる一因であった。
それでも、相手は侮ることなどできそうもない、天下随一の実力者である。どうすべきか悶々とするうちに、とうとう参陣が遅れてしまった。何とか意を曲げて小田原へと向かったものの、時すでに遅し。戦いはほぼ終結していたからである。それは同時に、政宗の死を意味していた。自らの命に逆らった形となった政宗を秀吉が生かしておくとは、とても思えなかったのだ。
ここで政宗が思い切った策に出たことは、多くの方の知るところだろう。何と死装束を身にまとって謁見するという、見え透いた行動に出たのだ。政宗のこの芝居染みた行動には、さすがの秀吉も思わず苦笑。わずかな減俸程度で怒りの矛を収めることにしてしまったのだ。この辺りが、歴史の面白いところである。要するに、何が効を奏するかわからないというべきか。
ともあれ、ここで問題にしたいのは、その直前の出来事である。政宗が小田原へと出立する前夜に起きた、とある事件である。政宗が悶々として出立を遅らせていることに業を煮やした母・義姫が、伊達家が秀吉から滅ぼされてしまうことを案じて、密かに政宗を殺し、次男の小次郎に跡を継がせて難を逃れようとしたという。それが、出立を前に別れの宴を催していたそのさ中、政宗が口にする料理に毒を盛るという手口であった。しかし、政宗が料理をわずかしか口にしなかったことで、血を吐いて倒れただけで済んだ。死に至らず難を逃れたのである。それが本当に義姫の仕組んだものであったかどうかは、後世の識者の間でも侃々諤々。それでも結局は、わからずじまいで、未だ解明には至っていないようである。
ただし、ここでは一旦、それが事実だったと仮定して話を進めてくことにしよう。となれば、気になるのが、なぜ義姫が政宗を毒殺しようとしたのか?だ。よく語られるところとしては、育児を守役の手に奪われて直接可愛がることのできなかった長男・政宗よりも、自らの手で育てた次男・小次郎の方を溺愛したからといわれることもあるが、まさかそれだけが理由ではあるまい。その底辺に、もっと切実なる問題があったはず。それは何か?を解き明かしたいと思うのだ。その解明のヒントになりそうなのが、義姫を取り巻く複雑怪奇な家庭問題であった。いったい、どいうことなのだろうか?
- 1
- 2