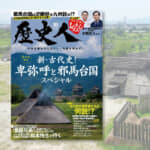女王「卑弥呼」の死後、なぜ13歳の少女「壱与」が王として擁立されたのか─壱与とはどのような人物だったのか─
新・古代史!卑弥呼と邪馬台国 #04

壱与の墓、といわれることもある「西殿塚古墳」
■「鬼道」による統治が壱与によって復活する
卑弥呼が亡くなったあと、次の倭国の王となったのは、その血をひく者ではなかった。あとを継いだのは「男王」であり、おそらく彼は卑弥呼のようなシャーマン的な性格の強い王でもなかった。しかしこの王の下では国が収まらず、再び戦乱が起こった。そこで卑弥呼の「宗女」(同じ一族の娘)である壱与(いよ)という13歳の少女を王に立てたところ、戦乱は収まったという。
「更に男王を立てしも国中服せず。更に当時千余人を相誅殺(あいちゅううさつ)す。復に卑弥呼の宗女壱与年十三なるを立てて王と為し、国中遂に定まる。」(『魏志』倭人伝)
卑弥呼については「年すでに長大なるも夫婿無し」と倭人伝にあるから、彼女は終生独身であった。子どもはなかったはずだ。壱与は、卑弥呼の「宗女」(同じ一族の娘)とあるから、最も近ければ卑弥呼の姪かもしれない。あるいはもう一世代下で、姪や弟の子かもしれない。いずれにせよ、卑弥呼の血を引く13歳の少女で、おそらく卑弥呼と同じ種類の「鬼道を使う」シャーマンだったのだろう。
この女王のもとで卑弥呼の死後に勃発した戦乱はやっと終わったという。それはいったん男王によって途切れかけた卑弥呼の「鬼道」による統治が、壱与によって復活したことを意味しよう。
卑弥呼の死(250年ころ)から混乱を経ての壱与の擁立まで何年ほど要したのかは明らかでないが、266年に「倭の女王」が朝貢してきたという史料がある。『日本書紀』が引用する「晋」の「起居注(日記体で記した中国皇帝の記録)」に
「武帝、泰初二年十月、倭の女王、訳を重ねて貢献せしむ。」
とあるのである。この時の「女王」とは壱与のことであろう。仮に卑弥呼の死の3年後に擁立されたとするならば、この時に13歳、266年には26歳くらいということになる。
周知のように、卑弥呼には補佐役である「男弟」がいた。
「男弟有り。佐(たす)けて国を治む。」
13歳の壱与にもそうした存在がいたに違いない。それは壱与より年上の親族、あるいは壱与の父親かもしれない。実質的にはこの人物が倭国を取り仕切っていたと言っていいのではないか。
壱与の墓として、このところ取り上げられることの多いのが、奈良県桜井市にある西殿塚古墳(全長230m)である。オオヤマト古墳群の最北、大和古墳群に位置する巨大前方後円墳である。現在、継体天皇の皇后「手白髪皇女」の陵墓に指定されていて、立ち入りが許されていない。
この古墳は箸墓古墳、行燈山古墳(崇神天皇陵古墳)、渋谷向山古墳(景行天皇陵古墳)と異なり、周濠がない。白石太一郎氏によると、この古墳には前方部と後円部の2か所にほぼ同型同大の方形壇があり、それが埋葬施設らしいという。白石氏は、ここに男女2人が埋葬されているのではと推定している。一人が壱与だとすると、もう一人は誰だろうか。私にはこれが壱与の補佐を務めた親族ではないかと思われる。
監修・文/水谷千秋

漢委奴国王印-150x150.jpg)