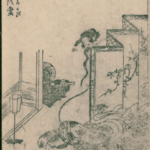功妙なバランスで幕府を支えた「老中制」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉚
9月7日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第34回「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」では、田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)が表舞台から去る一方、新たな老中・松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)の望む世が訪れようとしていた。まったく異なる時代の到来に、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)は抗(あらが)う姿勢を鮮明にするのだった。
■〝遊び〟のない世に蔦重が公然と反発する

『南天荘次筆』(国立国会図書館蔵)に描かれた松平定信。老中としての在任期間は1787〜1793年のわずか6年ほどだったが、江戸の三大改革のひとつである「寛政の改革」を主導した。疲弊した農村の立て直しのために農業人口の増加や耕地面積の拡大に積極的に取り組んだ一方、庶民にまで倹約を強いるなどの厳しい統制政策は少なからぬ不評を買った。
蔦重の予想に反して、新たな老中首座に就いたのは松平定信だった。異例の抜擢ではあったが、田沼時代とはまったく異なる世が訪れることを期待する民衆は、熱烈に歓迎した。その背景には、「徳川吉宗の孫」「現在の米不足を解消した」など、定信自らが市中に流した虚実入り交じる情報が好感されたことが大きかった。
質素倹約を旨とする定信を「うさんくさい」と毛嫌いする蔦重に対し、妻のてい(橋本愛)は「極めてまっとう」と反論する。ていの意見は世間の大方の声でもあった。
奢侈(しゃし)をことのほか嫌う定信は、華やかだった田沼派の役人を一斉に検挙。さらに、幕府の突き上げを食らった太田南畝(おおたなんぽ/桐谷健太)も執筆業から退くことを考え始めるほど、権力による「見せしめ」が日増しに厳しくなっていた。
こうした世の流れに抗うべく、蔦重は、定信の政治を表向き持ち上げるようでからかう内容の黄表紙と、時勢に逆行する豪華な狂歌絵本を出そうと動き出すのだった。
- 1
- 2