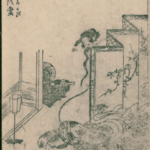功妙なバランスで幕府を支えた「老中制」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉚
■血縁と実力主義という絶妙なバランスが功を奏する
265年間にわたって江戸幕府が日本を統治できた背景の一つに、「老中」という優れた政治システムがあった。将軍に直属し幕政を統轄したこの最高職は、単なる重臣の寄り合いではなく、高度に洗練された統治機構だった。
老中の選考基準は極めて厳格だった。徳川家に古くから仕える譜代大名で、3万石以上12万石以下の城主が就任するのが原則だったといわれている。上限が設けられているのは、過度な権力集中を防ぐ仕組みだったようだ。奏者番(そうしゃばん)や京都所司代などの要職を歴任した実力者が選ばれ、老中就任者の実に6割余が奏者番を経験していた。
制度として特筆すべきは月番制である。4名から5名の老中が毎月交代で政務の責任者となり、重要事項は全員の合議で決定する。この輪番制により権力の独占を防ぎ、政策の継続性も確保された。老中は江戸城の御用部屋で午前10時から午後2時まで執務したが、緊急時には早朝から深夜まで対応に追われる激務だった。
時代の変化に応じた組織改革も行なわれている。1680(延宝8)年には堀田正俊(ほったまさとし)が財政専門の勝手掛老中(かってがかりろうじゅう)に就任し、専門性を重視した体制が始まる。享保年間、勝手掛老中となった水野忠之(みずのただゆき)は上米の制や新田開発を推進して財政再建を図ったが、急進的な改革が反発を招くこともあった。
老中への登用には厳格な資格要件がある一方で、実力主義の側面も見られた。石高が規定に満たなくても、能力があれば老中格に登用される道があり、奏者番での実務経験が重視された。阿部正弘(あべまさひろ)が25歳の若さで抜擢されたのは、公議世論の政治を行ったことからも分かるように、その柔軟な発想力と政治的手腕が評価されたからである。
一方、戦略的なキャリア形成で老中の座を射止めた者もいた。水野忠邦(ただくに)は九州の辺境である唐津から江戸近郊の浜松への転封を画策し、幕政の中枢に近づく環境を整えた。松平定信は田安家の出身でありながら長子ではなかったため、白河藩への養子縁組という選択で活路を見出し、藩主としての実績を積んで老中首座に上り詰めている。
幕末期にはさらなる組織変革が行なわれた。1856(安政3)年に外国御用取扱を新設して海防を専掌させ、1867(慶応3)年には月番制を廃止して国内事務、会計、外国事務、陸軍、海軍の五総裁制に移行した。これは機能別組織への大胆な転換だった。
阿部正弘は従来の幕閣内だけの意思決定を改め、諸大名や有識者の意見を積極的に求めた。この開放的な政治手法は、閉鎖的とされがちだった幕府政治の新たな側面を示している。
老中制度の本質は、血縁や家格という安定的な要因と、実力による競争という活性化要因の絶妙な均衡にあった。合議制による集合知の活用、専門性の重視、時代に応じた柔軟な組織変革。これらの要素が相まって、二世紀半を超えて江戸幕府を支えたのである。
現代においても、組織の持続性と革新性をいかに両立させるかは普遍的課題といえる。老中たちが築いた統治システムには、時代を超えた組織運営の知恵が込められている。
- 1
- 2