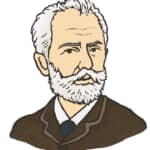空気は読んだが「女帝」への“忖度”を怠たり、権勢の座から転がり落ちた「政界のサラブレッド」とは?
忖度と空気で読む日本史
藤原氏が歴史に決定的な影響を及ぼすようになった奈良時代、一門でもっとも栄耀栄華を極めたのが藤原仲麻呂(なかまろ)だった。しかし、その権勢は長続きせず、最期は謀反により自滅する。背景には、庇護者であった光明皇太后の死後、急速に存在感を高めた孝謙天皇に対する仲麻呂の“忖度”の欠如があった。
■光明皇太后の引き立てで権勢を極めた政界のサラブレッド
藤原氏といえば、後世、摂関職を独占する北家(ほっけ)が主流派にみえるが、もともと宗家は不比等の嫡子・武智麻呂(むちまろ)が起こした南家であった。その武智麻呂の次男で、南家の全盛期を築いたのが仲麻呂である。
仲麻呂の出世を後押ししたのは叔母の光明皇太后である。光明は不比等の娘で、臣下として初めて皇后になった女性である。内向的でヤル気のない夫の聖武天皇以上に熱心に政治や文化事業に取り組んだことでも知られる。
天平勝宝元年(749)、娘の孝謙天皇が即位し皇太后となった光明は、大胆な政治改革を行う。専属の役所である皇后宮職を紫微中台に改編して、太政官に匹敵する強力な権限をもたせ、仲麻呂をその長官に任じたのである。仲麻呂は兄の右大臣・藤原豊成や政権首班の左大臣・橘諸兄をしのぐ権勢を誇るようになり、「重要な政を一人で掌握し、皆がその権勢を妬んだ」といわれた。
仲麻呂は自身の権力を固めるために手段を選ばなかった。聖武太上天皇が崩御した翌天平宝字2年(757)、皇太子・道祖王に「素行不良で軽薄である」と難くせをつけ、その座から引きずりおろし、自身の婿である大炊王(淳仁天皇)を皇太子にすえた。
同年7月には、仲麻呂の殺害を企てた橘奈良麻呂とその一味を捕らえ、激しい拷問の末に獄死させた。この中には、皇位継承候補者に立てられた黄文王や道祖王などの皇族も含まれていた。
こうして、反体勢力を一掃した仲麻呂は、天平宝字2年(758)、孝謙女帝から淳仁天皇への譲位を実行する。さらに、淳仁から恵美押勝(えみのおしかつ)というめでたい名をもらい、翌年、太政大臣に相当する大師(だいし)となり位人臣を極めた(当時、朝廷の官庁や官職名は、中国かぶれの仲麻呂によって唐風に変えられていた)。大宝律令の施行後、初の太政大臣任官である。
■光明皇太后の死、道鏡の登場に危機感を募らせる仲麻呂
だが、仲麻呂の絶頂期は長くは続かなかった。同4年(760)、後ろ盾だった光明皇太后が亡くなり、これまでおとなしくしていた孝謙太上天皇が、積極的に政治に介入するようになったのだ。
振り返れば、これまで孝謙は、光明と仲麻呂に頭をおさえられ政治を主導することはなかった。しかし、後年、孝謙が寵愛する道鏡を皇位につけようとゴリ押しことをみても、本来は自己主張の強い女性であったと思われる。
それだけに、光明の庇護をいいことに、自身に忖度せず政治をほしいままにする仲麻呂を、孝謙は苦々しい思いで見ていたことだろう。光明皇太后という重石のとれた孝謙は、徐々に仲麻呂に対する敵意をむき出しにしていくのである。
両者の対立が明らかになるのは同6年(762)のことである。孝謙は詔を出し「今の帝(淳仁)は私の言うことに従わず、田舎者のような恨みを言い、してはならないことをした」と糾弾し、「今後は日常の祭祀などの小事は帝が行い、賞罰など国家の大事は私が行う」と宣言したのだ。
おりしも、孝謙が看病僧である道鏡を寵愛し始めた頃で、自身も出家してしまうほどの入れ込みようだった。それを淳仁が諫めたことで、女帝の怒りをかったのである。
もちろん、淳仁にそれを言わせたのは、道鏡の台頭に脅威を感じた仲麻呂である。当然、孝謙もそれに気づいていたはずだ。怒りを募らせた女帝は、道鏡をさらに重く用いるようになり、太政官を経ることなく自身の政治意思を執行する勅旨省(ちょくしちょう)を創設し、仲麻呂を牽制した。
対する仲麻呂は、息子や側近たちを太政官や衛府の要職につけて朝廷の軍事力を掌握。自ら畿内近国の軍兵を統括する都督使(ととくし)に就任し、諸国から兵や兵糧を集めた。さらに、淳仁の兄・船王と謀って、孝謙の過ちを告発する準備を進めたという。明らかなクーデター計画である。女帝への“忖度”はできないが、自身への風当たりが強くなっているという“空気”は読めたということなのだろう。
これに対する孝謙側の動きは早かった。坂上苅田麻呂(かりたまろ/田村麻呂の父)を淳仁のもとに派遣して、天皇大権をふるうための鈴印(駅鈴と内印)を奪った。諸国に軍令を発する手段を失った仲麻呂は、北陸に逃れる途中、朝廷軍に追いつかれ、琵琶湖の湖上に逃れたところで殺害される。
女帝への忖度を怠り、権勢をほしいままにした剛腕政治家のあっけない最期であった。

孝謙(称徳)天皇 国立国会図書館蔵