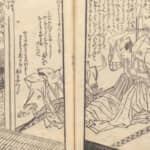田沼意次の失脚と田沼派の残酷な「手のひら返し」 子らにまで及んだ「縁切り」の結果とは
大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第31回「我が名は天」が放送された。大雨で利根川は決壊し、江戸の町は大洪水に見舞われた。蔦重(演:横浜流星)は深川の長屋で暮らす新之助(演:井之脇海)とふく(演:小野花梨)を気にかけ支援するが、その想いは最悪の結果に繋がってしまう。一方江戸城では、10代将軍・家治(演:眞島秀和)が息を引き取り、田沼意次(演:渡辺謙)は老中辞職に追い込まれてしまった。今回は、命運尽きた意次と“田沼派”の手のひら返しについて取り上げる。
■天災・飢饉に悩まされ続けた田沼政治の終焉
田沼意次が政治のトップに立っていた“田沼政治期”、それはたて続けに天災に見舞われる苦難の時期でもあった。とどめを刺したとも言えるのが、天明6年(1786)に起きた大雨である。これによって関東の河川は氾濫し、洪水に見舞われる。水害によって農作物は甚大な被害をうけ、米価高騰にも繋がった。何より、これによって起きた利根川氾濫が、意次が推し進めていた印旛沼干拓計画に致命傷を与えたのである。
それに加えて、最悪のタイミングで「御用金令」が出されていた。実質的な増税ではないかと大反発をくらい、諸大名の抵抗にもあって結局この政策は撤回に追い込まれたのだった。そして、この失策こそが田沼政治に対する不満が大爆発するきっかけになったのである。
さらに意次にとって運が悪かったのは、この時期に頼みの綱である主君・家治が病に倒れたことである。意次が推薦した医師が治療にあたったが、家治の容態は急激に悪化し、やがてその生涯を閉じた。享年50である。この死によってこれまで良好な関係を維持していた大奥にまで見放され、意次の命運はここに尽きた。
政治責任を追及され老中辞職を迫られた意次は、その圧力に屈して老中から退くことを願い出るしかなかった。そして意次の名代である横須賀藩主・西尾忠移と旗本の松平信志が呼び出され、老中・水野忠友から辞職願の受理、すなわちお役御免が言い渡されたのだった。
この水野忠友は、意次の四男・意正を養子にし、娘と結婚させて「水野忠徳」と名乗らせていた。安永4年(1775)には家治への御目見えも叶っている将来を嘱望された若者だった。しかし、意次が失脚し老中の職を辞するやいなや、すぐさま養子縁組を解消し(幕府もそれを認め)、田沼家に送り返したのである。
意次は自身の“家柄コンプレックス”を解消し、政治基盤を盤石なものにするために有力な家との姻戚関係を築いていたが、それも瓦解していく。老中・松平康福は自身の娘を田沼意知(意次の息子で城内で起きた刃傷事件で死去)に嫁がせたことで姻戚関係にあったが、「以後意次とは交際しない」という旨の届出を提出。既に亡くなっていた娘の改葬までして田沼と縁を切ったことをアピールした。
続いて、意次に取り立てられて奥医師になっていた千賀氏も意次との関係を絶った旨の届出を出した。さらに、意次が三女を嫁がせた西尾忠移と四女を嫁がせた井伊直朗は、それぞれ妻とは既に死別していたものの改めて「離縁」の措置をとるほど入念に「田沼の関係者ではない」ことを示した。
みな、かつては田沼家とどうにか縁を持って意次の信頼を勝ち取り、立身出世を願っていた者たちである。また、意次も姻戚関係を築き、こうした“田沼派”を積極的に登用した。それが老中の職を退いた途端にこのありさまとなったのである。この時点では「病のため」という建前での辞職が認められただけであり、何ら処罰も受けていない状態だったにも関わらずである。一説には、じつに50以上の家の大名・旗本が意次の老中辞職を機に田沼家との縁を切ったという。

イラストAC
<参考>
■安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた変革者』(日経ビジネス文庫)