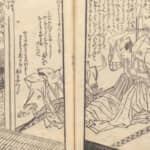人喰いヒグマを解剖して実食した恐怖の体験 死者4名をだした「札幌丘珠事件」の顛末
歴史に学ぶ熊害・獣害
明治11年(1878)1月11日から18日にかけて、現在の札幌市中央区と東区で発生した「札幌丘珠事件」。第1の事件では、猟師が冬眠中のヒグマを仕留めそこなったために逆襲された。その後、空腹のヒグマは駆除隊からの逃走を続け、18日未明に丘珠村で暮らしていた夫婦と生まれたばかりの赤子の3名が住む小屋を急襲したのが第2の事件となる。
物音に気付いて外の様子を窺おうとした父はヒグマの一撃を受けてほぼ即死し、赤ん坊を抱えて逃げ出した母は後ろから爪で攻撃されて頭皮がはがれるほどの重傷を負った。その衝撃で雪原に投げ出された赤ん坊はすぐさまヒグマに襲われて絶命し、喰われてしまう。
この事件では、最終的に父と子、そして1人の雇い人の3名と第1の事件の被害者である猟師の4名が死亡。母と、母が助けを求めたもう1人の雇い人も重傷を負う結果となった。
ヒグマは18日昼に駆除隊によって射殺された。オスの成獣で、体長は1.9mに及んだという。その後、札幌農学校(現在の北海道大学)に運び込まれ、教授と学生らによって解剖されることになった。札幌農学校の1期生で、クラーク博士の指導を受けた大島正健氏が回顧したその時の様子が『クラーク先生とその弟子たち』(教文館)に綴られている。
それによると、学生らは滅多にないヒグマの解剖という経験を歓迎し、解剖実習にとりかかったそうだ。そのうちの2~3人が、教授にバレないようにヒグマの肉を切り取り、休憩時間に炭火で焼いて口にしたという。そして「熊の肉は臭いなァ、恐ろしく堅いなァ」と言い合っていたというのだ。
その後、いざ本格的に内蔵切開に取りかかると、胃からは赤ん坊の赤い頭巾と思われる布片や髪の毛、そして消化されかかっている人体の一部などが大量に出てきた。そのグロテスクな光景と悪臭に、先程熊の肉を口にした学生らは外に飛び出して口に指を入れ、必死に熊の肉を吐き出そうとしたという。想像するだけで恐ろしい。
ヒグマのはく製は、その後開拓史博物館に保管され、明治天皇が明治14年(1881)に北海道を訪れた際に見学したため「天覧のはく製」となった。現在は胃の内容物をアルコールに漬けたものと一緒に北海道大学植物園に保管されている(一般非公開)。
本州でも近年熊の被害が報道され、とくに東北では熊の目撃情報が連日のように舞い込んできている。7月29日には、宮城県内で「熊出没注意報」が発令され、住民や観光客に注意を呼びかける事態になった。夏休みに入り、レジャーで山を訪れる方も多いかもしれない。日本における熊害の歴史からその恐ろしさと危険性を再認識し、事前のリサーチや予定変更、万全の対策等に繋げていただければと願う。

ヒグマ/写真AC ※本件とは関わりがないヒグマ
<参考>
■中山茂大『神々の復讐 人喰いヒグマたちの北海道開拓史』(講談社)
■札幌市教育委員会『札幌事件簿』(北海道新聞社)