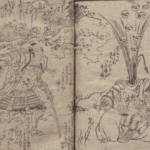土山宗次郎が背負った田沼時代の「光」と「影」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉓
6月15日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第23回「我こそは江戸一利者なり」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)に日本橋への出店の話が持ち上がる。吉原を捨てることになると反対する声もあがるなか、吉原の住人に突きつけられた現実が、蔦重に決意を促した。
■人気書店となった耕書堂に日本橋出店の話が持ち上がる

中央に描かれているのが、土山宗次郎が身請けした誰袖(『新美人合自筆鏡 吉原傾城』国立国会図書館蔵)。土山宗次郎は、誰袖の前にも700両で別の女郎を身請けしたといわれている。吉原を舞台にした、公金を使った派手な遊びが仇となり、悲劇的な最期を迎えた。
1783(天明3)年、田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)の権勢が頂点に達し、息子・意知(おきとも/宮沢氷魚)が奏者番に抜擢される。意次に近い土山宗次郎(つちやまそうじろう/栁俊太郎)は狂歌の会を頻繁に催し、この文化的潮流に乗じて蔦重に日本橋への出店を持ちかける。一方で意知は、蔦重に蝦夷(えぞ)地を天領とする計画への協力を求めるが、蔦重は拒否。しかし意知の言葉から、誰袖(たがそで/福原遥)や大文字屋の主(伊藤淳史)がこの件に深く関わっていることを察知する。
その後、誰袖は女郎の衣装を口実に松前藩の廣年(ひろとし/ひょうろく)に琥珀の買い取りを依頼し、抜荷(ぬけに)を勧める。抜荷が御法度であることを理由に激怒する廣年の前で偽りの涙を見せ、誰袖は承諾を引き出すのだった。
同じ頃、大田南畝(おおたなんぽ/桐谷健太)の人気が爆発的に高まり、蔦重も江戸一の「利者」として名声を得ていた。出版界では競争が激化し、蔦重は呉服屋から西村屋の錦絵「雛形若菜」の販売協力を依頼されるものの、自店の「青楼名君自筆集」の競合になるため、頭を悩ませる。
蔦重の耕書堂の本だろうが、憎き江戸市中の本屋から出す本だろうが、吉原の女郎が全国に広がるためならこだわりを捨てるべき、とする駿河屋(するがや/高橋克実)らの言葉に、蔦重は反発する。
そんな中、蔦重にとって転機となったのは、吉原の常連客・和泉屋(田山涼成)の弔いの一件だった。弔いを欠席した蔦重だったが、吉原者というだけで参列した吉原の親父たちが雨の中に座らされたと聞き、心を痛める。
歌麿(うたまろ/染谷将太)の励ましを受けた蔦重は、ついに吉原の親父たちの前で日本橋出店を宣言する。駿河屋に殴られても蹴られても「江戸の外れの吉原もんが、日本橋で商いを切り回しゃ、誰にもさげすまれない」と語り、日本一の絵師や戯作者を抱える強みを挙げて「足んねぇのは、日本橋だけ」と豪語するのだった。
こうして蔦重は日本橋の書店・丸屋の買収に動き出すが、皮肉にも丸屋が傾いた原因は、女将の元婿が吉原の花魁に店の金をつぎ込み、さらに蔦屋の往来物の売り出しが決定打となったことだった。この事実を知った蔦重は、買収の難しさを思い知るのだった。
- 1
- 2