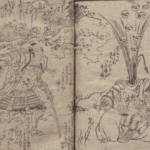土山宗次郎が背負った田沼時代の「光」と「影」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉓
■切腹も許されなかった悲劇的な最期
土山宗次郎は旗本・土山家に生まれ、本名は孝之とされる。生年は分かっていないが、1740(元文5)年生まれの可能性が高い。
文官としての素質が認められ、老中・田沼意次との出会いで宗次郎の人生は大きく動き出す。1776(安永5)年、幕府財政を司る要職である勘定組頭に抜擢され、田沼政権の主要な実務官僚として台頭した。
彼の最大の功績は、蝦夷地(現在の北海道)の実地探査と開発政策だった。当時、ロシア南下への危機感が高まる中、工藤平助の『赤蝦夷風説考』を参考に、蝦夷地の統治・開発を提言。1784(天明4)年には平秩東作(へづつとうさく)を派遣して現地調査を行わせ、その結果が『東遊記』としてまとめられた。同書は当時の松前藩やアイヌ文化を伝える貴重な史料となっている。彼は単なる官僚ではなく、開発行政の実践者であったと言える。
一方で、宗次郎は江戸の文化サロンでも存在感を示した。狂歌師・大田南畝らと深く親交しており、文化人たちのパトロンとしても知られている。
しかし、宗次郎の名が江戸市中に知れ渡ったのは、財政官僚としての功績ではなく、1784(天明4)年に吉原の花魁・誰袖を1200両という破格の金額で身請けしたことだった。これは現在の貨幣価値で数千万円から1億円以上に相当するとされ、「身分を弁(わけま)えぬ放縦」や「奢侈(しゃし)の象徴」として風刺の題材となった。
この豪遊は、公金を扱う者としての責任感に欠ける行為として、後に彼の失脚につながる一因となる。
栄華を極めた宗次郎の運命が暗転するきっかけとなったのは、意次の失脚だ。誰袖を身請けした約2年後、意次の失脚と同時期に宗次郎も閑職に左遷された。
さらに、勘定組頭時代の公金の使途不明を理由に、背任・横領の嫌疑がかけられる。この追及は、田沼政治を批判し、倹約・農本主義を掲げる松平定信(まつだいらさだのぶ)主導の「寛政の改革」が始まったことと無関係ではない。
宗次郎は田沼時代の象徴的存在として、新政権による清算、すなわち政治的粛清の標的となったと考えられる。追及を逃れるため、武蔵国所沢に身を隠したが、ほどなく逮捕。詮議(せんぎ)の末、1787(天明7)年12月に斬首刑に処された。武士でありながら切腹も許されなかった最期は、寛政改革という名の粛清の先駆けとなった。
- 1
- 2