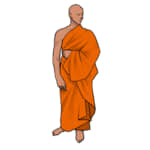ひめゆり学徒隊の悲劇的な運命を描いた名作『ひめゆりの塔』【昭和の映画史】
■激戦の地・沖縄で若い命を散らした乙女たちの悲劇
6月23日は沖縄戦終結の日である。実際にはこの日、摩文仁の指令壕で牛島中将以下の沖縄守備隊(陸軍第32軍)が集団自決し、日本軍による組織的抵抗が終わった。
沖縄戦の悲劇は、住民たちの苦難がこれで終わらなかったことである。住民や駆り出された少年少女たちの悲劇は、8月15日の玉音放送まで続いた。いや、その後もまだ続いた。さらに言えば敗戦後も続き、本土返還後も続き、そして今日まで続いている。
最近、数十年前にひめゆり平和祈念資料館を訪れた時の、うろ覚えの記憶を元に奇妙な発言した政治家がいた。資料館の記述について「要するに日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆりの隊が死ぬことになった。そして米国が入ってきて沖縄が解放されたと、そういう文脈で書いている」と述べたのである。
ひめゆり学徒隊の悲劇は、沖縄戦史の中でも突出して有名だ。乙女たちの悲惨な運命を描いた小説『ひめゆりの塔』(講談社)が話題になったからである。著者の石野径一郎は沖縄出身だが、昭和4(1929年)年、大学進学のために上京しており、経験はしていない。この小説は証言を基に書かれたものである。
よく言われるように、沖縄戦は老若男女の島民全てを巻き込んだ唯一の地上戦である。4歳の子どもまでが伝令として戦場を駆け、戦死した。沖縄守備隊に先立って自決した大田実海軍中将が、東京の大本営へ送った最後の電報は有名だ。
「陸海軍部隊沖縄に進駐以来、終始一貫勤労奉仕物資節約を強要されたにもかかわらず」と、島民たちが犠牲になっている様子を述べた後、「沖縄県民かく戦えり。県民に対し後世特別の御高配を賜わらんことを」という言葉で締めくくった(原文は旧仮名遣いとカタカナで記載)
ひめゆり学徒隊の悲劇もその一部である。映画『ひめゆりの塔』は、ただただ悲惨な敗走の記録だ。米軍の上陸を目前にした昭和20年(1945年)3月、沖縄における女子教育の頂点に立っていた県立第一高等女学校と師範学校女子部は軍命により、ひめゆり学徒隊となった。
高等女学校はみな花の名前を冠した学徒隊となった。県立第二高女は白梅学徒隊である。ちなみに、県立一高と師範学校は鉄血勤王隊だった。その中には沖縄戦研究の第一人者で、後に県知事を二期務めた大田昌秀琉球大学名誉教授もいた(2017年没)。
ひめゆり学徒隊は病院壕で看護活動に従事する。沖縄戦で重要な役割を果たした壕は、石灰岩が雨垂れなどで長年にわたって穿たれた、天然の洞窟だ。実際に入ってみると、壕は荒々しく猛々しく、灯りがないと真性の暗闇で、普通の神経では耐えられない場所だ。沖縄の言葉でガマと言う。空襲を避けるのに最適だったので、司令部も野戦病院も島民の避難場所もガマだった。
米軍が上陸してガマも空襲で潰れていく中、ひめゆり学徒隊はその中で傷病兵の世話をする。食糧も物資も麻酔もない中、ひたすら日本軍の勝利を信じて奮闘した。
しかし、嘉手納北方の読谷村に上陸した米軍は、戦線を南北に分断した後、南進して首里防衛戦を突破する。ガマに設置された野戦病院は軍命で移動を繰り返した。その度に重症者は置き去りになり、学徒隊も減っていった。
やがて、司令部は首里を放棄して南端の摩文仁を目指す。避難中の島民も行動を共にして犠牲になった。戦局の最終段階で、ひめゆり学徒隊は解散と各自避難を命じられる。だが、もはや帰るべき家もなく家族の消息もわからない。女学生たちは手榴弾で次々に自決していく。
- 1
- 2