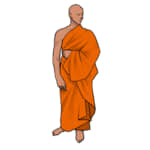日台合作で石原裕次郎主演の大作『金門島にかける橋』 戦争に翻弄される男女の悲劇【昭和の映画史】
■近代日本の闇を背負った「からゆきさん」とは?
日本人の多くは、台湾に対して好感を持っている。しかし、筆者も含めて多くの日本人は、実は台湾のことをよく知らないのではないか。
そこで筆者が入門書としてまず読んだのが、野嶋剛著『台湾とは何か』(ちくま新書)である。著者は香港中文大学、台湾師範大学、アモイ大学へ留学した経験を持つ。
新聞社入社後、シンガポールと台湾に駐在した東アジア通で、視野が広く叙述も客観的である。2016年の本だが、2023年には『台湾の本音「隣国」を基礎から理解する』(光文社新書)も上梓している。ご参考までに。
この映画『金門島にかける橋』は昭和37年(1962年)に製作された日台合作で、大規模な台湾ロケを敢行し、石原裕次郎が主演した大作だ。物語は裕次郎演じる船医の武井一郎が、3年前の出来事を回顧する場面から始まる。
武井は東京の病院で、朝鮮戦争の前線から送られてくる傷病兵の手当てをしていた。朝鮮戦争と言えば日本にとっては朝鮮特需だが、関わりはそれだけではなかった。2011年に公開されたスタジオジブリの『コクリコ坂から』では、ヒロインの女子高生が、船員だった父親の死因が朝鮮戦争だったことを知るのである。
話を戻すと、武井は病院で台湾から恋人を追ってきた女性、楊麗春に出会って強い印象を受ける。その後、武井は誤診で病院長と共に、政界の大物の手術に失敗してしまった。それを告白した武井は、どこの病院にも受け入れられずに船医になる道を選ぶ。
そして船で各国を回り、台湾の金門島に上陸する。その時、大陸から人民解放軍が砲撃してきた。その混乱のさなか、武井は楊麗春と再会するのである。二人はお互いの気持ちに気づくが、彼女は中華民国の建国記念日である双十節の日に、台湾軍の将校と結婚することになっていた。
武井は楊麗春の幸せのために身を引き、高尾行きの船に乗る。しかし、再び砲撃が始まって船は沈んでしまう。何とか友人の記者を助けて岸にたどり着くと、そこに武井を探して追ってきた楊麗春が現れる。二人は走り寄るが・・・・。
東西冷戦の真っ最中で、日中国交正常化に先立つこと10年前に制作されたというだけで注目に値する。まだ台湾と呼ばず中国と言っていた時代だ。アメリカ人や台湾人が、いきなり日本語で話し始めるような奇妙な点があるのは仕方なし。
今思うとあの時代だからこそ、武力衝突という難しい背景を描くことができたのではないだろうか。国共内戦に敗れて台湾に逃げ込み、金門島で暮らしている元国民党員と思しき長老が日本軍に対する恨みを口にするあたり、時代の刻印がある。
そして最後、武井が周囲で炸裂する砲弾に対して「やめろ、やめろ」と繰り返すところなどに、戦争が終わって20年も経っていない当時の、日本社会に満ちていた平和への強い思いがうかがえる。
石原裕次郎は言うまでもなく、戦後日本を代表する大スターだ。デビューさせたのは兄の慎太郎である。当時は兄弟で、『太陽の季節』そのままの無軌道な日々を送っていたという。それにしても石原兄弟は、どうしてあんなに人気があったのだろうか。
そこには時代背景と、戦後日本人の特殊な心情があったと思われる。まだ大学進学率が低かった時代、社会には戦前の身分制社会が残滓として残っており、庶民には上流階層への憧れがあった。
さらに、その背後にアメリカの威光があった。慶應大学を出た湘南のお坊ちゃんで、夏はサングラスをかけてヨットを楽しむ。アメリカ人のような、無軌道すれすれの自由奔放なキャラクターである。その在り方は庶民の憧れだったろう。
加えて、映画評論家の四方田犬彦が『日本映画史100年』(集英社新書)で、興味深い分析をしている。
それまで日本の男優は、大きくて目立つ顔を持つことが必要条件だった。しかし裕次郎は、顔よりも背の高さと足の長さによって人気を得たのである。その結果、彼を生かすショットはアップではなくロングになった。
また裕次郎は、戦後日本人が学び始めた個人主義の体現者であり、自己意識の塊だった。彼の「イカした」自己意識は、家族や国家といった共同体から切り離された者だけが持つ、ダンディズムと孤独感を感じさせたのである。秩序から外れているところが魅力だったのだ。
裕次郎は、軍服が似合わない戦後派の俳優代表となった。当時は戦争をテーマにした映画が盛んに作られていた。『真空地帯』『野火』『肉弾』『人間の条件』など、戦後日本の名作群として今も記憶されている作品群である。
それらには日本を代表する俳優たちが出演し、違和感なく軍服を着こなしていた。実際に戦地へ行ったベテラン俳優も多かったし、日本の男はみんな軍服が似合うと言われた。そんな中で、アメリカ人のように背が高く足が長い裕次郎は、異質の存在だったのである。
さて、2000年代の終わり頃から、台湾映画界はアイデンティティを掘り下げる自己認識の一環として、日本との関係を描く作品群を生み出した。その嚆矢となったのが、2008年に公開された魏徳聖(ウェイ・ダーション)監督の『海角7号 君想う、国境の南』である。
日本の敗戦によって、引き裂かれるように別れた台湾人男性と日本人女性の、60年の年月を超えた愛情を描く物語だった。低迷していた台湾映画界にあって、『タイタニック』に次ぐ歴代2位のヒットとなったのである。
この映画は台湾社会の一部から「日本に寄り過ぎている」と批判を受けた。しかし魏徳聖監督の意図は、台湾近代史の一部として日本との関わりを見つめることだったのだ。その意図は、次に作られた『セデック・バレ』二部作で明らかになる。
この二部作は、満州事変前年の昭和5年(1930年)に先住民族が日本に対して起こした武装蜂起、霧社事件を扱った大作だった。『海角7号』を観て「台湾はやはり親日国だ」と思った人は、『セデック・バレ』に驚いただろう。
日本統治時代は台湾近代史の一部である。魏徳聖監督に政治的意図はなく、台湾の歩むべき道を考える一環として、様々な角度から日本統治時代を振り返っていたのである。
しかし、日本で話題になる台湾映画はどうしても、台湾から引き揚げてきた体験を語る『湾生回家』(2015)のような、日本統治時代を懐かしむものになりがちだ。しかし、今や台湾は破竹の勢いで、韓国に続き日本を追い越そうとしている。
半導体で世界的シェアを握り、日産の買収にも意欲を見せ、熊本に工場を建てて地元がバブルに沸いている。教育費を削る一方の日本とは逆に、人材育成や教育にも熱心だ。
英語力でアジアをリードしようと、国民総バイリンガル計画も進めている。それはそれでまた、台湾のアイデンティティーを複雑にしそうだが。とはいえ、もはや昔の台湾ではない。日本人は今、台湾への見方を変える時に来ているのではないか。

台湾・金門島からみた厦門。