出稼ぎ売春が大々的に行われていた近代日本の裏面史 “からゆきさん”の壮絶な半生を描いた『サンダカン八番娼館 望郷』【昭和の映画史】
■近代日本の闇を背負った「からゆきさん」とは?
昨今は驚くようなニュースが多い。中でも筆者が最も驚いたものの一つが、日本女性が海外で出稼ぎ売春をしているという話である。最初は「まさか!」と思い、信じられなかったが本当だった。そのため、ニューヨークの空港で若い日本女性が一人で入国しようとすると、止められて詳しく調べられるという。
出稼ぎ売春の多くは、ホストに借金をして返せなくなった女性だそうだ。借金を売春で返す。あるいは、貧困から脱出するために売春をする。そしてネットには、それを仲介する人間や組織が存在する。
ホストは男性慣れしていない真面目な女性や、都会に出てきたばかりの大学生を狙う。また、都会で一人暮らしをする若年独身女性の手取りは少なく、夜も仕事をせざるを得ないこともある。
時代が変わってもIT技術が発達しても、女性を売春の沼に落とす仕組みはなくならない。コロナ禍では有名お笑いタレントが「もう少し待てば、きれいなお姉さんが来ます」と言って物議を醸した。生活に困った美人が、風俗の世界に入ってくるという意味だった。
この映画『サンダカン八番娼館 望郷』(昭和49年/1974年)は、貧しさが売春に直結する構図によって、出稼ぎ売春が大々的に行われていた近代日本の裏面史を描いたものだ。女性史家の山崎朋子が昭和47年(1972年)に現した著作、『サンダカン八番娼館 底辺女性史序章』の映画化である。
この本は驚きをもって読まれ、ベストセラーになった。日本人はもはや、からゆきさんの存在を知らなかった。高度成長を経た日本人にとって、貧しさから海を渡って売春をした女性たちがいたなんて、信じられなかったのである。
もともと「からゆき」とは「唐行」から来た言葉だと言われている。江戸時代の長崎で、唐人屋敷へ行く遊女のことを指したという。
すでにこの頃から日本女性は東南アジアに出稼ぎに行っており、明治維新後はその数が激増した。20世紀初めのインドシナでは、在住日本人の多くがからゆきさんだった。
ロシアなどの北方に行った女性たちもいる。倉橋正直著『北のからゆきさん』には、日本女性の評判を聞いて高名な小説家までやってきたという記述がある。彼女たちは襟のところに懐紙を忍ばせており、その使い方が魅力的だということで懐紙がブームになったそうだ。
この映画は改革開放直後の中国で、性的な場面を削除して上映され、圧倒的な人気を得た。当時の成人で、この映画を観なかった中国人はいない。著者役を演じたのは、当時コマキストと呼ばれるファンを持っていた栗原小巻で、中国でも大人気となった。
からゆきさんだった過去を語るサキを演じるのは、戦前からの大スター田中絹代である。庶民的な風貌で清純な若妻や戦争未亡人を演じ、戦後は老け役や汚れ役にも挑戦して新境地を開いた。この映画は晩年の代表作である。
栗原演じる三谷圭子は底辺の女性史を研究しており、旅行中の天草で偶然、おサキさんという高齢女性に出会う。三谷はサキが、元からゆきさんではないかと直感し、その体験を聞きたくて泊めてもらうことにする。
初めは話をはぐらしていたサキだが、やがてある出来事をきっかけに過去を語り始める。サキは父親を4歳で亡くした。家は困窮して、母親は生活のために亡夫の兄と結婚する。やがて12歳になったサキは、娼館で働く女性を探しに来た男に勧められ、外国行きを決意する。
高額の手当をもらえて、ご飯もお腹いっぱいに食べられると騙されたのだ。サキは前金としてもらった300円を兄に送り、人手に渡った畑を買い戻すよう伝えた。そして村の娘数人と密航船に乗った。
着いたのはイギリス領ボルネオ、現インドネシアのサンダカンである。そこにはすでに日本人が経営する娼館が、一番館から九番館まであった。サキは八番館に入る。そして13歳になると客を取るように言われる。すでに借金は2000円に膨らんでいた。
サンダカンはボルネオ最大の港町だ。日本人のみならず、地元民や様々な国の人間が娼館を利用する。寄港する各国艦船の船員や水兵もやってくる。中でも一番賑わうのは、日本の軍艦が寄港する時だ。
その時の描写がすごい。兵隊たちは軍歌を歌いながら、整然と娼館に向かって行進してくる。だが到着したとたん、怒涛のように館内になだれ込むのだ。
筆者は10年ほど前、大学で非常勤講師をしていて、授業でこの場面を見せたことがある。その時、教室には学生たちのどよめきが起き、「信じられない」という声が飛び交った。そうだろう。
筆者も初めて観た時は驚いた。こういう私的な行為を集団で、しかも公認の場で行うなどということは、今では考えられない。吉原のような公認遊郭があったからこそだろう。そして日本人は娼館と共にアジアに出ていった。
日本社会には構造的に娼館が組み込まれており、日本人が往くところ必ず娼館ができた。娼館は、なくてはならない存在だったのである。民間業者が手がけるビジネスだったが、当然、日本軍とも持ちつ持たれつの関係にあった。
女性たちは、しばしば転売されてもっと遠方に行かされた。サキたちの八番娼館でも経営者が替わり、4人がプノンペンに移動しなくてはならなくなった。誰も行きたがらないので、くじ引きになる。外れた4人は泣き叫びながら連れて行かれた。
やがて経営者が元娼婦のキクに替わって、サキの生活は楽になった。しかし、そのキクも死去する。そこで現地に葬って帰国したものの、兄は外聞をはばかってサキを避けた。居場所がないサキは満州に渡って結婚するが、夫は戦死してしまう。
敗戦により、サキは帰国して夫の故郷で暮らす。だが息子が成人すると用なしとなり、天草に帰された。そして独り、ひっそりと暮らしていたのである。それでもサキは帰国できて、結婚もできた。しかし、からゆきさんの多くは帰国できなかったのだ。3年後、サキたちの足跡を辿るため、三谷が訪れたサンダカンで見たものは・・・
この映画はアカデミー賞外国語映画賞の候補になり、田中絹代はサキ役で、ベルリン国際映画祭銀熊賞(最優秀女優賞)を獲得した。田中は出演した『西鶴一代女』『雨月物語』『山椒大夫』が3年連続ベネツィア国際映画祭で、作品として国際賞と銀獅子賞を受賞している。
そして歯を抜いてまで熱演し、晩年になって遂に最優秀女優賞を得たことは、戦争を挟んだ長い女優人生を締めくくるにふさわしい慶事だったのではなかろうか。この3年後、田中は67歳で旅立った。
監督の熊井啓は、日本を代表する社会派監督の一人で、敗戦後の怪事件を扱った『帝銀事件 死刑囚』や『謀殺 下山事件』、松本サリン事件をテーマにした『日本の黒い夏 冤罪』などを制作している。
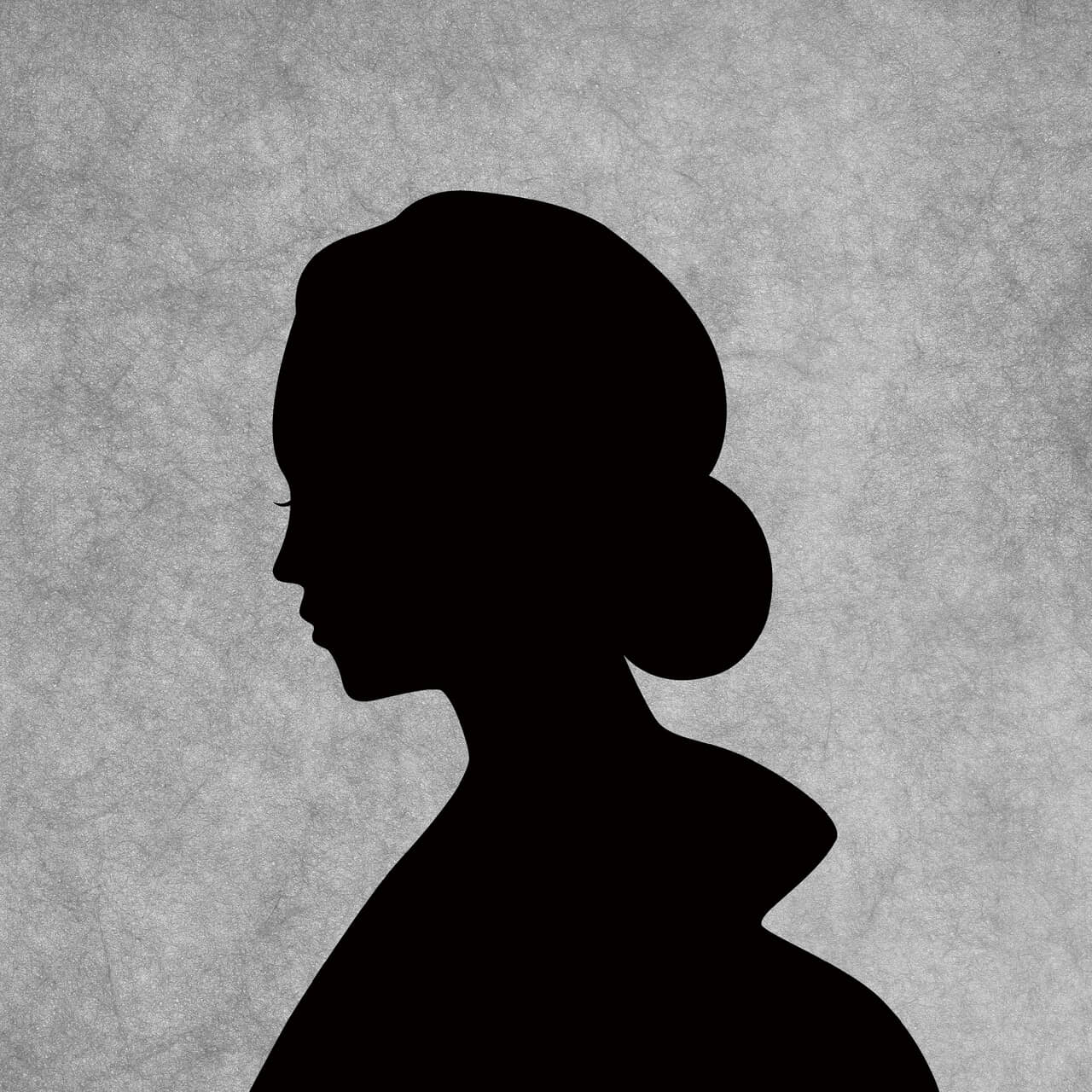
イメージ/イラストAC






