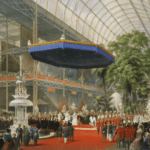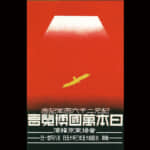1970年大阪万博は何をもたらしたのか? 半世紀後の大阪・関西万博が抱える費用対効果と環境問題
2025年4月13日、いよいよ大阪万博が開幕となった。数々の問題を抱えながらこの日に開会に漕ぎつけた関係者の労を労いたいし、開会したからには盛況、かつ無事に終幕することを祈りたい。日本の万博との関わりは敗戦後、かなり時間が経過してからだった。1958年高松宮宣仁親王夫妻はフランス、ベルギーを訪問した。このときブリュッセルでは戦後初の博覧会が開かれていた。これが皇族の最初の海外万博訪問だった。日本は「日本の手と機械」とのテーマで、伝統工芸品や電子顕微鏡など最新の機械製品を展示している。また日本館は建築家前川國男により建設されグランプリを獲得している。この成果は日本で大きく報道され、その後日本国内で万博招聘の声が高まっていくことになる。
1964年東京オリンピック開催で自信をつけた日本は1965年に国際博覧会条約に加盟、さらに1970年の大阪万博開催は高度成長時代を象徴するような日本の存在感を世界に示す絶好の機会だった。日本のアピールは「わが国の立場、その歴史的伝統、地理的環境、さらに日本の文化的特色」を生かすこと、これが万博への命題で次なる目標が文化と産業の祭典であり「人類の進歩と調和」がテーマになるのは自然の流れだったかもしれない。
万博準備委員会は、各国に参加招請状を送付後、幹事が手分けして数十か国を訪問、各国王室・政府や国際機関の首脳への根回し、さらに開発途上国にはパビリオン建設のサポートなど東京オリンピックと同様に惜しみない支援をおこなっていた。まさにオールジャパンの体制である。特に日本のアジア諸国へのアプローチは積極的だった。この結果、発展途上だったアジア諸国からは初参加が25ヶ国に増加した。それはアジア初の万博開催意欲への日本のイニシアチブの表れでもあった。オリンピックといい、万博といい、途上国の参加を資金などで補助した日本の根回しは、帝国主義時代の万博のあり方を脱却し、その後の政府開発援助(ODA)などと合わせて、アジア・アフリカ諸国との友好関係を結ぶ今日の日本外交の礎をつくる役割を果たしたといっても過言ではない。
さて大阪万博では、日本の高度経済成長を表すような成果、なかでも動く歩道、モノレール、リニアモーターカー、電気自動車、携帯電話、缶コーヒーなど今や日常に使用する製品が展示された。さらに岡本太郎の太陽の塔、アメリカ館の「月の石」など評判を呼ぶものも展示された。その結果、70ヶ国や多くの国際機関が参加、入場者6400万人と大盛況となった万博だった。
同万博の産物はこれだけではなかった。もう一つ注目したいのは、各国から元首クラスや要人が数多く来日していることだ。特に元首、王族などの来日は答礼というスケジュールが生じる。皇居での晩餐会、茶会などは皇室の国際親善の道を深化させることになった。おりしもベルギー国王の弟のアルベール公が来日したとき、皇室との接触で昭和天皇訪欧要請の親書がベルギー王室よりあり、1971年の天皇初外遊の糸口が開かれていくことになる。
ところで、2025年の大阪万博はこのオールジャパン体制の意義はかなり薄味になっている。それはコロナ禍で開催された東京オリンピックを巡りいくつかの企業スポンサーとの癒着が露見、大規模プロジェクトに対する不信感が高まったことと無関係ではない。また3万㎥弱の世界最大の木造建築が売りだが、閉会後の再利用は四分一という話も環境問題を考える意味で軽視できない。今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」という高尚なテーマを掲げ企業にはPRするいい機会でもあるが、大規模プロジェクトのスタイルについて環境、費用対効果を真剣に再考する時期にきていると思われる。

1970年大阪万博の会場。中央に太陽の塔がある。