大河ドラマ『べらぼう』田安賢丸の養子入りが大問題なのはなぜ? 徳川将軍家の血筋を繋ぐ「御三家」と「御三卿」とは
大河ドラマ『べらぼう』3話では、御三卿の生まれである田安賢丸(演:寺田 心)が白河藩に養子入りすることが決まった。これに対して宝蓮院(演:花總まり)が怒りを露わにしていたが、なぜ賢丸の養子入りが問題なのか、そもそも「御三家」や「御三卿」とは何かを解説する。
■将軍の位を安定して繋いでいくための“保険”
「御三家」とは、初代将軍・家康の男子をそれぞれ始祖とする家のなかでも将軍家に次ぐ家格を持ち、「徳川」を名乗ることや三つ葉葵の家紋を許された家である。家康の9男・義直を祖とする尾張家、10男・頼宣を祖とする紀伊(紀州)家、11男・頼房を祖とする水戸家は、他の大名家や御家門とは別格の待遇を受けていた。
後に「御三家」と称されるようになるが、揃って成立したというよりは、家康の死後に徐々に形成されていったといえる。最終的に御三家の格式が定まって将軍家を支えていく名家としての役割を発揮するのは、5代将軍・綱吉の時代頃からとされている。
一方「御三卿」とは、8代将軍・吉宗が安定的な将軍位継承のために独自に創設したものだ。吉宗の次男・宗武を祖とする田安家、4男・宗尹を祖とする一橋家、そして父の意を汲んだ9代将軍・家重の次男・重好を祖とする清水家である。
御三卿は大名として藩を持つことはなく、江戸城内に与えられた屋敷で暮らした。そして将軍家や御三家の後継者がいないときに、適当な者が選出されている。御三卿の家から将軍になったのは11代将軍・家斉と15代将軍・慶喜で、いずれも一橋家だった(慶喜は御三家の水戸家から一橋家に養子に入っている)。ちなみに、明治維新後に徳川宗家を継いだ家達は田安家の出身である。
御三家のひとつである紀伊家出身の吉宗が、既に御三家があるにも関わらず、それに準ずる家を創設させた理由としては、将軍家と御三家の折り合いが悪かった、あくまで自分の血筋で将軍家を繋いでいきたかったなど、諸説ある。
■田安家が激怒した賢丸の養子入り問題
さて、『べらぼう』では、田安賢丸の養子入りが問題になっていた。この背景を簡単に整理しよう。
賢丸の父であり田安家の祖である徳川宗武は、吉宗の次男として誕生。長男の家重が生来虚弱だった上、障がいによって言語が不明瞭だったことなどから、文武に長けており聡明な次男の宗武を次期将軍にという声も多かった。老中・松平乗邑が宗武を推していたこともあり、吉宗も一時はそれを考えたという。
しかし、当時の考え方では家督相続に能力は関係なく、血筋が優先され、長幼の序が重んじられていた。もし、嫡子を廃し、次男や三男を継嗣に立てると悪例とされ、天下の人心に大きな影響を与えると考えられていたのである。結局吉宗は家重に将軍を継がせることにした。
この次期将軍争いは、宗武が田安徳川家を創設し、家重が9代将軍に就任した後も尾を引いた。家重は宗武に対して3年間の登城禁止処分を言い渡し、その後も生涯対面することはなかったという。
やがてそれぞれの子、10代将軍・家治と田安家2代目当主・治察の時代になる。ちょうど『べらぼう』の時間軸だ。田安家としては、治察が病弱で妻子もいなかったことから、ゆくゆくは聡明な賢丸に当主を継がせることも視野に入れていた。
さらに、家治が愛妻家で側室を多くもちたがらず、男子は家基のみという状況だったことから、家基にもしものことがあれば、賢丸が時期将軍候補になることを期待していたと考えられている。田安家にとっては、宗武が果たせなかった将軍位継承は悲願だった。
そんな状況で決まったのが、賢丸の白河藩への養子入りだ。御三卿の家から出てしまえば、賢丸の将軍への道は完全に閉ざされる。宗武の正室である宝蓮院(演:花總まり)が激怒していたのも、「またもや田安家を将軍位から遠ざけるのか」という亡き夫の無念を知るがゆえの怒りだったのだ。ちなみに賢丸は側室の子なので、宝蓮院は養母にあたる。
白河藩が御三卿から養子を迎えることで家格を上げようとした、一橋家がライバル排除のために手を回したなど様々な説があるが、いずれにしても賢丸の養子入りが決まったのは田沼意次の暗躍があったのだと考えられるようになった。
後に松平定信となった賢丸が残した自叙伝『宇下人言』には、兄の治察が死の間際に語ったこととして、「母の宝蓮院が御側御用取次の稲葉正明から賢丸が田安家を相続する話を取り付けていたが、後に田沼意次らが約束を破った」と記されている。
第3話で描かれた幕府サイドの一連の描写には、将軍位を巡る水面下のバトルが秘められていたのである。

イメージ/イラストAC
<参考>
安藤優一郎『江戸文化から見る 男娼と男色の歴史』(カンゼン)




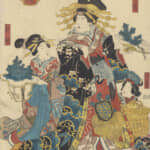
photoAC-150x150.jpg)
