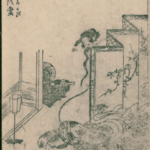美人画に革命を起こした喜多川歌麿の「大首絵」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉝
10月19日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第40回「尽きせぬは欲の泉」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)と距離を置いていた喜多川歌麿(きたがわうたまろ/染谷将太)が、再び手を組む様子が描かれた。一方、幕府の締め付けに音を上げた山東京伝(さんとうきょうでん/古川雄大)もまた、戯作の世界に戻ることを決意するのだった。
■蔦重と喜多川歌麿が再び手を組む

喜多川歌麿が玩具「ポッピン」を吹く女性を描いた大首絵。様々なタイプの女性を書き分けた揃物の一作。東京国立博物館蔵/Colbase
幕府内では、松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)の厳しすぎる使約令に反発が起こり始めていた。定信は取りやめを求める本多忠籌(ほんだただかず/矢島健一)らの進言を退け、自らの政策に賛同する者のみを周囲に配置することで、独裁体制を強化していった。
経営が安定しない蔦重は、他店の黄表紙の板木を安く買って再印本を売る計画を立て、鶴屋から山東京伝の板木を譲り受けることになった。
その条件として、京伝の妻・菊(望海風斗)から滝沢瑣吉(たきざわさきち/津田健次郎)という変わり者の男を紹介される。蔦重は瑣吉を店で働かせながら黄表紙を書かせ、挿絵は勝川春朗(かつかわしゅんろう/くっきー!)に任せることを思いついた。二人はすぐに喧嘩を始めたが、蔦重は競い合うことで良作が生まれると確信する。瑣吉は後の曲亭馬琴(きょくていばきん)、春朗は後の葛飾北斎(かつしかほくさい)である。
定信の政策により出版界は停滞していた。自身の政策の成果であるにもかかわらず、定信は浮かない表情を見せる。
一方、蔦重は喜多川歌麿に女の大首絵を描かせることで打開しようと考えた。当時流行していた相学になぞらえ、様々な「相」の女性を描いた錦絵のシリーズを企画したのである。
亡き妻きよへの想いから女を描くことを拒む歌麿を、蔦重は熱意で説得する。こうして歌麿は江戸に戻り、蔦重の難しい注文に応えながら大首絵を描き始めた。
一方、戯作から身を引くことを真剣に考えていた京伝は、煙草入れ屋の開業資金を募るべく、書画会を開く。そこでの歓迎ぶりに感激した京伝は引退を撤回。戯作者と煙草入れ屋との兼業を決めたのだった。
- 1
- 2