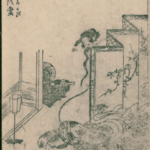「更生」から「懲役」の場へ変質していった「人足寄場」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉜
10月5日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第38回「地本問屋仲間事之始」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)の強気の姿勢が江戸の出版界を窮地に招く過程が描かれた。逆風のなか、蔦重はある奇策をもって幕府に抵抗しようと版元らに提案する。
■江戸の出版関係者が一丸となる

府中刑務所(東京都府中市)。人足寄場には収容者の心の慰めとして稲荷神社が建立されていた。人足寄場は石川島監獄署、巣鴨監獄、府中刑務所と移転。その役割と制度が引き継がれていったが、この稲荷神社も同様に移され、現在の府中刑務所にも祀られている。
黄表紙『心學早染艸』の執筆を機に、版元である蔦重と絵師の北尾政演(きたおまさのぶ/古川雄大)は互いの信念の違いから絶縁状態となった。見かねた鶴屋喜右衛門(つるやきえもん/風間俊介)が二人の仲を取り持とうとするが、不調に終わる。
その頃、市中では松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)の強いる厳しい倹約の世に耐えかねた荒くれ者たちが暴れまわり、治安の悪化が深刻化していた。定信はこれを受け、不逞の輩を集めて更生させる施設である人足寄場(にんそくよせば)の整備を長谷川平蔵宣以(はせがわへいぞうのぶため/中村隼人)に命じた上、社会を乱す元と見なす黄表紙を世から一掃すべく、出版統制に乗り出した。
事態の打開を図るため、鶴屋は蔦重とともに江戸中の出版関係者を呼び集めた。奉行所からのお触れによれば、出版統制に至ったのは蔦重の出版物がきっかけとあっただけに、蔦重に対して出版関係者から怒号が飛び交う。蔦重は江戸中の全ての草稿を届け出て、奉行所の手を塞ぎ、業務を滞らせてしまうという奇策を提案する。
猛反発する関係者のなかで、北尾重政(きたおしげまさ/橋本淳)をはじめとする一部の絵師たちが蔦重に協力すべく立ち上がった。その様を見て、出版関係者一同は一丸となり、大量の草稿を届け出て、奉行所に悲鳴をあげさせることに成功した。この騒動のなか、ついに蔦重と政演は和解した。
一方、妻のきよ(藤間爽子)が重い病にかかった喜多川歌麿(きたがわうたまろ/染谷将太)は、懸命に看病を続けていた。しかし、それもむなしく、きよは病死。歌麿はきよの死を受け入れず、その亡骸をひたすら描き続けていた。現実に向き合わせようとする蔦重を思わず殴り飛ばし、歌麿は亡き妻への想いとともに大声で泣きはらすのだった。
- 1
- 2