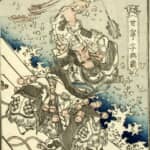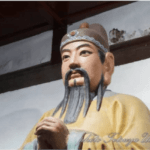三国志における最強の軍略家「曹操」が赤壁以上の“命の危機”に直面!? 馬超に大苦戦した潼関の戦いとは?
ここからはじめる! 三国志入門 第124回

潼関の戦い(211年)の頃の勢力図
■勝率8割以上を誇る曹操が、危うく足をとられそうに
三国志において、最強の軍略家・兵法家は誰か。さまざまな論はあろうが、曹操の名前を挙げるひとも多いのではないだろうか? 彼は生涯で40戦以上の戦いに臨んだが、勝率はじつに9割近くに達するといわれる(勝敗・戦績には諸説あり)。
ゆえに曹操の敗北はインパクトがある。ほとんど負けていないにもかかわらず、敗戦のときは大敗が目立つためか、その派手な負けっぷりも特徴といえるほどだ。
ざっくりいうと、彼の「大きな負け」は4回ある。旗揚げ間もない190年、董卓軍・徐栄(じょえい)との戦いで兵力差のハンデから惨敗。197年、張繡(ちょうしゅう)に奇襲され命からがら逃げた。長男の曹昂(そうこう)、ガードマンの典韋(てんい)が戦死するほどの手痛い敗戦だった。
そして3敗目が208年の赤壁。説明はいらないだろう。もうひとつが219年の漢中の戦いで、蜀から北上してきた劉備軍と戦うも、腹心の夏侯淵を倒され漢中を奪われた。これらは相当な打撃で、曹操の中華統一の野望が阻まれた要因でもある。
細かいところでは、濮陽(ぼくよう)で呂布に討たれそうになったことなどもあり、戦場で何度も命を落としかけている。よくぞ死なずに生き延びたといえるほどで、その悪運の強さも英雄の条件といえよう。
ここで紹介する「潼関(どうかん)の戦い」も、またそのひとつである。先の赤壁の戦いから2年あまり経った211年、曹操は西へと兵を向けた。

隘路に位置する潼関。真正面から攻めるには不利だ
■赤壁敗戦の汚名、その払拭も兼ねた潼関遠征
戦いの名目としては張魯(ちょうろ)討伐のためだったが、実際には関西地方(長安周辺、関中と呼ばれる一帯)に兵を置いて守りを固め、馬超・韓遂(かんすい)らを威圧し、配下に取り込もうとしたのだ。馬超らは孫権との同盟が噂されるなど、常に曹操の背後をおびやかす状態にもあった。
曹操が兵を向けると、馬超・韓遂は危機感を抱き、ついに牙をむく。そして先手必勝とばかり、楊秋・李堪・成宜ら西方の十軍閥を糾合して兵を挙げ、潼関方面へ進軍した。その数10万。いわば「馬超の乱」である。
馬超らは、なにも洛陽を攻め落とそうとしたわけではない。望みは関中・隴右(ろうゆう)といった自分たちの土地の支配権を訴えるためであったが、中原の覇者を自負する曹操はこれを野放しにはできなかった。
同年7月、両軍は対峙。曹操が慎重な姿勢をとったのは、涼州の精強な軽装騎兵、長い矛(ほこ)を持つ歩兵隊を警戒していたためだ。しかも馬超たちが布陣する潼関は堅牢な城塞。山と河に挟まれ、まっすぐにしか攻め込めない。局面打開には、黄河を超え、潼関の北側や西側へ進出をはかるしかなかった。
ひと月あまり対陣ののち、曹操は先遣隊を北へやって渡河させると、みずからは殿軍(しんがり)となり、100名ほどの親衛隊とともに河を渡りにかかった。そこへ襲来したのが馬超軍である。馬超は曹操本隊を叩くタイミングを狙っていたのだ。その数1万。先遣隊と分断され、曹操は敵中に孤立し、絶体絶命となった。
次編に続く