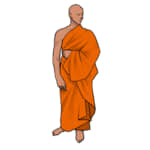戦友の“遺書配達人”が見た生々しい戦争の傷跡 戦争に人生を狂わされた人々を描く『あゝ声なき友』【昭和の映画史】
■昭和の知られざる名作
昭和47年(1972年)に公開された『あゝ声なき友』は知られざる名作だ。渥美清が映画化を切望し、そのためにプロダクションまで設立して情熱を注いだ作品である。監督に社会派の巨匠・今井正を迎えて、自ら主演した。
にもかかわらず、興行的には成功したとは言いがたく、昭和の名作リストからも微妙に外れている。その理由は皮肉なことに、渥美清が主役を演じたからである。
昭和44年(1969年)に始まった『男はつらいよ』シリーズは、すでに8作を数え、渥美清は喜劇俳優として国民的人気を博していた。その渥美が真面目な物語で真面目な役を演じるということが、社会に受け入れられなかったのである。もし他の俳優が演じていたら、ヒットしていたかもしれない。
しかし、プロダクションを設立するほど原作に入れ込んだ渥美としては、是非とも自分で演じたかったのだろう。実際、この主人公には渥美清だからこその味が出ている。原作は有馬頼義(ありまよりちか)の『遺書配達人』である。
有馬頼義は旧久留米藩藩主・有馬家の16代目当主。祖母は岩倉具視の五女である。二・二六事件の時は姉の嫁ぎ先に泊まっていて、隣に住んでいた舅にあたる斎藤内大臣が殺害されるという経験をした。
旧制・早稲田第一高等学院在学中、小説を書いて報酬を得たために退学となり、入隊して満州へ渡る。本来なら幹部候補生の資格を得られたのを放棄して、初年兵として入隊した。そこで理不尽な暴力を受ける。
終戦後は大臣だった父が戦犯容疑者となり、家は傾いて次兄も死去。有馬は職を転々として生活した。だが昭和29年(1954年)、何とか工面した資金で自費出版した小説が認められ、直木賞を受賞、小説家として歩み始めた。
有馬の代表作は何と言っても『貴三郎一代』だろう。と言っても、そんな小説あったのかというぐらいの知名度だが、これこそ勝新太郎主演で一世を風靡した映画『兵隊やくざ』シリーズの原作である。
このシリーズは全く凄まじい内容で、昭和40年代(1960年代後半以降)にはこういう映画がヒットしていたのかと驚く。まだ軍隊生活で、理不尽な暴力を受けた世代が現役だった時代だ。みずからの体験を重ねつつ、爽快なラストに喝采を叫んだのではないか。
勝新演じる主人公の大宮はやくざの用心棒で、ソ連との国境に近い満州の奥地に送られてくる。指導係に決まったのは、田村高廣演じる上等兵の有田だ。有田は名家の出身で大学出のインテリである。原作者の有馬と名前まで似ている。
だが早く帰国することを目標に、あえて幹部候補生試験に不合格になっていた。朝ドラ『あんぱん』に出てきて、軍隊時代の柳井嵩を助ける八木上等兵が、これとよく似た設定である。
我が道を征こうとする大宮は当然、階級が上の下士官たちに睨まれる。それに反発するから、殴ったり殴られたり集団暴行を受けたり、罰として営倉に入れられたりという惨憺たる日々を送るのである。
やがて戦況は悪化し、部隊は南方に移動することになった。早期に帰国したいという有田の今後は、絶望的になる。そこで大宮は脱走計画を立てて有田を誘い、中国人の服を入手した。そして、乗り込んだ軍用列車から機関車を切り離す。二人を乗せた機関車だけが、満州の広野を走り抜けていくのだった。
原作者の、満州における軍隊体験が深く刻まれた物語だ。映画で、有田は大宮の破天荒な生き方に次第に惹かれ、アウトローとしての仲間意識を持つ。有田の抱える屈折と大宮の奔放さの双方に、有馬の過酷な軍隊体験と、そこで自分を貫けなかった忸怩たる思いを投影させたのだろう。
そんな有馬が昭和34年(1959年)に連載し、翌年に出版したのが原作の『遺書配達人』だ。60年安保の年で、日中戦争が生んだ国民的作家・火野葦平はこの年に自死している。
- 1
- 2