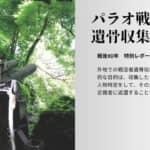乗員が太平洋戦争緒戦での大勝利の陰の立役者“九軍神”として祀られた大日本帝国海軍の特殊潜航艇「甲標的」とは⁉
太平洋戦争後80年の記憶
太平洋戦争中、大日本帝国軍はさまざまな艦艇をつくり、戦況に大きな影響を与えた。ここでは、特殊潜航艇「甲標的」の誕生と初陣、そしてどのような戦いをなしたのかについて紹介する。
第一次大戦後、航空機がまだ未発達だった当時の政戦略戦力たる海軍軍備を世界的に制限するため、ワシントンとロンドンの両海軍軍縮条約が締結された。その結果、主力艦(戦艦)の保有隻数は、アメリカ5、イギリス5に対して日本は3と劣位となった。
当時、日本海軍はアメリカを仮想敵国と想定。アジアにおけるアメリカ関連地域を日本が占領した場合、その奪還と、日本との決戦に向けてアメリカの大艦隊が太平洋を西進して来るのを、条約で制限がかけられていない補助艦艇や航空機を用いて途中で攻撃し、アメリカの戦艦の隻数を減らしてから艦隊決戦をおこなって勝敗を決めるという「漸減邀撃(ぜんげんようげき)」を対アメリカ戦略の主軸とした。
このような流れのなかで、日本海軍は技術的対象として小型潜航艇の研究に着手したが、これに「漸減邀撃」が関連して、アメリカ艦隊の進路上に展開した潜航艇母艦から複数の小型潜航艇が発進し、各挺それぞれが断続的に攻撃を仕掛けて、その漸減を実施するというプランが考えられた。こうして誕生したのが、特殊潜航艇「甲標的(こうひょうてき)」である。
「甲標的」は乗員2名で魚雷2本を搭載。小型なので航続距離が短いため、既述のごとく戦闘海域の近くで母艦から複数が発進し、敵艦隊を攻撃する運用が考えられた。そのため、広大な外洋での作戦行動を意識した設計で、直進性能が重視されている反面、小回りは苦手だった。また、波が高い外洋では、丈の低い「甲標的」の潜望鏡で敵艦隊を見つけるような周辺視察は容易ではなかった。さらに、小さな艇体の浮力に比して魚雷2本が重いので、魚雷を発射すると艇の姿勢が一瞬悪化することも起こり得た。おまけに正確な航法支援機器もない時代に、母艦から発進こそできても、広大な外洋でまた母艦に戻るのは相当に難しい。
これらの事柄を考慮した結果、太平洋戦争開戦を間近に控えた1941年9月、外洋で戦うのではなく、「甲標的」で港湾を襲撃するという案が考えられた。しかし、広大な外洋での雷撃を想定して開発された「甲標的」は、小さい割に速度はそこそこながら旋回径が大きく、しかも後進機能を備えていなかった(開戦後しばらくして解決)。つまり小回りが利かないので、入り組んだ狭隘(きょうあい)な港湾への侵入には、実のところ不向きであった。
かような報告を受けた山本五十六連合艦隊司令長官は、この港湾襲撃案が死を前提とする「必死作戦」ではなく、生還を前提とした「決死作戦」であることを何度も確認し念を押したうえで、やがて実施される真珠湾攻撃への「甲標的」の参加を認めた。
かくして1941年12月8日の空母艦上機による真珠湾攻撃と足並みを揃えて、第1次特別攻撃隊の「甲標的」5艇が、それぞれ伊号潜水艦5隻に積載されてハワイ・オアフ島沖まで運ばれ、そこで発進して同湾への潜入を試みた。気を付けたいのは「特別攻撃」の言葉である。太平洋戦争末期になると、この言葉は「必死」と同義となってしまうが、開戦当初は文字通りの「特別」な「攻撃」であり、「必死」の「攻撃」ではなかった。
結局、出撃した5艇中の1艇は海岸に漂着。残る4艇のなかには真珠湾内に潜入し雷撃を敢行した艇もあったが、その戦果は諸説あり、現在に至るも判然としていない。そして5挺すべてが未帰還となった。そのため戦死した乗員は、太平洋戦争緒戦での大勝利の陰の立役者「九軍神」として祀られた。
ところで、1艇当たりの乗員が2名なのにもかかわらずなぜ「九軍神」かというと、漂着した1艇の艇長酒巻和男少尉がアメリカ軍の捕虜となり生存していたので除外されたためで、この事実は中立国スウェーデン経由で日本に伝えられた。酒巻少尉は、太平洋戦争における日本人捕虜の第1号であった。

ハワイ諸島オアフ島東岸、ベローズ陸軍航空基地にほど近いワイマナロ・ビーチに漂着した酒巻艇。酒巻少尉と稲垣2曹は航行不能となった同艇から脱出したものの、後者は溺死してしまった。
なお「九軍神」の氏名は次の通り。戦死後、全員が2階級特進となった。ここに記したのは特進前の階級である。
艇長・横山正治大尉と艇付・上田定2曹、艇長・吉野繁實中尉と艇付・横山薫範1曹、艇長・廣尾彰少尉と艇付・片山義雄2曹、艇長・岩佐直治大尉と艇付・佐々木直吉1曹、酒巻艇の艇付・稲垣清2曹。
真珠湾攻撃に参加後、「甲標的」は何度かの作戦に投入され、見事に戦果をあげたケースもあった。