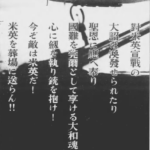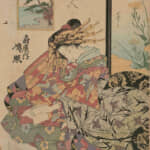「子を殺すか、売るか」という非情な選択を迫られ… 満州で「大陸の花嫁」となった女性たちの“終わらない戦争”
■「大陸の花嫁」が語った残酷すぎる実態
昭和7年(1932年)、関東軍は中国東北部にあたる満州を軍事制圧し、そこに清朝最後の皇帝・溥儀を形だけのトップに据えた「満州国」を打ち立てました。溥儀の弟にあたる溥傑は、明治天皇の生母・中山慶子の姪にあたる嵯峨浩と結婚していました。こういう事実もあって、満州と日本は海を隔ててつながった大日本帝国の一部という“幻想”が当時の日本人を支配していたのです。実際、満州移民の男性たちの妻となるべく、当地に渡った「大陸の花嫁」の多くには、外国に移民するという意識は希薄でした。
中国東北部にあたる満州は、夏は30度を超える暑さ、冬は極寒の厳しい自然で有名な土地柄なのですが、軍部に買収された新聞・雑誌各社は、「満州には肥沃な大地が広がっており、やる気のある者ならそこで大成功できる」と声を合わせて謳いあげました。
関東軍の理想は、中国大陸を占領していく軍隊の背後を大量の農民たちが付いて回ること。そして軍隊が占領した土地をすぐさま開墾して農地に、そして日本の一部に変えていくことだったのです。
しかし、「五族協和(日本人、漢民族、朝鮮人、蒙古人、満州人が協力し合う)」の理想社会と謳われたはずの満州の現実は、ごく一部の日本人が他民族を迫害する地獄のような社会でした。満州への移民は昭和7年から始まっていましたが、当初は軍隊経験者の男性が大半で、「武装移民団」とさえ呼ばれていたのです。
「開拓団」という触れ込みでしたが、彼らに用意されていた住む家や暮らす村は、満州に暮らしていた人々の土地や建物を剥奪したもの。当然、不満な現地人との流血沙汰は日常茶飯でした。おまけに満州の厳しい気候条件での農作は、開拓団内にいくら農村出身者が多いとはいえ、日本とは事情が違って困難でした。豊かな生活どころか日々の食物にすら困る日々が待っていたのです。
するとすぐに失われていくのがモラルです。戦勝国は、敗戦国の土地と人々を意のままにできるという傲慢で危険な発想が、当時の日本人には浸透していました。
「大陸の花嫁」として満州の村で暮らした根津マツさんによると、「私の部落では満人(=満州に暮らす中国人)が草刈っておいたのをとってきたり、秋になると満人の小麦だの何だの盗んで馬車でもってきたりした人いたの」。
「冬になると(略)蒙古に近いから蒙古人が炭売りに来るの。私の部落ではないけど、金がない人はその蒙古人をいじめて、ひっぱたいたりして帰した」。おそらく、暴力で炭も奪い取ったのでしょう。だから「終戦のとき、その蒙古人たちに押し切りの刃で頭切られて死んだ人もいたわけ」。
ほかにも3人で侵入してきた「満人」の泥棒のうち、一人を撃ち殺した夫妻の家が終戦後に襲われ、一人で家にいた「奥さん」が「殺されて、裸にされて外にころがされていた」という話も……。関東軍の後ろ盾がなくなれば、少数派の日本人など多数派の現地人に敵うわけもありません。そもそも「男たちは根こそぎ動員されて、開拓団は女と子どもばかりになって」いたのですから。
敗戦色が濃厚になってきた時期、根津マツさんたちには「負けたらみな(ソ連軍の捕虜になどならず)自決しろって(関東軍から)毒薬」が渡されていました。しかし、彼女の村には少数ながら病気の十数名の男性が残っており、その中で指導的立場の男性が「早まったことはしないでくれろ」といったので、根津さんたちは服毒しなくて済んだのです。
ところが、日本に帰国するには子どもが邪魔ということで、自分の手で殺すか、「満人」たちに売りとばすか……という非情の選択を迫られるのでした。
根津さんはそのいずれも拒否し、あまりの空腹でビンの口をかじるしかない二人の子どもたちとの帰国を目指したものの、開拓団から見捨てられてしまいました。その後は、生きるために、自身の身を中国人男性に売り渡すしかありません。当時、満州の貧しい農村労働者の中国人の間で、妻とは「買うもの」だったからです。
その後、根津さんは満州の農村で中国人の妻として、暮らし続けました。
それでも根津さんは日本の家族と連絡が取れていたかなり幸福なケースで、昭和58年(1973年)、文化大革命の嵐が吹き荒れる中国から日本に永住帰国することができたのでした。中国人の夫も共に日本に行くことに同意していたそうですが、帰国2ヶ月前に亡くなったそうです(以上、陳野守正『「満州」に送られた女たち――大陸の花嫁』梨の木舎から)。

『興亜大鑑』より「大陸の花嫁たちの合同結婚式」/国立国会図書館蔵