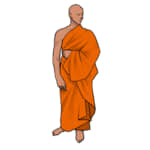日中戦争中に現地で撮影された戦争映画『土と兵隊』 国策映画の枠を超えたヒューマンドラマ【昭和の映画史】
■原作は火野葦平の『土と兵隊』
この映画には原作がある。火野葦平の『土と兵隊』で、『麦と兵隊』『花と兵隊』との三部作になっている。火野葦平は、日中戦争が生んだ国民的スター作家である。昭和12年(1937年)、30歳の時に招集されて杭州湾上陸作戦に従軍した。
翌年2月、上海で第6回芥川賞受賞の報を聞く。授賞式は陣中で行われ、日本から小林秀雄がやってきて賞を授与した。その立場に目をつけた陸軍が報道部に転属させ、火野は従軍作家となった。
一作目の『麦と兵隊』は徐州会戦の従軍記で、同名の歌も作られ、東海林太郎が直立不動で歌って軍国歌謡の名曲となっている。「徐州、徐州と人馬は続く」という歌詞も素晴らしい。
その後、 火野は実際に出征した人間ならではの身体感覚を持って、兵隊三部作を書いた。淡々とした従軍記だが、海の向こうで起きている戦争の実際を知りたい日本人に、火野の嘘のない誠実な筆致が受け入れられた。
原作は最後、中国人捕虜の斬首に立ち会った火野が目を背ける場面で終わっている。従軍している記者たちの傲慢な態度も在りのままに描いている。昭和15年(1940年)にはロンドンで、三部作全てが翻訳出版された。
宣教者の娘として中国で育ち、ピュリツァー賞とノーベル文学賞を受賞したアメリカ人作家パール・バックも、日本を批判していたにもかかわらず『麦と兵隊』を高く評価している。
敗戦後、この映画はGHQによる没収の対象となり、火野は社会からも集中的非難を浴びた。だが自伝的小説『花と龍』や、みずからの戦争責任に言及した『革命前夜』などを発表、生来の筆力で復活した。
昭和35年(1960年)は年頭から、昭和26年(1951年)のサンフランシスコ講和条約締結時に結んだ日米安保条約の改定へ向けて、社会に不穏な空気が流れていた。 そうした雰囲気の中で、火野は服毒自殺を遂げた。「死にます、芥川龍之介とは違うかもしれないが、或る漠然とした不安のために」と書かれたメモが遺されていた。
当時このことは伏せられ、13回忌に遺族が公表して社会に衝撃を与えた。時代背景や書き置きの内容などから類推するに、火野の脳裏に、日中戦争の象徴的存在となった過去の記憶が蘇ったのではないだろうか。
国民的人気を得た火野が、戦後に背負った十字架は重かった。しかし、あれは火野だけが負うべき十字架だったのだろうか。火野は筆力に恵まれ、一日本人として招集され、そこを陸軍に見込まれて従軍作家となり、多くの作品を書いた。火野が書いた作品を時系列で読み通してみると、日本人が見た日中戦争がどういうものだったか、その一端がうかがえる。
その後、兵隊三部作はほぼ忘れられて入手も困難になっていた。だが2013年、社会批評社から『火野葦平戦争文学選』全7巻が刊行され、『土と兵隊』は『麦と兵隊』と共に第1巻に収められた。2021年には角川文庫からも刊行されている。
ちなみにアフガンで井戸を掘り続け、銃撃で命を落とした中村哲医師は妹の子、つまり火野葦平の甥だった。

雨の中行軍する日本軍/『土と兵隊』より
国立国会図書館蔵
- 1
- 2