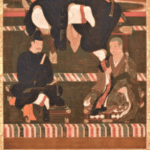江戸時代にUFOみたいな舟で「蛮女」が漂着!? 「虚舟」と渡来系氏族・秦氏にまつわる奇妙な伝承
日本史あやしい話
「虚舟」とは、何とも儚げな名前である。江戸時代の常陸国、そのとある浜辺に流れ着いた小舟のこと。記されていたのは曲亭馬琴が編纂した奇談集『兎園小説』(1824年刊行)で、「虚舟の蛮女」と題した怪しげなる話に登場する。面白いのはその形状で、まるでUFOを思わせるような奇妙なものだったからビックリ!さらにこの「虚舟」なる小舟、日本の発展に大きく寄与したとある人物も乗り込んだことがあるというから、目が離せない代物なのだ。いったい、どういうことなのだろうか?
■江戸時代の常陸国の浜辺に謎の「虚舟」が漂着
時は、享和3(1803)年2月のことである。舞台は、常陸国のとある浜辺だったとか。どこからやって来たのか定かではないが、浜の人々が沖合に何やら漂うものを発見。引き上げてみて驚いた。長さ三間(約5.5m)という小舟ながらも、まるでお香の入れ物(香盒)のような不思議な形だったからである。下半分は鉄板でしっかりと補強されて頑丈そうだが、上半分に透明な硝子窓がはめ込まれていたという、少々危なっかしい乗り物であった。
恐る恐る中を覗き込んでみると、床には敷物が敷かれ、二升(約3.6リットル)ほどの水が入りそうな小瓶や、菓子、肉を練ったような食べ物が置かれていた。さらにじっくりと中を見回して、ビックリ仰天。今まで目にしたこともないような顔立ちの女性がいたからである。蛮女と記しているところから察すれば、おそらく異国の女性だったのだろう。
もちろん、言葉が通じるはずもなかった。となれば、浜の人たちの困り果てた様相が思い浮かびそう。外国船が漂着した場合、薪と水を与えて追い返すようにとの「薪水給与令」が発せられたのは文化3(1806)年のこと。その3年前の当時としては、外国船となれば、有無を言わず打ち払うよう通達されていたからである。当然のことながら、無慈悲とは思いながらも、役人に知られては厄介とばかりに、そのまま再び沖合に押し流してしまったことも想像に難くない。
ちなみに、その舟と女性の様相は、同書に文章とともに挿絵として記載されている。そこに描かれた小舟は、まるで宇宙から飛んで来たUFOを思わせるような奇妙な形の乗り物であった。もしもそのお話自体が史実だったとすれば、本当にUFOだったのかも…と、勘ぐってしまいたくなってしまうのだ。
■インドからやってきた金色姫と養蚕の関係
実はこれと似たようなお話が、つくば市神郡の蚕影神社や神栖市日川の蚕霊神社、日立市の蠶養神社などにも伝わっているので見ておくことにしたい。それが、「金色姫伝説」と名付けられた奇妙な物語である。
舞台は常陸国豊浦の湊(日立市の小貝ヶ浜か。神栖市波崎の舎利浜との説も)で、舟の形が繭形の丸木舟だったというのが、前述の『兎園小説』と異なるところ。発見者は漁師の権太夫だったという。権太夫が舟を割ってみると、中から見目麗しい少女が現れた。どうやって言葉を通じさせたのか定かではないが、彼女の語るところによれば、インドの大王の一人娘だったとか。継母にいじめられて悲しむ姿を見かねた父の大王が、娘を桑の木をくり抜いて作った丸木舟に乗せて流したのだとも。
この少女の語りを聞いて哀れに思った権太夫、彼女を家に連れ帰って、我が子のように育てた。ただしその甲斐もなく、数年後に病を得て亡くなってしまったというから、何とも儚いお話である。
しかし、物語はここからが本題である。驚くことに、その亡骸がいつの間にか繭になった(彼女が持っていた箱の中に蚕の幼虫がいたとする話もある)と続けるのだ。生前の少女から教わっていたように、この繭で糸を紡いで機を織った。それが養蚕の始まりだったとして、物語の幕を下すのである。
なるほど、なるほど…と、一度は頷いたものの、はたと思い当たることがあって、首を捻ってしまった。確か、日本に養蚕を広めたのは、渡来系氏族・秦氏だったはずでは?ということを思い出したからである。
- 1
- 2