妻子ある男性との不倫で「毒婦」と批判された女優・松井須磨子 相手は妻そっちのけで「本気の恋」を歌に詠む
炎上とスキャンダルの歴史
■所属する劇団内で育まれた妻子ある男性との「不倫愛」
現代日本では、不倫愛が発覚した、あるいはその疑惑だけでも芸能人カップルに厳しい社会的制裁が加えられがちです。かつて江戸時代の役者たちは「スキャンダルも芸のこやし」と訳しうる「色気と度胸」という生活態度でOKだったのですが、明治維新後は、欧米から「演者も芸術家」という概念が日本にも輸入されたのです。
明治の世では「役者」ではなく、「俳優」という言葉が、演者に対して使われるようになりました。芸能の女神のアマノウズメノミコトのことを「巧作俳優(たくみにわざおぎす)(『日本書紀』)」と描いたときに使った言葉から生まれたのが「俳優」です。
「俳優」たるもの、世の尊敬を集めるべき立派な芸術家として、私生活を慎むべし……劇団である文芸協会演劇研究所(以下、文芸協会)を主催する「演劇界のドン」坪内逍遥は性的なモラルに厳しいのでした。
その逍遥の一番弟子で、文芸協会を彼と率いていた島村抱月が、劇団の女優・松井須磨子と不倫の渦中であることを島村の妻・いち子から知らされた逍遥の衝撃は凄まじかったでしょうね。
逍遥も若き日には、根津遊郭の娼妓だった鵜飼センという女性を見初め、3年かけて通い詰め、彼女を妻に迎えた程度にはあれこれ経験しているのです。しかし1913年(大正2年)、不倫愛がきっかけで文芸協会を退所することになる島村抱月は当時42歳(ちなみに妻・いち子は40歳)。「名門」島村家の従順な婿養子として、若いころから文学研究一筋だった人生に「このままでいいのか」という疑問を抱いていたようです。
「こしかたの三十年は長かりき砂漠を行きてオアシスを見ず」
――これは須磨子との本気の恋を経験した抱月が、自分の約30年の人生を「砂漠」に、そして須磨子との愛情生活を「オアシス」に例えた抱月の歌です。
ほかに
「ある時は二十の心ある時は四十の心われ狂ほしく」
という歌もあって、恋している自分は二十代のようだ。しかしある瞬間には四十代の本来の自分が目を覚まし、「道ならぬ恋にうつつを抜かしているところではない」という反省が訪れる。そういう気分の落差が悩ましすぎる……と抱月は嘆いているのです。
上手といえない恋歌だからこそ、逍遥にとって須磨子への恋が「初恋」であったことが透けて見えるようで、なんともいえなくなります。
逍遥の妻・いち子はたいへん傷ついたでしょう。抱月がこの歌を発表したのは『早稲田文学』でしたから……。抱月・須磨子の師である逍遥の目にも止まることは確実でした。
逍遥も両者に不倫を止めるよう、何度も諭したのですが、結局、二人は逍遥の言うことを聞かず、抱月は文芸協会役員を辞任、須磨子は文芸協会脱退という道を選びます。
須磨子は抱月の家庭を壊した「毒婦」として、新聞・雑誌の批判の的となりました。しかし、スキャンダルが女優・松井須磨子にとってはむしろ追い風となったのです。
ちなみにこのとき、須磨子は27歳。俳優・田中圭さんとの不倫愛の「疑惑」だけで、数あったCMの大半を降板させられた永野芽郁さんは現在25歳。
永野さんが「清純さ」や「透明感」をセールスポイントにしていたのとは異なり、永野さんとほぼ同年代の須磨子は「バツ2」という経歴を隠さず、家を飛び出していく人妻・ノラ(イプセン『人形の家』)などを当たり役とする「個性派女優」でした。
それゆえに文芸協会から独立後、芸術座という新劇団を結成した抱月と須磨子――とりわけ「毒婦」とさえ呼ばれた須磨子の姿をわが目で見ておきたい観客たちが彼らの舞台に押し寄せたのです。

『カルメン』の扮装姿の松井須磨子/『松井須磨子 : 新比翼塚』より
国立国会図書館蔵


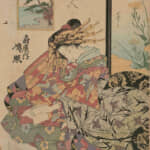

-150x150.png)
-150x150.jpg)
