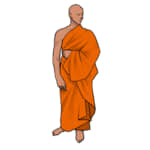戦後の国鉄三大ミステリーのひとつ「下山事件」の真相は… 『日本の熱い日々 謀殺・下山事件』【昭和の映画史】
■GHQ占領下で製作された、民主主義を讃える大ヒット映画
前回取り上げた『青い山脈』が公開されたのは、昭和24年(1949年)のことである。この映画では封建的気風に立ち向かう女性教師と女学生が描かれて、戦後民主主義が高らかに謳い上げられた。
しかし戦後民主主義はこの頃、早くも曲がり角を迎えていたのである。ずっと押さえつけられていた労働運動は、敗戦によって活発化した。日本に民主主義を確立することを目指したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)内のリベラル派は、組合の勢力拡大を容認した。
そこで活動家たちはGHQの後ろ盾を期待して、昭和22年(1947年)2月1日にゼネラルストライキを計画した。しかし、すでにソ連との対決を意識していたアメリカは、組合運動がこれ以上拡大することに懸念を抱く。結局2.1ゼネストは、前日にマッカーサー司令官の命で中止となったのである。ここに「逆コース」が始まった。
東西冷戦の影が忍び寄り、GHQは方針を転換した。だが、労働運動はすぐには衰退しなかった。『青い山脈』が公開された昭和24年には、戦後史に残る怪事件である国鉄三大ミステリー事件が起こる。
三つの事件は下山事件、三鷹事件、松川事件の順に起きた。下山事件は7月6日、当時の下山国鉄総裁が出勤途中で行方不明になり、翌日に常磐線の北千住・綾瀬間の線路で轢死体となって発見された事件である。
三鷹事件は9日後の15日に起きた。中央線三鷹駅で無人列車が暴走し、死者6人、負傷者20人を出した。さらに8月17日には、東北本線の松川・金谷川間でレールが外され、脱線して死者が3人出たのである。
7月と8月の2ヶ月の間に、国鉄をめぐる不可解な事件が連続して起きたのだ。中でも最大の謎は下山事件である。この事件には当時の世相が深く刻まれている。米ソ対立が本格化する中、GHQは日本を、アジアにおける共産主義陣営への防波堤とすることを決める。そのためには社会の安定、特に経済の立て直しが必要だった。
そのため、ドッジラインに基づく緊縮財政と公務員の人員整理(解雇)を求めたのである。特に国鉄には、約10万人という大量の解雇を迫ったのだ。しかし、1月に実施された総選挙で野党が躍進した勢いもあり、組合は強く反発した。下山総裁は労組との難しい交渉に対応しており、事件前日に3万人に第一次人員整理を通告したところだった。
そこで、下山事件は他の二つの事件ともども組合員によるもので、共産党が関係しているということになったのである。三鷹事件は国鉄の組合員11人が起訴され、10人は無罪、1人に死刑判決が下った。
松川事件では国鉄の組合員10人と東芝の組合員10人、合計20人が起訴された。しかしアリバイが成立して全員無罪となった。三鷹事件の元死刑囚についても冤罪疑惑があり、2024年には長男によって、3回目の再審請求がなされている。
最大の謎となった下山事件は物証が多く、目撃者もいて、遺体発見直後から様々な憶測が飛んだ。メディアの中心にいた新聞も、それぞれ自殺説他殺説を主張した。法医学的見地からも、東大と慶應大が激しい論争を繰り広げた。
しかし結局、未解決のまま昭和39年(1964年)、東京五輪の直前に時効となったのである。しかし謎は残ったままだ。戦後日本を代表する社会派推理作家の松本清張も、GHQ占領下で起きた怪事件を独自に解釈した『日本の黒い霧』で、下山事件を大きく取り上げている。
その後も多くの関連書籍が世に出た。それぐらい、背後に深い闇を感じさせる怪事件だったが、今ではGHQ関与説がほぼ定説になっている。昨年4月にNHKが放映した『未解決事件』File10も、その立場を取っている。オンデマンドで視聴できる。
- 1
- 2